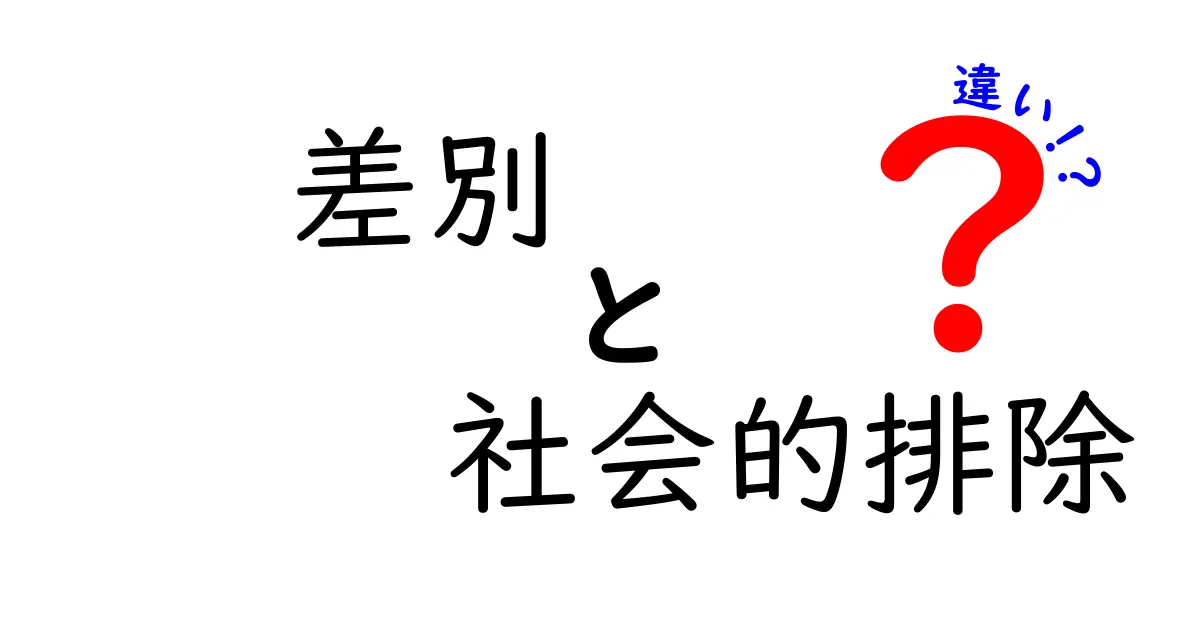

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
差別・社会的排除・違いの違いを学ぶ総論
この話題を始めるとき、多くの人は「差別」と「社会的排除」という言葉が混同されやすいと感じます。似ているようにも見えますが、実は意味も起こる場面も違います。差別は考え方や判断の偏りから生まれ、特定のグループに対して不公平な扱いを生みやすいです。一方、社会的排除は制度や社会の仕組みの中で人が取り残され、参加や機会を奪われることを指します。違いは「誰が/どこで/どう扱われるか」という視点の違いです。ここでは三つの言葉を別々に理解し、それぞれが私たちの毎日にどう影響するかを見ていきます。
まずは言葉の影響を身近に感じることが大切です。日常の場面で、発言が誰かを傷つけたり、誰かの機会を奪ったりしていないかを自分に問い直す習慣をつくると良いでしょう。「違いを認めること」と「差別を正当化すること」は別の話です。差別は人を劣って扱う理由になりえますが、違いを尊重する心は、学校や地域をよりよくする力になります。
差別とは何か
差別とは、ある集団の人々を生まれつきの特徴や信念、出身地、性別、年齢、障害の有無などを理由に、不公平な扱いをする考え方や行動のことを指します。それは偏見に基づく判断であり、事実と異なる先入観次第で広がってしまいます。差別の現場は、学校の配慮の不足、職場での昇進の機会の不均等、地域社会での言葉の暴力など、さまざまな形で現れます。たとえば、同じ才能を持つ生徒なのに、性別や出身地のせいでチャンスが減ってしまうようなケースがそうです。差別は日常のちょっとした言い回しにも潜み、気づかないうちに人を傷つけることがあります。こうした状況を見つけたら、ただ黙って見過ごすのではなく、友達や先生に相談したり、説明を求めたりすることが大切です。
社会的排除とは何か
社会的排除は、制度や社会のしくみの中で人々が社会の一部の機会から取り残され、参加できない状態を指します。これは「見えない壁」があちこちにあって、教育、医療、仕事、居場所といった基本的な機会を奪われることです。例えば、情報が不十分なために学習の機会を失う子ども、交通手段がなく通学が困難になる人、障害がある人が公共の場での参加を難しく感じる場などが挙げられます。社会的排除は個人の努力だけではなく、社会全体の制度や文化の影響を強く受けます。したがって、排除を減らすには、学校のバリアフリー化や地域の支援制度の整備、情報へのアクセスの改善といった「仕組みの変革」が必要です。私たちは日常生活の中で、誰かの参加を妨げる行動や環境を見つけたら、改善のための行動を起こせるよう心がけるべきです。
違いとは何か
ここでの「違い」は、人や物事がもつ性質の違いを指す中立的な意味です。生物学的な特徴、出身地、言語、趣味など、違い自体は悪いことではありません。それを盾にして誰かを排除したり、劣って扱ったりすることが問題です。つまり、「違い」を尊重することと、「差別・排除を正当化すること」は別の話です。私たちが目指すべきは、違いを認めつつ、互いの権利と機会を公平にする社会です。視点を変えれば、差別も排除も起きにくくなり、みんなが安心して学び、働き、遊べる場所が増えます。具体的には、授業や職場での相互理解を深める話し合い、学校行事の多様性を尊重するプログラム、アクセスのしやすい情報提供などを通じて、違いを力に変える取り組みが求められます。
ここまでの説明を通じて、差別・排除・違いの三つの概念が互いに影響し合いながら日常生活に現れていることが見えてきます。私たちはまず自分の言動を振り返り、意図せず他者を傷つけていないかを点検する習慣を持つことが大切です。さらに、社会の仕組みを変える小さな一歩を積み重ねることが、未来の子どもたちにとって公正で居心地の良い世界を作る第一歩になります。
放課後、友達AとBが差別について雑談している場面を想像してみてください。Aは『差別って、特定の特徴を理由に人を下に見る考え方だと思う』と言い、Bは『その一歩先には社会の制度やルールが絡んでくるんだ。学校のルールがみんなに同じ機会を提供していないと、排除に近づくことがある』と続けます。私たちはここで、差別の根っこにある偏見を正すことと、社会のしくみを変える取り組みの両方が必要だと深く感じます。だからこそ日々の会話や行動で、相手の違いを認める練習を続け、誰もが参加できる場づくりに参加することが大切だと、私は友達と話していて改めて思いました。友達同士の小さな気づきが、やがて大きな変化へとつながるのです。





















