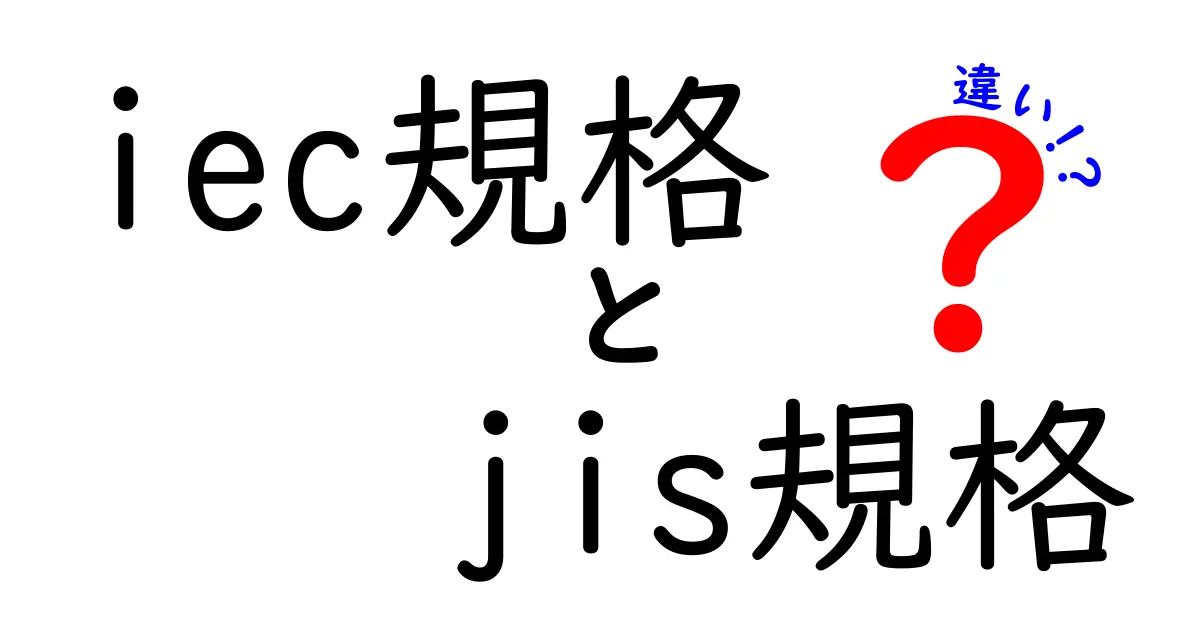

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
IEC規格とJIS規格って何?基本の違いをわかりやすく説明します
世界にはたくさんの製品や技術のルールがあります。その中でも、IEC規格とJIS規格はよく聞く言葉ですよね。IEC規格は「国際電気標準会議」が作ったルールで、世界共通の基準を目指している規格です。一方、JIS規格は「日本工業規格」のことで、日本だけで使われる基準です。
この違いが意味するのは、IEC規格は国際的に共有しているので、多くの国で同じ基準で製品が作られたり検査されたりするのに対し、JIS規格は日本の産業や生活に合わせて作られたものということです。
つまり、IEC規格はグローバル対応、JIS規格は国内対応というイメージを持つとわかりやすいでしょう。
なぜIEC規格とJIS規格があるのか?仕組みと目的の違い
IEC規格は、世界中の技術者や企業が同じルールを使うことで、製品の安全性や互換性を保つために作られています。たとえば、電気製品がどの国でも同じ安全基準を満たしていると、海外での販売がスムーズになるのです。
一方で、JIS規格は日本の市場や技術に特有な事情を反映して作られています。気候や文化の違い、日本独自の生産方法などに合った基準を設定することで、日本の消費者やメーカーが使いやすい製品作りをサポートしています。
このように、IEC規格が「世界の共通言語」なら、JIS規格は「日本のローカルルール」と言えるでしょう。
IEC規格とJIS規格の具体的な違いを比較表でチェック!
IEC規格とJIS規格の関係と将来の展望
実は、JIS規格はIEC規格を参考に作られることが多く、両者は互いに影響しあいながら発展しています。
近年ではグローバル化が進み、日本もIEC規格を積極的に取り入れる傾向にあります。これにより、日本製品の海外での品質信頼度が高まるので、企業にとってもメリットが大きいのです。
それでもJIS規格は日本の消費者や産業に合った細かいルールとして大事にされています。
将来的には、IEC規格とJIS規格の融合や調和がさらに進み、世界と日本、両方に適した基準が増えていくでしょう。
IEC規格という言葉は聞いたことがあっても、実際どんな団体が作っているのかは意外と知られていません。国際電気標準会議(IEC)は、電気や電子の製品で世界の安全と性能を統一するために設立されたんです。
面白いのは、参加している国も多く、各国の専門家が集まって、それぞれの意見を調整しながらルールを決めるということ。だから、IEC規格に合った製品は、どの国でもほぼ同じ基準で使えるというわけです。
この国際的な協力の仕組みって、実はすごく高度な“会議の技術”の結晶なんですよ!
前の記事: « 【篭と籠の違い】漢字の選び方と使い分けを徹底解説!
次の記事: 表示灯と誘導灯の違いって何?わかりやすく解説! »





















