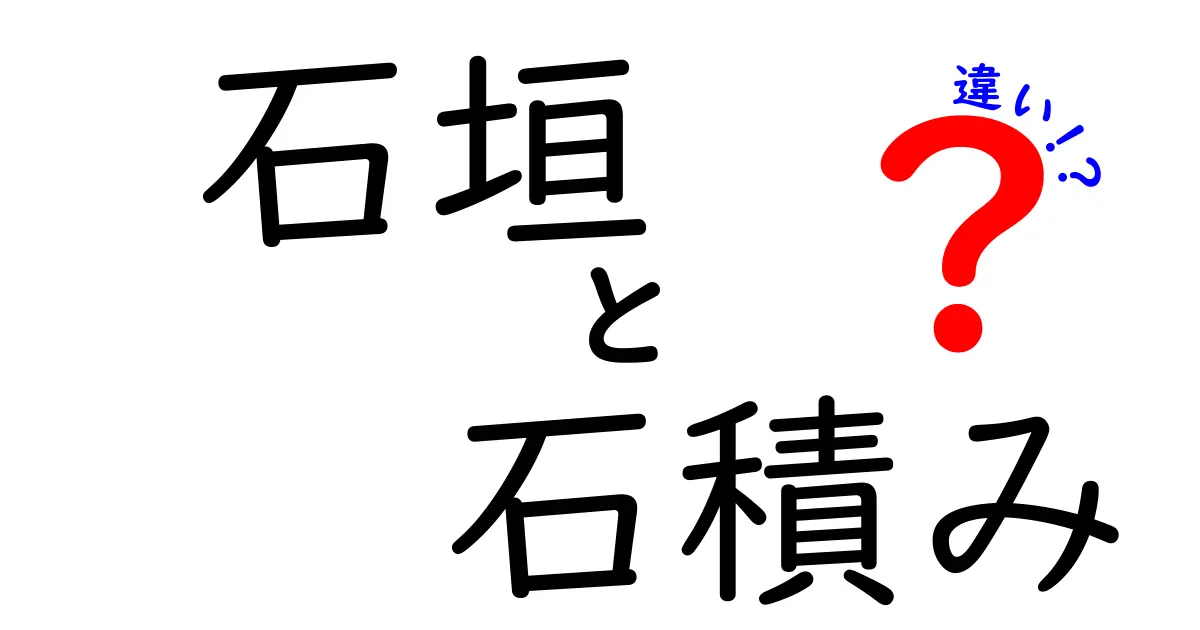

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
石垣と石積みは何が違う?まずは基本の意味を押さえよう
日本の風景によく見られる石垣と石積み。どちらも石を積み重ねて作られていますが、実はその意味や使われ方には違いがあります。
石垣は主に城や庭園、農地の境界などに使われる、石でできた壁のことを指します。防御や土地の区画、斜面の保護などの目的があります。
一方、石積みは石を積んでつくる技法や工法を指し、石垣も石積みの一種と言えます。つまり、石積みは石を積む行為・技術全般であり、石垣はその成果物のひとつです。
このように、石垣は形や用途で区別された建造物であるのに対して、石積みは石を積み上げる技術や方法そのものを示しているのです。
石垣の役割と特徴:歴史や機能面から見る違い
石垣は日本の歴史上、特にお城の建築で重要な役割を果たしました。
主に敵からの攻撃を防ぐ防御壁として築かれ、土地を安定化させる〈護岸・斜面崩壊防止〉の役割もあります。
石垣はただ石を積み重ねるだけでなく、石の選び方、形状、積み方に多様な技術が駆使されています。たとえば、城の石垣は
- 「打ち込みはぎ」:石を平らに切りそろえて隙間なく組み合わせる技法
- 「野面積み」:自然の石の形を活かして積む技法
など、多彩な石積み方法が使われています。
このような石垣は建築物の美しさや強さの証明であり、石積みの技術の高さが反映されています。
石積みの種類と作り方:構造の違いが耐久性や見た目に影響
石積みはそのやり方や目的によって種類が分かれます。
主な石積みの方法は以下の通りです:
- 野面積み(のづらづみ)
石の自然形を活かした粗い積み方。古くからある伝統的な技法で、山や野原で採れた自然石をそのまま使うことが多いです。 - 切石積み(きりいしづみ)
石を加工し、形を整えてから積む方法。隙間が少なく、壁の強度が高くなるのが特徴です。城の石垣によく見られます。 - 乱積み(らんづみ)
大小さまざまな石を、自然の形状を残しつつ無作為に積むスタイル。景観や園芸で多用されます。
それぞれの方法は耐久性、見た目、使う石の種類によって適切な使い分けが必要です。
次の表は石積みの特徴をまとめたものです。
| 石積みの種類 | 特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 野面積み | 自然石そのまま。隙間が多いが自然な雰囲気 | 古い城壁、農地の石垣、庭園 |
| 切石積み | 石を加工し平らにして隙間が少ない | 城の石垣、重要建築物 |
| 乱積み | 大小色々な石を無造作に積む | 庭園や景観、石垣以外の壁 |
これに対し、一般的な「石積み」と「石垣」の違いは目的と完成形により分けられる点にあります。石積みはいろんな用途のための技術全般で、石垣はその技術で形作った壁ということです。
石積みの中でも『野面積み』は、実は石の自然な形状や風合いを活かす、とても伝統的な工法です。昔は山から採った石をそのまま積んでいたため、見た目も自然で素朴。そのため社寺の境内や農村の石垣でよく見られます。現代では庭園や公園のデザインで、この自然な石積みの味わいが再評価されています。自然のままの石を使うので石職人の置き方の技術が特に求められ、まさに職人技の見せどころでもあるんですね。
次の記事: 防水と防汚の違いをわかりやすく解説!知っておきたいポイントとは? »





















