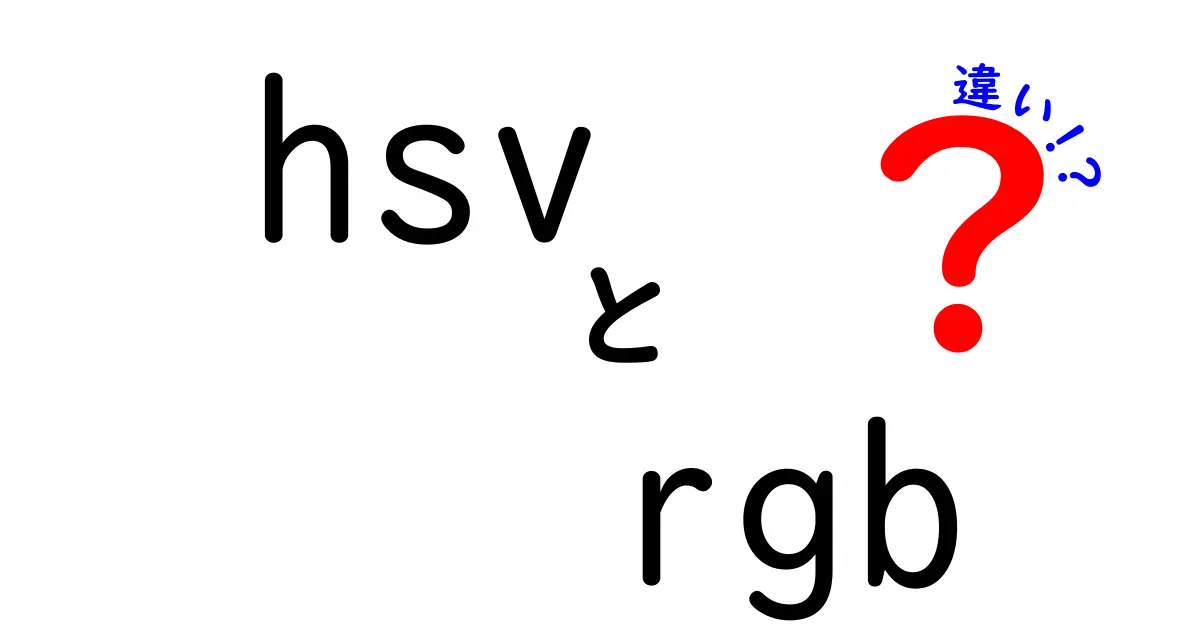

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
HSVとRGBって何?基本の色の表し方を知ろう
色を表す方法にはいろいろありますが、HSVとRGBはとてもよく使われる2つの色の表し方です。
まず、RGBは赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)の3つの色の光の強さを組み合わせて色を作る方法です。テレビやパソコンの画面で多く使われています。
一方、HSVは色の性質を色相(Hue)、彩度(Saturation)、明度(Value)で表す方法です。これは色をより直感的に理解しやすい形で表現しています。
この2つは目的や使い方が違うので、それぞれの特徴や違いを知ることが大切です。
RGBとHSVの違いを詳しく見てみよう
それでは、具体的にRGBとHSVの違いについて説明していきます。
- RGB(赤・緑・青): 光の3原色で、0から255までの数値で色を決めます。全ての値が0なら黒、最大(255)の場合は白や明るい色になります。主にデジタルのディスプレイで使われています。
- HSV(色相、彩度、明度): 色相(0°~360°)で色の種類を示し、彩度(0~100%)で色の鮮やかさ、明度(0~100%)で明るさを表します。絵を描くときや色調整に便利です。
以下の表で違いをまとめました。
彩度・明度:0~100%
このように、RGBは機械側の色の扱いに強く、HSVは人間がイメージしやすい色の操作に向いています。
色変換ができる理由と使い分けのポイント
面白いことに、RGBとHSVは相互に変換できるため、デザインソフトやプログラムで色を切り替えて使うことが多いです。
この変換は、数学的な計算でRGBの数値からHSVの色相・彩度・明度を求めたり、その逆をしたりします。
例えば、赤のRGBは(255, 0, 0)ですが、HSVでは色相が0度、彩度100%、明度100%となります。
使い分けとしては、
- 色を直接指定したいときはRGB
- 色味や明るさを調整したいときはHSV
が基本です。
この仕組みを理解すると、パソコンで色を選ぶときなどに迷わず目的の色を探せるようになります。
色相(Hue)って数字で表せるのは驚きですよね。0度が赤、120度が緑、240度が青など、色の環が回るように数字が決まっています。この仕組みは、色の種類を数値で簡単に理解できるので、デザインや絵を描くときに大活躍します。実はこの色相の数字をいじるだけで色味がガラリと変わるので、色作りの楽しみが広がりますよ!
次の記事: 色と視認性の違いとは?見やすさを左右するポイントを徹底解説! »





















