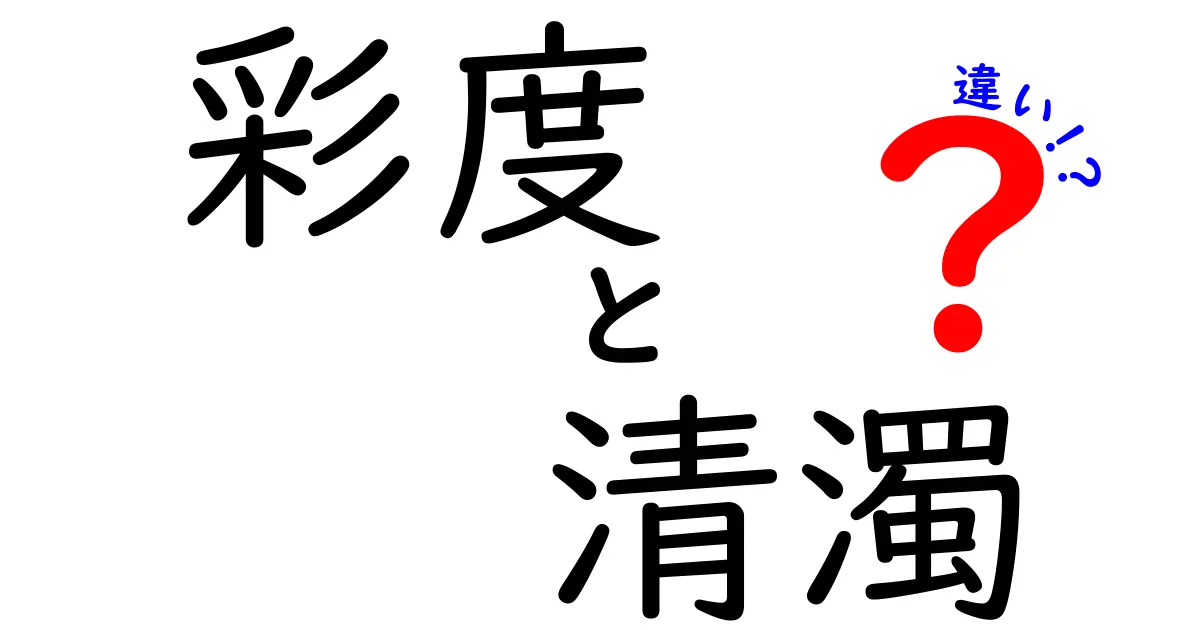

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
彩度と清濁とは何か?色の基本用語を理解しよう
色を感じたり説明したりするとき、よく出てくる言葉に「彩度」と「清濁」があります。この二つは色の印象を大きく変えるとても重要な概念です。簡単にいうと、彩度は色の鮮やかさの度合い、つまり色の強さや鮮明さを表します。例えば真っ赤なリンゴは彩度が高い赤色です。彩度が高い色は見た目がはっきりしていて明るく感じます。
一方で清濁は色の清らかさや透明感のことを指しています。色がどれだけ透明で澄んでいるか、濁っているかを説明する言葉です。例えば、透き通った青空の色は清い色で、泥水の色は濁った色です。このように、彩度と清濁はどちらも色を深く理解するために欠かせないポイントなのです。
彩度と清濁の違いをもっと詳しく解説
彩度は主に色の「鮮やかさ」「強さ」を示します。科学的には色の純度とも言われ、白や黒を混ぜることなく純粋な色の濃さが高いほど彩度は高くなります。例えば、赤色に白を加えるとピンクになり、彩度は下がります。
清濁はもう少し感覚的な要素が強いです。色が透き通っていて澄んで見えることを「清い」と言い、透明感があり、混ざりけが少ない印象です。それに対して、くすんだり混ざりけが多い色は「濁っている」と表現されます。例えば、水彩絵具で色を混ぜすぎてどんよりした色になると濁った色になります。
彩度と清濁は似ているようですが、彩度は色の濃さ、清濁は色の透明感や純度に近い感覚、という違いがあります。
彩度と清濁の違いをわかりやすく表で比較してみよう
まとめ
彩度と清濁はどちらも色の性質を説明する言葉ですが、彩度は色の強さや鮮やかさ、清濁は色の透明さや濁りを示します。これらの違いを知ることで色の表現がもっと豊かに、正確になります。日常生活や芸術作品、デザインなどでも役立つ知識なので、この機会にぜひ覚えておきましょう。
「彩度」の話を深掘りすると、実は人によって色の彩度の感じ方が微妙に違うことが面白いです。同じ赤でも鮮やかだと感じる強さは人それぞれ。また、彩度が高い色は目に強く刺激を与えるため、派手に見えたり注意を引きやすくなります。だから広告やファッションでよく使われるんですよ。意外と彩度は心理にも影響を与える重要な要素なんです。
前の記事: « カラーとブランドカラーの違いとは?わかりやすく解説!





















