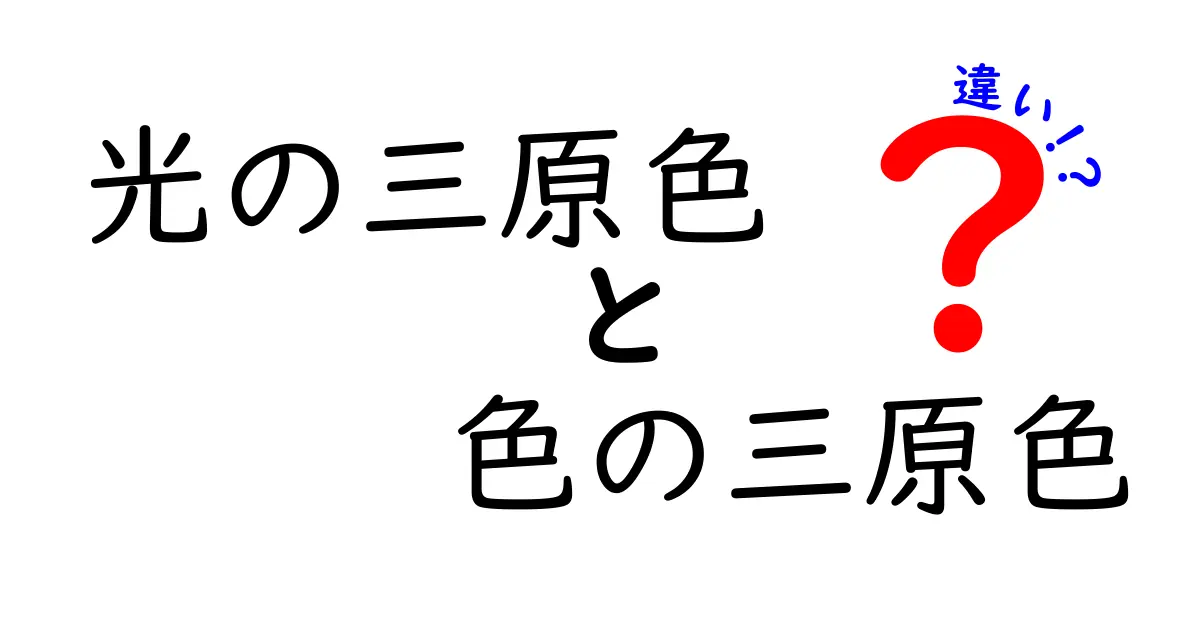

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
光の三原色と色の三原色の基本的な違い
私たちは普段、色を見たり感じたりしていますが、その色のしくみには大きく分けて「光の三原色」と「色の三原色」があります。
光の三原色とは、光の世界で色を作り出す3つの色のことで、赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)の3色を指します。これらを組み合わせることでさまざまな色が作られます。
一方、色の三原色は、絵の具や印刷などの「色のもの(物質)」の世界で使う3色で、シアン(Cyan)、マゼンタ(Magenta)、イエロー(Yellow)の3色です。これらを混ぜることで色を表現します。
このように根本的に使われる場所が異なり、「光の三原色」は光を使った色の表現、「色の三原色」は物質で色を表現する方法なのです。
光の三原色と色の三原色の仕組みと応用
それぞれの三原色は、色の仕組みとしても性質が違います。
光の三原色は「加法混色」という方法で色ができています。これは3つの光を重ねていき、足していくことで色が明るくなり、すべての光が合わさると白色になります。テレビやスマートフォンのディスプレイがこの仕組みを使っています。赤と緑の光を混ぜると黄色、緑と青を混ぜるとシアン、赤と青ではマゼンタができます。
色の三原色は「減法混色」という仕組みです。これは絵の具などの色の物質が光を吸収し、一部だけ反射することで色を見せています。シアン・マゼンタ・イエローを混ぜ合わせると黒に近づきます。印刷物や絵画ではこの方法が使われています。
それぞれの方法には特有の応用例がありますので、生活の色々な場所で活躍しています。
光の三原色と色の三原色の違いを理解しやすい表
下の表は、光の三原色と色の三原色の違いを簡単にまとめたものです。
この表を見ると、光の三原色と色の三原色がどれだけ違う考え方や仕組みで成り立っているかがよくわかります。
どちらも重要ですが、使われる場面によって使い分けられていると言えます。
まとめ:光の三原色と色の三原色の違いを知ろう
今回は「光の三原色」と「色の三原色」の違いについて詳しく説明しました。
・光の三原色は光を使った色の表現で、赤・緑・青の3色
・色の三原色は物質(絵の具など)で色を表現し、シアン・マゼンタ・イエローの3色
・光の三原色は加法混色、色の三原色は減法混色という仕組みの違い
この違いを理解すると、普段見ているテレビ画面や印刷物の色の秘密が見えてきます。
ぜひ、色の世界にもっと興味を持って楽しんでくださいね!
色の三原色に使われる「マゼンタ」って実は見慣れている赤や青とは少し違う色です。マゼンタは赤と青の間にある紫に近い色ですが、光ではなく絵の具などの減法混色の世界で使われます。興味深いのは、光の三原色にはこのマゼンタが含まれていないこと。これはマゼンタが光の色ではなく、物質の色だからです。日常の絵の具や印刷で見かけるマゼンタはまさに色の三原色の大切な一角なんですよ!





















