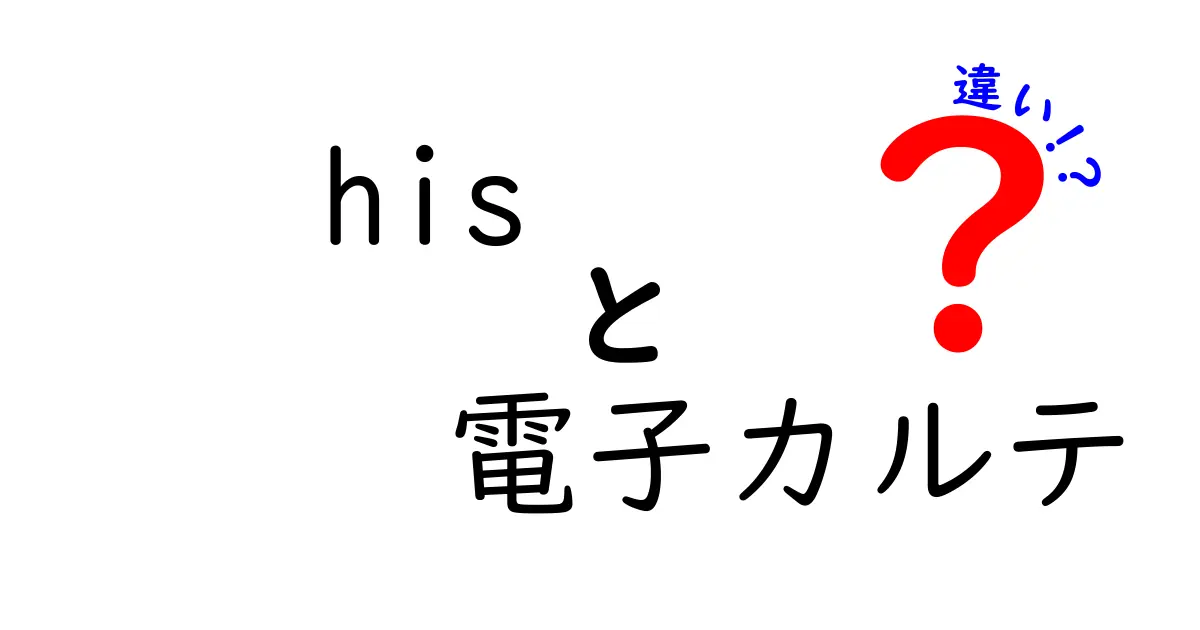

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
HISとは?電子カルテとは?基本を押さえよう
まずは、HIS(Hospital Information System)と電子カルテ(Electronic Medical Record:EMR)の違いをはっきり理解することが大切です。
HISは病院全体の情報を管理するシステムであり、診療以外の事務的な作業や患者情報の管理を効率化することを目的としています。具体的には患者の予約管理、会計、検査結果の管理、病院のスタッフ間での情報共有などが含まれます。
一方で電子カルテは、医師が患者の診察内容や検査結果、治療歴などの診療記録を電子的に残すシステムです。紙のカルテをパソコンに置き換えたものとイメージしてもらうとわかりやすいでしょう。つまり、HISは病院全体の情報を扱い、電子カルテは診療記録の専門システムといえます。
なぜ違いが重要なの?
この違いを理解しないと、病院のIT導入や運用で混乱することがあります。
例えば、新しい情報システムを導入するとき、電子カルテだけでなくHIS全体の連携が必要です。
また、医療関係者がシステムの操作やトラブル対応をする場合、何がHISの仕事で、何が電子カルテの機能か知ることは大切です。
つまり、違いは病院のIT活用を成功させるために欠かせない基礎知識。
HISと電子カルテの具体的な違いを表で比較
より具体的に、両者の違いを見てみましょう。下の表は機能・役割、利用者、対象情報の観点で比較したものです。
| 項目 | HIS(Hospital Information System) | 電子カルテ(Electronic Medical Record) |
|---|---|---|
| 目的・役割 | 病院全体の情報管理。予約・会計・検査・勤務管理など多機能。 | 患者の診療記録を電子的に記録・管理。主に医師が使用。 |
| 主な利用者 | 医師、看護師、事務職員、検査技師など病院スタッフ全員 | 主に医師、時に看護師や診療補助スタッフ |
| 扱う情報 | 患者情報全般、病院運営データ、検査結果、会計情報など | 患者の病歴、診察メモ、処方情報、検査結果など診療情報に特化 |
| 導入範囲 | 病院全体の業務をカバー | 診療現場のカルテ管理に限定 |
HISと電子カルテは連携して初めて効果的に機能する
上の表からわかるように、HISと電子カルテは異なる目的を持ちながらも連携して動くシステムであることがポイントです。
例えば、診察が終わると、電子カルテに記録された診療内容がHISに取り込まれ、会計処理や患者管理に利用されます。
この連携により、医療現場の効率化やミス削減が実現しています。
つまり、HISが病院の“司令塔”なら、電子カルテは“医師のメモ帳”といった役割分担だと考えるとイメージしやすいです。
まとめ:HISと電子カルテの違いを押さえて医療のIT化を理解しよう
この記事では「HISと電子カルテの違い」についてわかりやすく解説しました。
ポイントを整理すると
- HISは病院全体の情報管理システムで多機能
- 電子カルテは診療記録に特化した医療記録システム
- 両者は異なるが密接に連携し医療現場の効率アップを支える
この違いを知ると、病院のITシステムがどんな構造で動いているかイメージしやすくなります。
今後、医療の現場ではさらにデジタル化が進むため、本記事の基本知識を押さえておくことは非常に役立ちます。
HISと電子カルテの正しい理解が、より良い医療サービスに繋がる第一歩となるでしょう。
電子カルテは医師が患者の病状や治療経過を記録する重要なツールですが、実は紙のカルテと比べて検索が速く、情報の共有も簡単です。例えば、昔は探すのに時間がかかった過去の診療記録も、電子カルテなら数秒で表示可能。これにより医師は効率良く診療に集中できるんです。ちなみに電子カルテには画像や検査データも同時に保存できるので、ただのメモ帳以上の役割も果たしています。学生の皆さんも、将来の医療現場で電子カルテの進化に注目してみてはいかがでしょうか?
次の記事: 紙カルテと電子カルテの違いとは?わかりやすく徹底解説! »





















