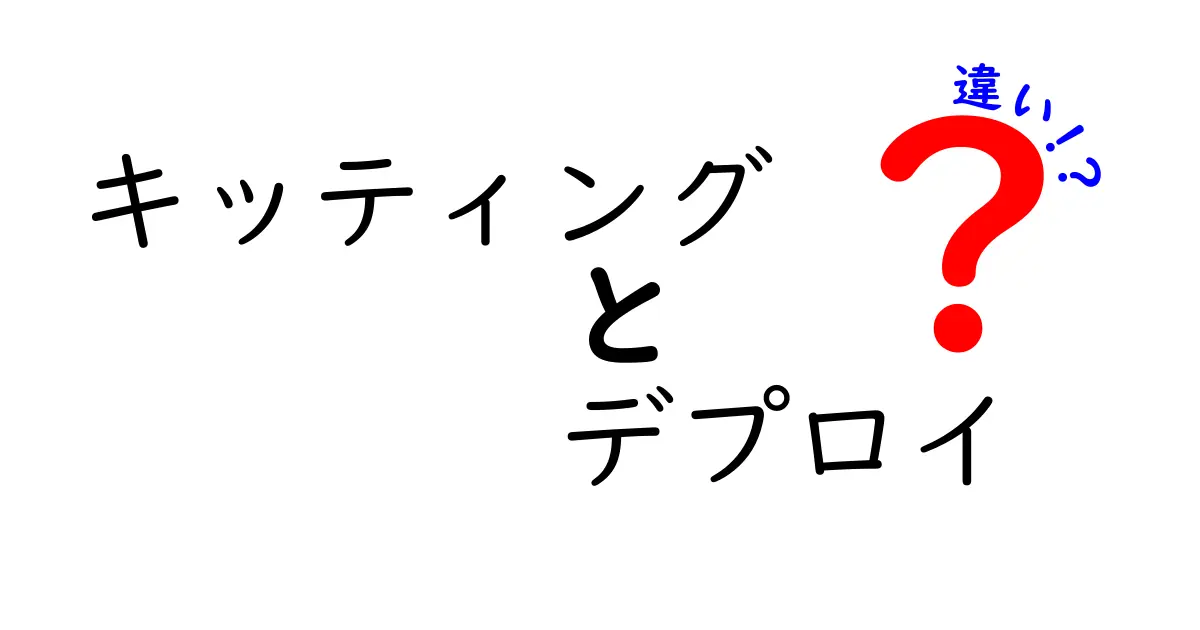

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
キッティングとデプロイとは何か?基本の理解から始めよう
近年、IT機器の導入やシステム展開に関わる仕事でよく耳にする言葉、「キッティング」と「デプロイ」。この二つは似ているようで異なる意味を持っています。
まず、キッティングとは何かを説明します。キッティングは主にパソコンやスマートフォンなどのIT機器を、会社や組織で使うために必要なソフトウェアのインストールや設定、周辺機器の接続などをまとめて準備する作業を指します。簡単に言うと、「IT機器を使える状態にセットアップする」ことです。
一方、デプロイは、開発したソフトウェアやアプリケーションを、実際にユーザーが使える環境へ配置し、稼働させることを意味します。ソフトウェアを公開して本格的に動かし始める作業だと理解すると良いでしょう。
こうした基礎的な説明だけでも、両者の違いが少し見えてきますね。
キッティングとデプロイの具体的な違いを詳しく解説
さらに詳しく両者の違いを知るため、表で比較してみましょう。
| 項目 | キッティング | デプロイ |
|---|---|---|
| 意味 | IT機器を使える状態に準備する作業 | ソフトウェアを実際の環境に配置し稼働させる作業 |
| 対象 | ハードウェア(パソコンなど)およびその設定 | ソフトウェアやシステム |
| 主な作業内容 | ソフトのインストール、設定、検証、周辺機器接続 | コードの配置、環境設定、動作確認、公開 |
| タイミング | 機器導入時や機器の入れ替え時 | ソフトウェアの新規公開や更新時 |
| 目的 | 機器の利用開始準備 | ソフトの運用開始 |
この表から分かるように、キッティングはハード面を中心に据えた準備作業であるのに対し、デプロイは主にソフト面にフォーカスした運用開始の作業です。
たとえば、新しいパソコンを会社に導入する際、そのパソコンに必要なソフトを入れてネットワーク設定をするのがキッティング。その後、新しい業務システムをお客様に提供する時、サーバーにソフトを置いて実際に使えるようにするのがデプロイとなります。
なぜキッティングとデプロイの違いを理解することが重要なのか?
ITの現場では、仕事の内容や責任範囲を正確に把握することが成功の鍵となります。
キッティングとデプロイは似て非なる作業であり、混同すると効率が悪くなりトラブルの元になることもあるからです。
たとえば、キッティングの仕事であるはずの機器設定を飛ばしていきなりデプロイだけを行うと、ユーザーが使えない状態でソフトを公開してしまうこともあります。
また逆にデプロイ担当がキッティング作業まで請け負うと、想定外の手間がかかったり納期が遅れたりします。
このように、両者の違いを正しく理解し役割を分けることが、スムーズで確実なIT導入を実現するために非常に大切です。
さらに、この理解をもとにスキルを磨けば就職や転職時にも大きな武器になります。
IT初心者さんもまずは基本的な違いをしっかり押さえておくことをおすすめします。
キッティングでよく知られているのは、パソコンのセットアップ作業ですが、実は"キッティング"という言葉自体は英語の"kitting"から来ています。元々は工場などで部品をまとめてセットにする意味で使われ、ITの世界においても、複数の機器やソフトを一括して"まとめセットアップ"する作業として使われています。こう考えると、単なるインストールだけでなくちょっとした"梱包作業"のようなイメージも含んだ言葉なのです。機械好きな人には面白い言葉ですね。
次の記事: 看板と立札の違いって何?わかりやすく解説します! »





















