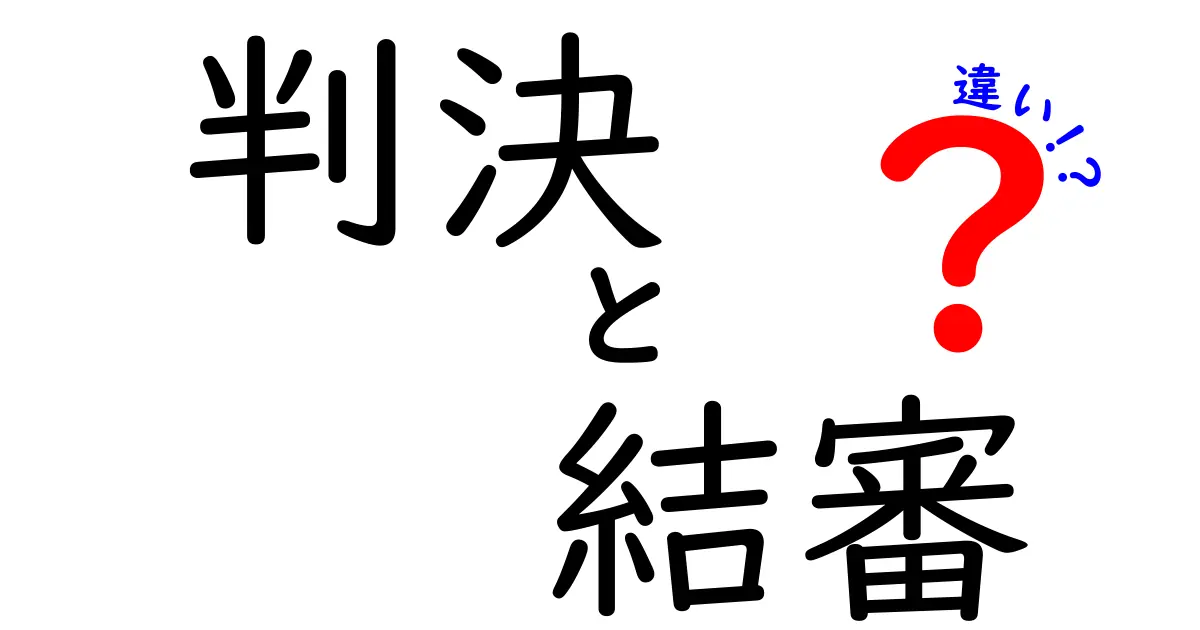

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
判決と結審の基本的な意味とは?
裁判でよく耳にする言葉に「判決」と「結審」があります。どちらも裁判に関わる重要な言葉ですが、その意味やタイミングには違いがあります。
まず、結審(けつじん)とは、裁判での話し合いがすべて終わった状態を指します。つまり、原告・被告双方が自分たちの主張や証拠を出しきって、裁判所がこれ以上の審理は必要ないと判断した段階です。
一方、判決とは、裁判所が結審の後に行う最終的な判断です。裁判の争点について法律を基に裁判官が判断し、その結果を文書で示すことを指します。
つまり、結審が“裁判の話し合いが終了した状態”であるのに対して、判決は“裁判所がその話し合いの結果を示す行為”という違いがあります。
裁判の流れの中での「結審」と「判決」
裁判は大まかに・訴状の提出・口頭弁論・結審・判決という流れで進みます。
具体的には、まず当事者が裁判所に訴えを起こすところから始まります。その後、裁判の中で、双方が証拠を提出したり、証人を呼んだりして話し合い(口頭弁論)を重ねます。この話し合いが十分に行われ、これ以上審理を続ける必要がなくなるのが結審です。
結審が宣言されると、その後、裁判所は書面により判決を下します。
判決は裁判所の最終的な判断なので、裁判の結果がどうなったかが明確に示されます。
結審と判決の間には通常、数日から数週間の日数が空くこともあります。これは裁判官が慎重に判断を下すための時間です。
結審と判決の違いを比較した表
| 項目 | 結審 | 判決 |
|---|---|---|
| 意味 | 裁判の話し合いが終わること | 裁判所が最終判断を示すこと |
| タイミング | 口頭弁論終了直後 | 結審後、数日~数週間以内 |
| 目的 | 審理終了の合図 | 争点に対する裁判所の判断 |
| 形式 | 宣言や合意で終了 | 文書での判決書 |
このように結審は裁判の話し合いを締めくくる段階で、判決はその話し合いの結果を裁判所が示す最終的な判断という役割を持っています。
中学生にもわかりやすいように言うと、結審は“お互いに主張は全部言い終わったよ、これから先生(裁判官)が決めるよ”という状態で、判決は“先生が考えて出した結論”だとイメージすると良いでしょう。
結審という言葉、実は裁判の世界で意外と知られていないポイントです。中学生の頃、結審が何かの終わりってぼんやりイメージしていたかもしれませんが、裁判では“もう話は全部聞いたよ”っていう合図なんです。だから結審のあと、すぐに判決が出るわけじゃなくて、じっくり裁判官が考える時間があるんですね。これは裁判の公平さを保つためにすごく大事なことなんです。つまり、結審は裁判の“区切り”、判決は“最終決定”と覚えておくと、裁判の流れがグッとわかりやすくなりますよ。
次の記事: 「わざと」と「故意」の違いとは?分かりやすく徹底解説! »





















