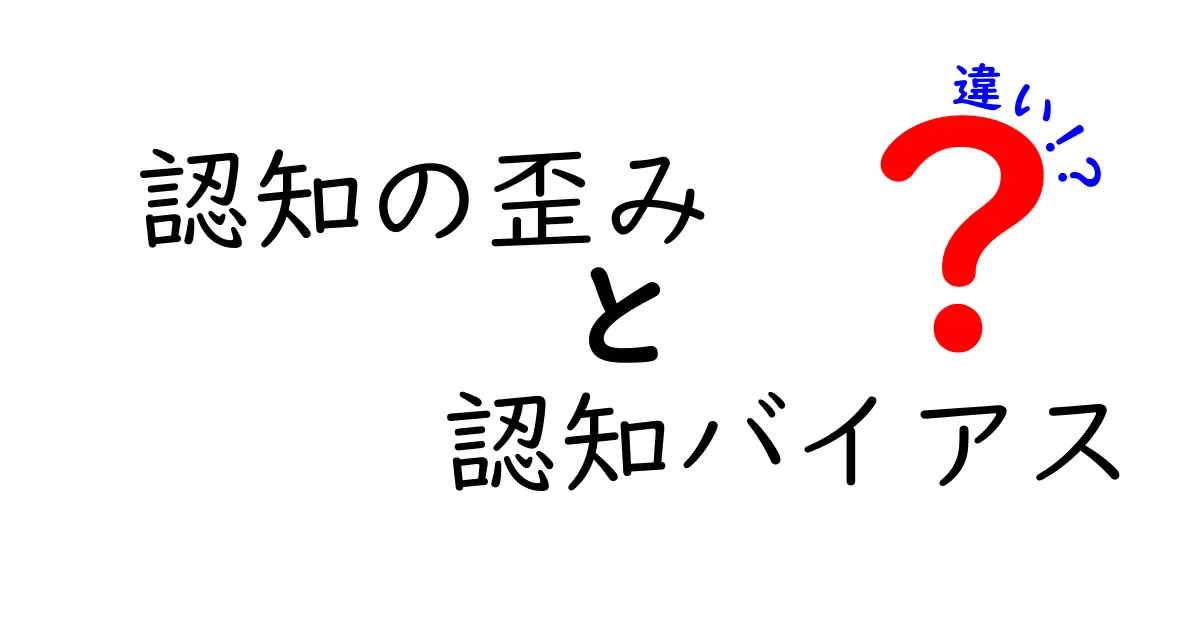

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
認知の歪みと認知バイアスって何?
まず、認知の歪みと認知バイアスは似ているようで少し違う心理学の用語です。
どちらも私たちの考え方や感じ方に影響を与え、時に間違った判断をしてしまう原因となるものです。
簡単に言うと、認知の歪みは自分の考え方が偏ってしまう傾向や癖のことを指します。
一方、認知バイアスは私たちの思考や判断が無意識のうちに偏ってしまう心理的な傾向のことで、より幅広い現象を含みます。
どちらも日常生活でよく起こることですが、それぞれの違いを理解すると、自分の考え方を見直したり、周りの人とのコミュニケーションがより良くなるヒントになります。
認知の歪みの特徴と例
認知の歪みは、物事や自分に対する考え方が現実よりも偏ってしまう心理のことです。
これは特に感情や気分の影響を受けることが多いです。
たとえば、テストで少しミスしただけなのに「私は全部できないダメな人間だ」と考えてしまうのは認知の歪みの一つです。
これは「全か無か思考」という典型的な認知の歪みの例です。
認知の歪みの主な種類には以下のようなものがあります。
- 全か無か思考:物事を白か黒かで考え、途中のグレーゾーンを認めない
- 過大評価・過小評価:自分のミスや失敗を必要以上に大きく見たり、逆に成功を小さく見たりする
- 感情的理由付け:気分によって物事を判断する
- マイナス化思考:良いことがあっても「それは特別なことではない」と否定的に解釈する
このような歪みが続くと、気持ちが落ち込みやすくなり、人間関係が悪くなったり、ストレスが増える原因にもなります。
認知バイアスの特徴と例
一方、認知バイアスは日常の判断や意思決定の際に私たちが無意識に陥る偏りのことです。
これは個人の性格だけでなく、人間の脳の仕組みや情報処理の問題から起こります。
例えば「アンカリング効果」という認知バイアスは、最初に提示された数字や情報に強く影響され、その後の判断が偏ってしまう現象です。
お店で値段を見た後に割引商品を見ると「お得に感じる」理由もこれに当たります。
主な認知バイアスの種類には以下のものがあります。
- アンカリング効果:最初の情報に引っ張られる
- 確証バイアス:自分の考えを裏付ける情報ばかり集めてしまう
- 正常性バイアス:危険な状況を過小評価してしまう
- 代表性ヒューリスティック:ステレオタイプに基づいて判断する
こうしたバイアスは、ニュースの受け取り方やネット上の情報判断、買い物の選択などに影響を与えるため、とても身近です。
認知の歪みと認知バイアスの違いをわかりやすく比較
| ポイント | 認知の歪み | 認知バイアス |
|---|---|---|
| 意味 | 考え方や感じ方が偏ってしまう心理的クセ | 判断や意思決定で起こる無意識の偏り |
| 主な原因 | 感情の影響が大きい | 脳の情報処理の仕組みや思考の省略 |
| 対象 | 自分や周囲の物事への見方 | 外界の情報や状況に対する判断 |
| 意識の有無 | 本人が気づくこともある | ほとんど無意識に起こる |
| 日常例 | 自分を過小評価する思考 | ニュースの情報を偏って受け取る |
まとめ
認知の歪みは自分の感情や気持ちが反映された考え方の偏りで、
認知バイアスは脳の仕組みから起こる無意識の偏りです。
この違いを理解することで、自分の思考や行動を客観的に見直し、
より良い判断ができるようになります。
どちらも誰にでも起こることだからこそ、自分や他の人の考え方を知り、
問題があれば意識して対処していくことが大切です。
認知バイアスの一つである「アンカリング効果」は、最初に見た数字や情報に強く影響されがちなことを言います。たとえば、お店で"元の値段"を見せられた後に割引価格を見ると、割引後の値段がお得に感じるのはこの効果が働いているからです。私たちの脳は最初の情報を基準にしてしまい、その後の判断が偏ってしまうんですね。これは買い物だけでなく、日常の色んな判断でも起こるので気をつけたいところです。
前の記事: « 虚偽表示と通謀虚偽表示の違いを徹底解説!わかりやすく学ぼう
次の記事: 強迫症と潔癖症の違いって何?見分け方と特徴を丁寧に解説! »





















