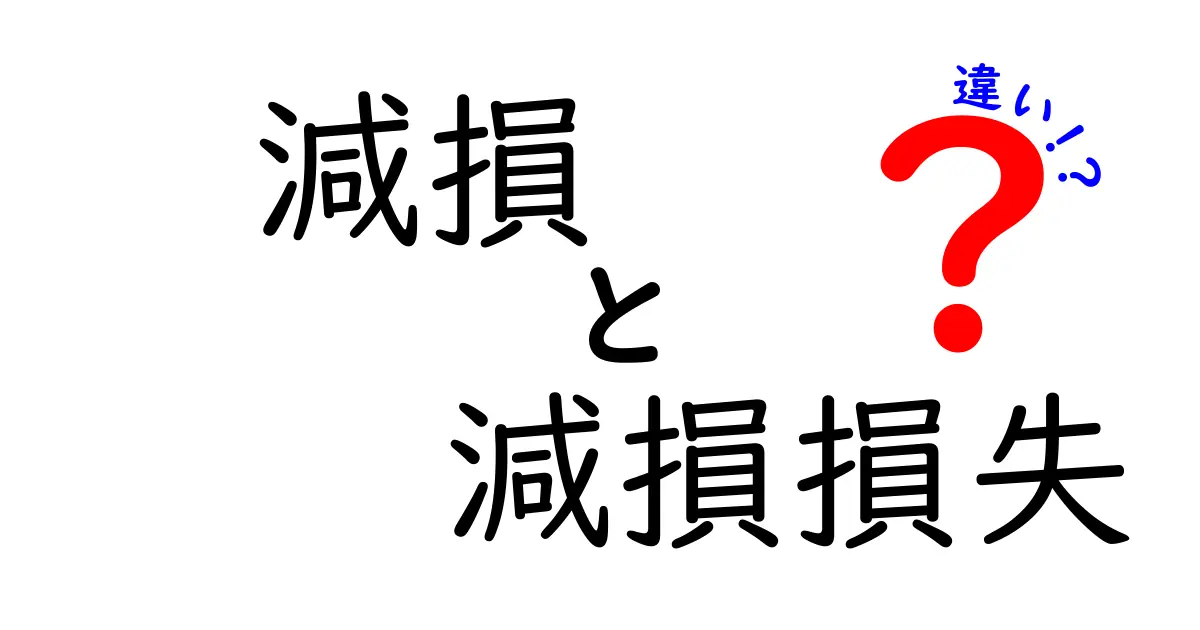

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
減損と減損損失の意味
みなさんは「減損」と「減損損失」という言葉を聞いたことがありますか?どちらも会計や経理の分野でよく出てくる言葉ですが、似ているようでちょっと違います。
減損とは、会社が持っている資産の価値が何らかの理由で下がってしまった状態を指します。例えば、古くなった機械や土地の価格が下がった場合に使われます。
一方、減損損失は、その減損が確定して会計上の費用として計上されたものを意味します。つまり、減損によって資産の帳簿価値を減らした結果、損失として会社の損益に計上される部分です。
簡単に言うと、減損は資産の「価値が下がった状態」であり、減損損失はその「下がった価値分を損失として記録すること」なのです。
減損と減損損失の違いを表でまとめると?
なぜ減損や減損損失の理解が大事?
会社の経営や財務状態を正しく把握するためには、資産の価値を適切に見積もることが必要です。もし資産が実際には価値が下がっているのにずっと高いまま帳簿に残っていると、会社の利益が実際より良く見えてしまいます。
そこで、減損の考え方を使って資産の価値を見直し、減損損失を計上して利益を修正します。こうすることで、投資家や経営者は会社の本当の経営状態を把握できるのです。
会計の世界では、この減損処理がとても重要な役割を持っています。
ポイントとしては、減損は価値の変化を確認すること、減損損失はそれを損失として記録することという違いを押さえておくことが大切です。
まとめ
今回は「減損」と「減損損失」の違いについて解説しました。
・減損:資産の価値が下がった事実や状態
・減損損失:その価値の下落部分を会計上の損失として計上したもの
この2つはとても近い言葉ですが、意味や目的は違います。
会社や経理、会計の勉強をするときは、この違いをしっかり理解することで会計処理の意味や流れがスムーズにわかります。
みなさんもぜひ覚えておきましょう!
実は「減損」という言葉は資産の価値が下がる一般的な状態を表していますが、実際の会計処理でよく使われるのは「減損損失」です。
それは、減損の状況をチェックした後に初めて具体的に損失額を計上し、会社の損益に反映させるためです。
この処理が会社の利益の適正化に大きく貢献しているので、ただの価値の減少「減損」だけでなく、それを費用として計上する「減損損失」の意味を深く理解すると、会計の世界の見方が変わってきますよ。





















