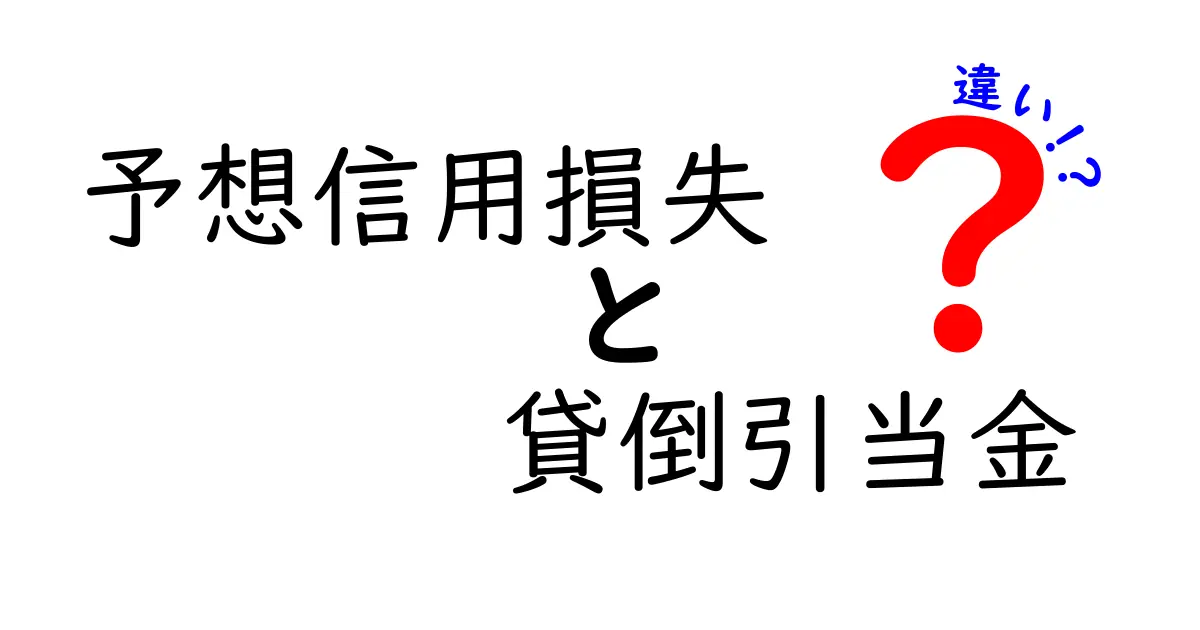

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
予想信用損失と貸倒引当金って何?基礎から理解しよう
私たちが銀行や会社の財務を学ぶときに、よく出てくる言葉に「予想信用損失」と「貸倒引当金」というものがあります。これらは似ているようで、実はちょっと違う役割を持つものなんです。今日は中学生でもわかるように、この二つの言葉の意味や違いについて、やさしく説明していきます。
まずは、言葉の意味から見ていきましょう。
予想信用損失は、貸したお金が将来返ってこないかもしれないリスクをあらかじめ見積もるものです。これは将来の損失を予想して「まだ起こっていないけれど、起こる可能性があるお金の損失」として計算されます。
一方で貸倒引当金は、その予想信用損失を会社の会計上で準備金として積んでおくお金のこと。つまり、実際に貸したお金が返ってこない場合に備えて、あらかじめ用意しておくお金です。
このように、予想信用損失はリスクの予測で、貸倒引当金はリスクに備えたお金の積立と考えるとわかりやすいです。
では、もう少し詳しく、それぞれの特徴や違いを見ていきましょう。
予想信用損失と貸倒引当金の主な違い
ここでは、予想信用損失と貸倒引当金の違いをわかりやすく表にまとめてみました。項目 予想信用損失 貸倒引当金 意味 貸したお金が返ってこない可能性がある損失を予測 その予測をもとに会計で準備しておく引当金(備え) 性質 将来のリスクの見積もり 実際に計上する準備金や引当金 タイミング 未来の可能性として常に評価 会計期間ごとに金額を調整し積み立てる 目的 リスクを予測して管理する 損失発生時の影響を緩和する 法律や規則 IFRS(国際会計基準)で重要視されている 日本の会計基準や銀行監督上の規定に従う場合が多い
上の表からわかるように、予想信用損失は“予測”であり、貸倒引当金は“準備金”としての役割があることがポイントです。
銀行や企業はこの予想信用損失をもとに、貸倒引当金を計上していくのが今の流れとなっています。
特にIFRSと呼ばれる国際会計基準では、予想信用損失の考え方が重視されているため、世界的に見ても大切な概念なんです。
実務での使われ方と注意点
ではこの二つは、実際の会社や銀行の会計や経営にどのように使われているのでしょうか?
予想信用損失はもっとも大切な「リスク管理」の考え方の中心になります。
たとえば、企業が取引先に商品を売って売掛金をもらう場合、いつかその相手が倒産するかもしれません。
その可能性を見積もることで、どのくらいの損失が予想されるかがわかり、経営者はリスクに備えた計画を立てることができます。
一方、貸倒引当金は実際に帳簿で損失が出たときのための準備金として計上されます。
もし倒産したりお金が戻らなかった場合に、この引当金を使って会社の損失を補うことになります。
注意したいのは、予想信用損失は将来のリスクの見積もりなので絶対に当たるとは限らないということです。
一方で貸倒引当金は、会計ルールに従って慎重に金額を決める必要があります。しっかりとした計算や監査が必要なので経理担当者の仕事はとても重要です。
これらを正しく理解し管理することで、会社は安定した経営を目指すことができます。
まとめると、予想信用損失は「リスクを知るための予測」であり、貸倒引当金は「リスクに備えて積み立てるお金」と覚えておくと理解しやすいでしょう。
予想信用損失の話になるとよく問題に上がるのが「どうして将来の損失を予測しなければいけないのか?」という点です。実は、ただ単に数字を当てはめるだけではなく、社会情勢や取引先の業績まで詳しく調べる必要があります。つまり、数字の裏には現実のリスクをしっかり見る目が大切なんです。これができるかどうかで会社の経営は大きく変わると言われています。ちょっとしたニュースや経済の動きも大事にしたいですね。





















