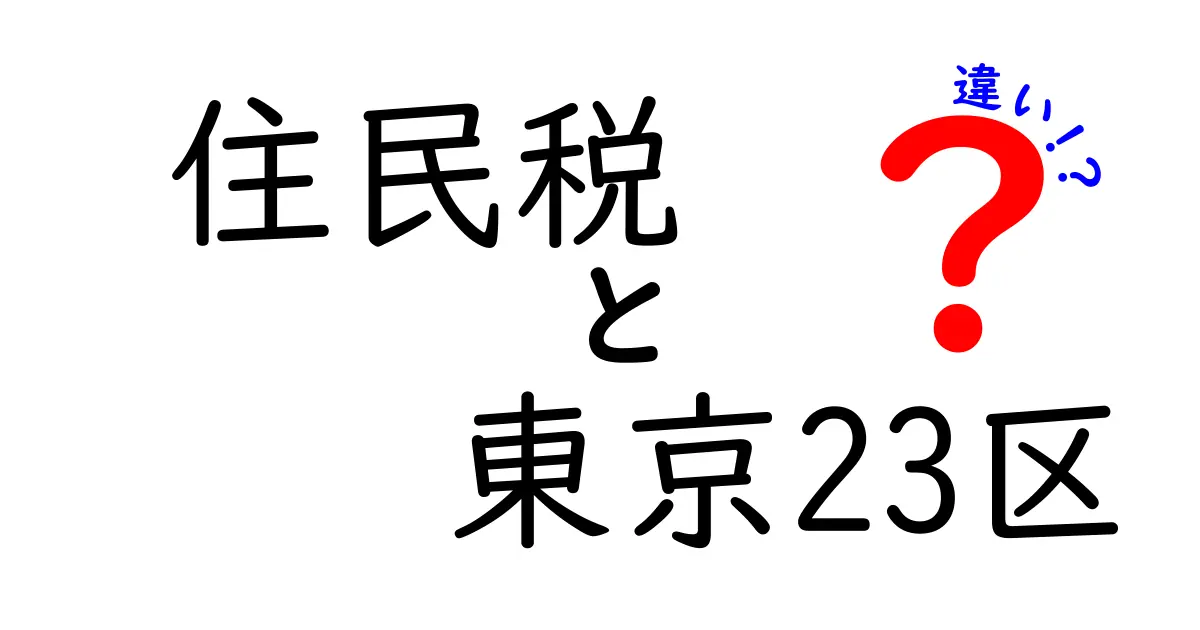

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
東京23区の住民税とは?基本の仕組みを解説
住民税は、私たちが住んでいる地域の自治体に支払う税金で、地域のサービスやインフラに使われます。東京23区は特別区と呼ばれ、それぞれが独立した自治体として住民税を徴収しています。
住民税は「均等割」と「所得割」の2つの部分から成り立っていて、均等割は誰でも一律の金額、所得割は収入に応じて変わります。東京23区では基本的にこの2つを合わせて税率が決められており、他の自治体と比べると高めに設定されていることが多いです。
ポイントは、東京23区内でも区によって税率や控除などの条件がわずかに異なるので、引っ越しや仕事を考える際は注意が必要です。
東京23区ごとの住民税の違いは?区ごとに違うポイント
実は、東京23区の住民税は全国の自治体の中でも比較的似ているものの、係数や控除の内容、サービスの提供内容に小さな差があります。例えば、以下のような違いが見られます。
- 税率の違い:所得割の税率は多くの区で10%前後ですが、一部の区では特例で異なる場合があります。
- 均等割の額:区によっては均等割の金額が数百円の差があることも。
- 控除の内容:医療費控除や扶養控除など、適用の細かい基準に違いがある場合があります。
- 税のサービスへの還元:教育や福祉など、使われ方に特徴があり、結果的に住民サービスの質に差が出ることもあります。
これらの違いは大きく生活にかかわるものではありませんが、知っておくと住まいや仕事の選択に役立ちます。
東京23区の住民税の料金表と比較
※表は一部の区の例です。統一されている区も多いため概ね参考としてご覧ください。
このように多くの区は均等割3500円、所得割率10%前後で設定されていますが、一部の特例や控除については各区の公式サイトで確認することをおすすめします。
住民税の『均等割』って聞くと難しそうですが、簡単に言うと「住んでいるだけでどの人も払う決まった金額」のことです。だから、収入が少なくても一定金額はかかるんですよ。でも東京23区では多くの区が均等割3500円と同じくらいなので、引っ越しても大きな変化はありません。ただし、税金の使われ方は区ごとに違うので、均等割を払う意味を考えると面白いですね!





















