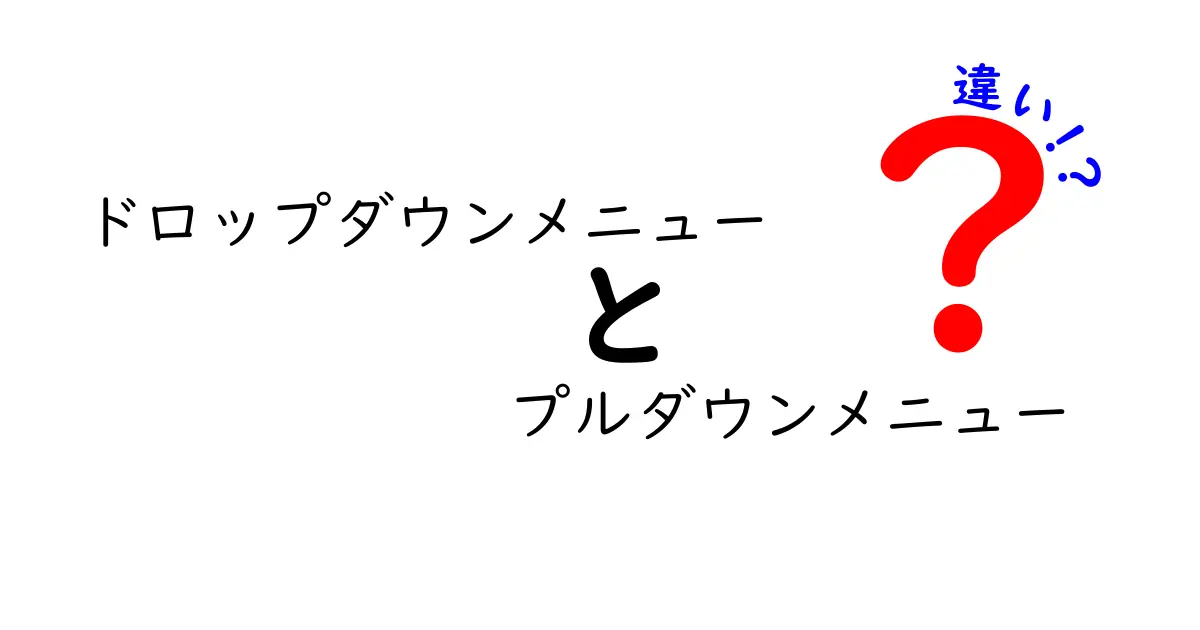

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ドロップダウンメニューとプルダウンメニューの基本的な違い
みなさんはウェブサイトやアプリを使っていると「ドロップダウンメニュー」と「プルダウンメニュー」という言葉を聞いたことがありませんか?これらはどちらも画面に表示されるメニューのことを指していますが、実は少し使い方や意味が違う
ドロップダウンメニューは、押すと下に項目が「降りてくる」イメージで、上から下へ表示されるメニューです。一方、プルダウンメニューは、基本的には同じ見た目ですが、元々はユーザーがメニューを「引っぱり出す」イメージで使われてきました。つまり、両者は見た目は似ていますが、由来やニュアンスが違います。
歴史と用語の違い
まず、言葉のルーツを知ると理解しやすくなります。
ドロップダウン(drop down)は、英語で「落ちてくる」という意味で、上からメニューが降りてくる様子を表しています。
プルダウン(pull down)は「引き下げる」や「引っぱる」という意味で、ユーザーがメニューを引っぱって表示するイメージからきています。
英語圏ではどちらも似た意味で使われることが多いのですが、日本では特にIT業界やデザインの分野で区別されて使われることがあります。
まとめると日本語での違いは、ドロップダウンは表示される動きに注目し、プルダウンはユーザーの操作に注目しているという点です。
実際の使われ方と違いのまとめ
それでは、実際のウェブデザインやソフトウェアでどのように使われているのか見てみましょう。
一般的には下記の点で区別されることがあります。項目 ドロップダウンメニュー プルダウンメニュー 操作方法 ボタンやカーソルを合わせるとメニューが自動的に降りてくる ユーザーがクリックや押す動作をしてメニューを引き出す 表示の仕方 主に下方向にメニューが展開される 下や横にメニューが展開されることもある 使用例 ウェブサイトのナビゲーションやフォルダの選択 選択項目をユーザーが引き出して選ぶ場面
このように見た目は非常に似ているため、混同されやすいですが、使われる場面やユーザーの操作方法に注目すると違いがわかります。
まとめと注意点
最後に重要なポイントをまとめます。
- ドロップダウンメニューはメニューが下に降りてくる動きに注目した言葉
- プルダウンメニューはユーザー操作でメニューを引き出すイメージの言葉
- ユーザーにわかりやすく設計することが最も大切なので、言葉の使い分けにこだわりすぎず使うのがポイント
これで「ドロップダウンメニュー」と「プルダウンメニュー」の違いがよく理解できたのではないでしょうか?ウェブやアプリの操作をするときに、この違いを知っていると、より技術的な話も理解しやすくなりますよ。
ぜひ覚えておきましょう!
「プルダウンメニュー」という言葉は、ユーザーが文字通り『メニューを引き出す』というイメージから来ています。でも実は、ほとんどのウェブサイトでは、指でタップしたりマウスでクリックしたりして表示されるので、実際には“引っぱっている”感じはあまりありません。だから、プルダウンという表現は、昔のコンピュータ操作やプログラムの言い回しがそのまま残っているだけかもしれませんね。
こうした言葉の背景を知ると、メニューひとつでも歴史や使われ方の深さを感じられて面白いですよね。
次の記事: URLとハイパーリンクの違いとは?初心者でもわかる基本解説 »





















