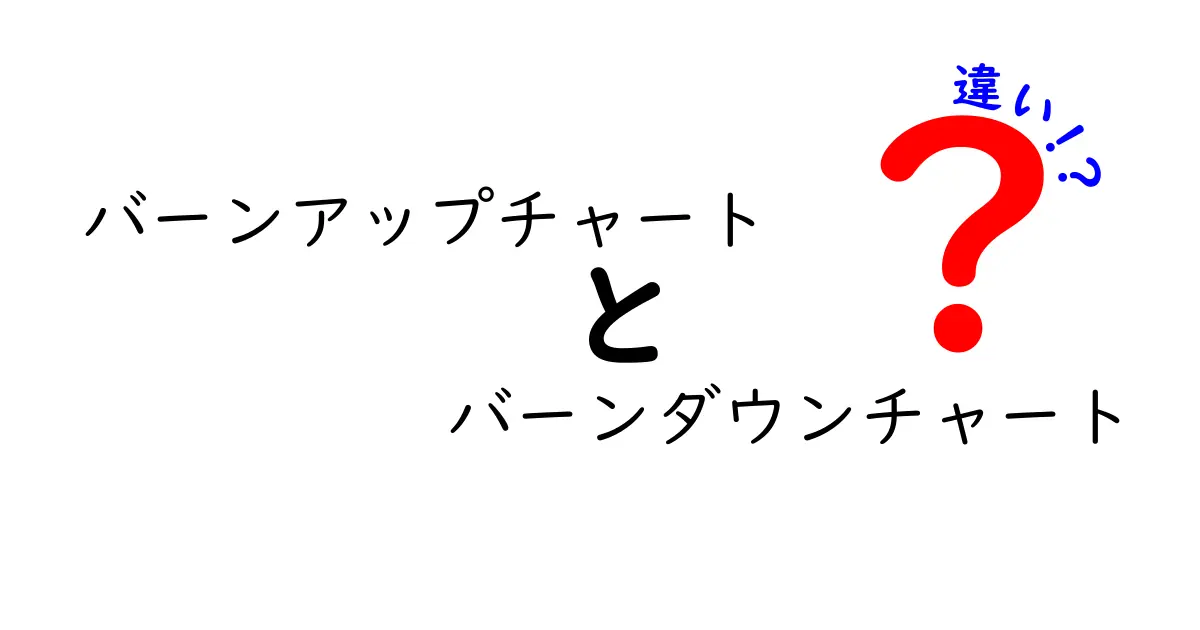

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
バーンアップチャートとバーンダウンチャートの基本的な考え方
バーンアップチャートとバーンダウンチャートは、プロジェクトの進捗を視覚的に把握するための道具です。バーンアップチャートは「これまでに達成した量」を縦軸に取り、横軸には時間を置く形で、完了した作業量が上昇していく曲線を描きます。対してバーンダウンチャートは「残りの作業量」を縦軸に取り、同じく時間を横軸にして、残りが減っていく様子を下へ伸びる線で表します。両者は目的が同じでも、見え方が異なるため、会議の運用や日常の意思決定のスタイルに合わせて使い分けると、メンバーの理解が深まりやすくなります。
バーンアップは、達成した量が増えるほど「順調に進んでいる」という前向きな情報を伝えやすく、モチベーションの維持にも効果があります。特にグラフィックが右肩上がりになると、完了の実感が強くなり、次のタスクに取り組むエネルギーが生まれやすいです。
ただし、予想外の新規タスクが入ると完了量の追加分が線形に積み上がらない点が弱点となることもあります。一方、バーンダウンは「まだ終わっていない量」がどれくらい残っているかを直感的に示し、遅れの早期発見に向いています。残作業が急に増えるとラインが急な角度で跳ね上がるため、会議での警告信号として機能します。
このように、バーンアップとバーンダウンは、同じ現象を別の見方で伝える道具です。初心者が最初に理解するべきポイントは、どちらが「何を伝える主役の情報源」なのかということです。 すなわち、完了量を主役にするならバーンアップ、残量を主役にするならバーンダウンという考え方です。
さらに、使い方のコツとしては、初期設定を合わせておくこと、日次・週次の更新をルーティン化すること、そして両方のチャートを併用して比較することが挙げられます。
開始時には計画した総作業量と実際の完了量を両方のチャートで描いておくと、差異の理由を討論する際の手掛かりが増え、リスクの兆候を早く捕まえやすくなります。
違いのポイントを整理しよう
ここでは、見た目の違い、意味する情報、適用の場面、更新の仕方とチームの反応について詳しく比較します。バーンアップチャートは「完了量の増加」を追うため、積み上がる量が確かに増えていくかどうかを直感で感じやすく、リリース日が近づくにつれて士気が高まることがあります。
一方のバーンダウンは「残り作業量の減少」を追うため、今この瞬間の作業量がどれくらい残っているかが分かりやすく、タスク追加や仕様変更があったときの影響を直感的に把握できます。
実務では、両方を同時に用いると強力です。たとえば、朝のデイリースクラムでバーンダウンをチェックして「この日までに終わるのか」を確認し、週の振り返りでバーンアップを見て「達成感をどう作るか」を話し合う、という組み合わせです。
また、適用シーンとしては、アジャイル開発のスプリント管理、学校のプロジェクト、イベント準備の進捗管理など、作業量の変動がある場面で効果を発揮します。
以下の表は、代表的な違いを簡単に整理したものです。観点 バーンアップチャート バーンダウンチャート 主役となる情報 完了量の増加 残り作業量の減少 見た目の印象 右肩上がりの曲線 右肩下がりの曲線 遅延の気づき方 完了が遅れても総量の変化で把握 残量が減らないと警告が出やすい 適用シーンの例 達成感を重視する場面 残作業の厳密な管理が必要な場面
この表を見ながら、プロジェクトの性質に合わせて一つのチャートだけでなく二つを併用することを検討してください。最後に、「目的を決めてからチャートを選ぶ」この順番を守ると、混乱を減らせます。
雑談風に深掘りします。友達と机を囲みながら、バーンダウンの話題を取り上げます。友達が『残りの作業がどんどん減っていくのを見るのは安心だね』と笑います。私は『でもそれだけじゃなくて、なぜ減っているのか、追加作業が入るとどう変わるのかを考えると、より現実に近い進捗を掴めるんだよ』と返します。バーンダウンは“今この瞬間の重さ”を直感で感じさせ、遅延の兆候を早く伝えてくれます。だからこそ、急な仕様変更があった日には「残りが増えた」のではなく「新しい作業の総量に対する減少率」が重要になります。逆にバーンアップは、これまでの達成量の積み上がりを見せることで、頑張ってきたことを可視化します。友達は「達成量が増えると、次は何を終わらせようかと考える力が湧くね」と納得します。結局は“何を見たいか”という欲求と、チームの風土次第。私は「小さな成功を重ねられる日常こそが長い目での成功につながる」と伝え、二つのチャートを併用する実例を教えます。バーンアップは士気を支え、バーンダウンは警告と現実感を与える、そんな相棒のような関係が理想だと思います。





















