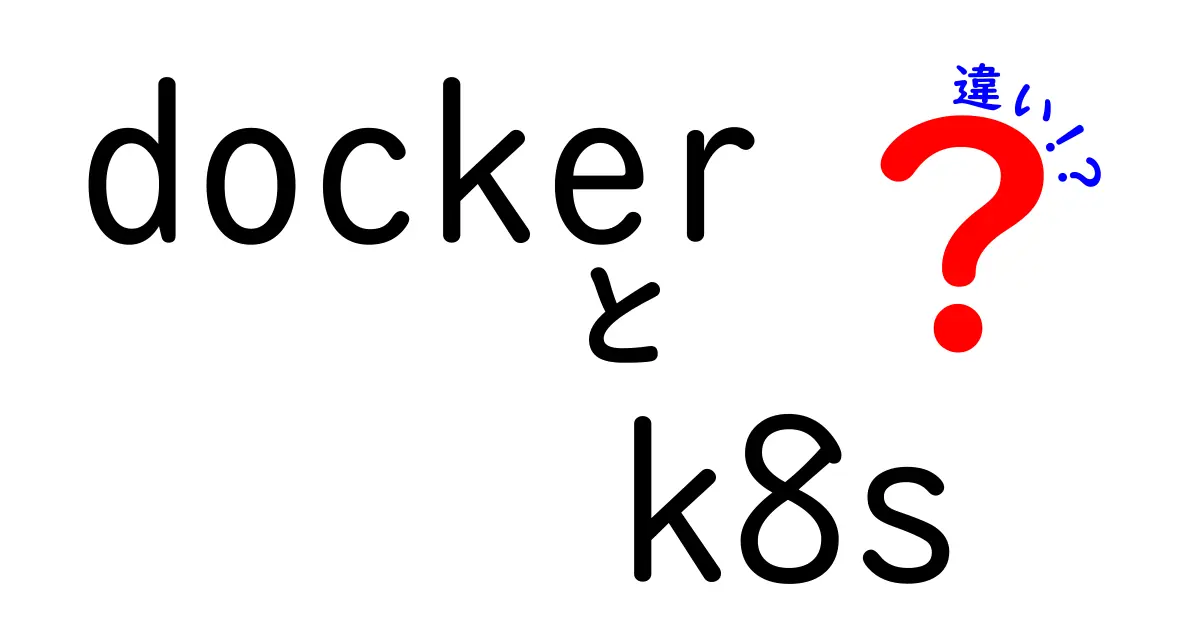

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
DockerとKubernetesの基本をおさえる
まず、Dockerはソフトウェアを動かすための箱を作る仕組みです。箱の中身はイメージと呼ばれ、必要なプログラムや設定、依存関係がひとまとめに詰められています。実行時には箱ごと起動して動かすので、開発環境と本番環境の違いを最小化できます。箱を作るときは“レシピ”のようなDockerfileという設計図を使い、同じ箱を何度も再現可能です。こうして作られた箱はコンテナと呼ばれ、OSの違いにも影響されにくく、起動が速く、リソースの使用量も抑えやすい点が魅力です。
この仕組みを知っておくと、アプリを動かす“箱の考え方”が分かりやすくなります。
一方、Kubernetesは多くのコンテナを動かす環境を自動で管理するオーケストレーションの仕組みです。複数のマシンにまたがるクラスタを見守り、どの箱をどのマシンで動かすかを決め、箱が壊れたら別の箱に置き換え、負荷を均等に配分します。これにより、一つのアプリが止まっても全体の影響を最小化できます。現場ではDockerで箱を作り、Kubernetesでそれを大規模に動かすのが一般的です。なお最近はDocker自体を直接の実行エンジンとして使うのではなく、containerdやCRI-Oといった実行エンジンを使う流れが広がっています。
違いの大枠:何が同じで、何が違うのか
この二つは“道具の役割”が違います。Dockerは箱を作って動かすまでのツール、Kubernetesはその箱を複数の場所で安定して運用する仕組みです。
つまり、Dockerは“箱づくり”の専門家、Kubernetesは“箱を動かす運用部”のような役割分担です。両方を組み合わせると、開発は速く、運用は強くなります。現実の現場では、Container Runtimeの話題が出てくることもあり、Dockerだけを前提に考える時代は終わりつつあります。
この理解があると、学習の順序や実務の選択肢が見えやすくなります。
実務での使い分けのコツ
実務で重要なのは、規模と信頼性の要求です。小規模なサービスや開発段階では、Dockerを使って箱を作り、シンプルなデプロイを回すだけで十分なケースが多いです。逆に、複数のチームが関わる大規模なサービスや、ダウンタイムを避けたいときにはKubernetesの力が役に立ちます。
また、運用の自動化や監視、ローリングアップデート、自己修復といった機能は、Kubernetesを軸に据えると効果的です。
最後に重要なのは、技術を使いこなす人の手腕です。道具同士の関係を正しく理解し、適切な運用ポリシーを決めることが成功の鍵になります。
オーケストレーションという言葉を深掘りしてみましょう。難しそうに感じるかもしれませんが、イメージとしては学校の合奏を指揮者が全体のテンポと音量を合わせることに似ています。Dockerで箱を作る人、Kubernetesで箱を整列させる人、そして現場の運用テーブルで監視と通知を回す人、それぞれ役割が違います。ここを深く意識するだけで、学習の順序が自然と見えてきます。
この“オーケストレーション”の考え方は、プログラミングの世界だけでなく、日常の作業の進め方にも通じる大切な考え方です。複数の箱を同時に動かすためのルール、障害時の自動復旧、ローリングアップデートといった概念を含みます。私は友達と一緒にプログラミングの課題を解くとき、役割分担を決め、誰がどの部分をいつ公開するかを相談します。それと同じ感覚で、現場のオーケストレーションも、全体の動きを滑らかにするための“約束事”を作る作業です。





















