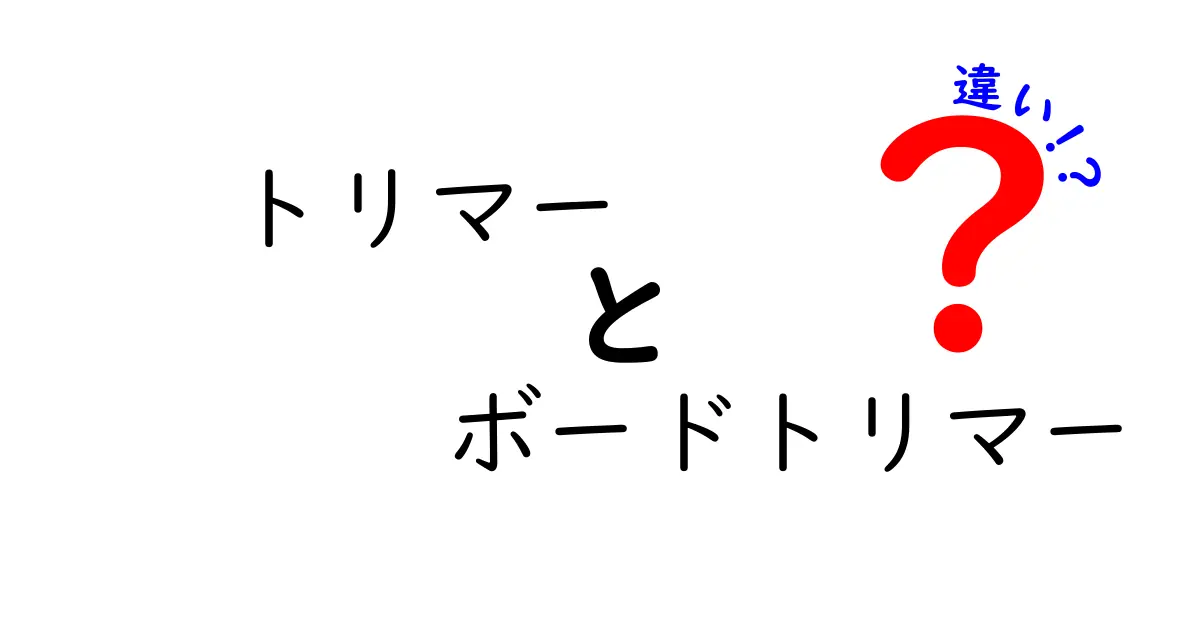

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
トリマーとボードトリマーの違いを徹底解説:どちらを選ぶべき?
この記事では、トリマーとボードトリマーの違いをしっかり理解できるよう、道具の目的・使われる場面・構造の違い・選び方のポイントを順を追って解説します。まず前提としてこの用語には複数の意味があることを知っておくと混乱を避けられます。木工作業で使われる“トリマー”は、板のエッジを薄く削って滑らかに整えるための道具で、薄い材料の処理や曲線の仕上げに強いのが特徴です。一方の“ボードトリマー”は、名前のとおり板材そのものを安定させて厚さを一定に揃え、角を均一に削るための機能が充実した機械で、長い材料の加工に向いています。
この二つはサイズ・重量・刃の形状・動力源(電源の有無)・騒音・振動の程度など、いくつもの点で違います。初めて購入する人は「どんな作業を中心にするのか」「材料はどのくらいの厚さか」「仕上げの精度はどの程度必要か」を最初に決めることが大切です。
この判断を最初に明確にしておくと、後で後悔する買い物を減らせます。次節では、より具体的な違いと使い分けのコツを、実務での場面を想定して整理します。
基本な違いを整理する
まず覚えるべき基本は、機能の目的と作業の規模です。トリマーは細かな仕上げ・溝の加工・装飾的なカットを行うのに向いており、細かいコントロールと繊細さが求められます。板は薄く、刃も小型のものを使います。一方でボードトリマーは板材の端を整える大規模な加工や、厚い材料を長さ方向に均一に切削する場面で活躍します。ブレードのサイズ感や出力レベルも大きく異なり、扱いの難易度は高くなる傾向があります。重要なのは「安定性・安全性・作業範囲」の三つを自分の作業に合わせて優先順位化することです。実際の現場では、素材の硬さ・厚さ・仕上げの要求値に応じて速度を調整し、少しずつ深さを変えながら進めます。短い材料なら小型機で十分ですが、長い端材にはボードトリマーの安定性が有効です。
用途別の選び方と使い分けのコツ
用途別の選び方は、まず自分の加工対象を具体的に想像することから始まります。木材の厚さは3mmの薄板なのか、25mmの厚板なのかで適した機種は変わります。初心者なら、まずは小型で軽いトリマーを選び、手元の感覚をつかむと良いです。安全面では、作業中の指の位置を守るためのガードやブレーキ機構、オイルの供給と刃の清掃方法を事前に学んでおくと事故を防げます。ボードトリマーを買う場合は、テーブルの平面出しとブレークダウンの安定性、取り付けの自由度、付属のダスト収集機能を確認します。長期的に使うことを前提に、交換用ブレードの入手性とコストも事前に調べておくと比較がしやすい。実際の作業は、まず深さを0.5mm程度に設定して薄く削り、複数回に分けて仕上げるのが基本です。最後に、清掃とメンテナンスを定期的に行い、刃の摩耗や機械の動きの渋さを早めに感じ取れるようにしておくと、長く安心して使えます。
友達とカフェで雑談している感覚で話します。『トリマーとボードトリマー、名前は似てるけど役割がぜんぜん違うんだよね』って。私たちは木工の道具の話をしているとき、腕前よりまず道具の設計思想を理解することが大切だと気づきます。薄板を滑らかに削るトリマーと、厚い板を安定させて滑らかに切るボードトリマー。使い方のコツは安全と手入れ、そして自分の作業の目的に合わせて選ぶことです。





















