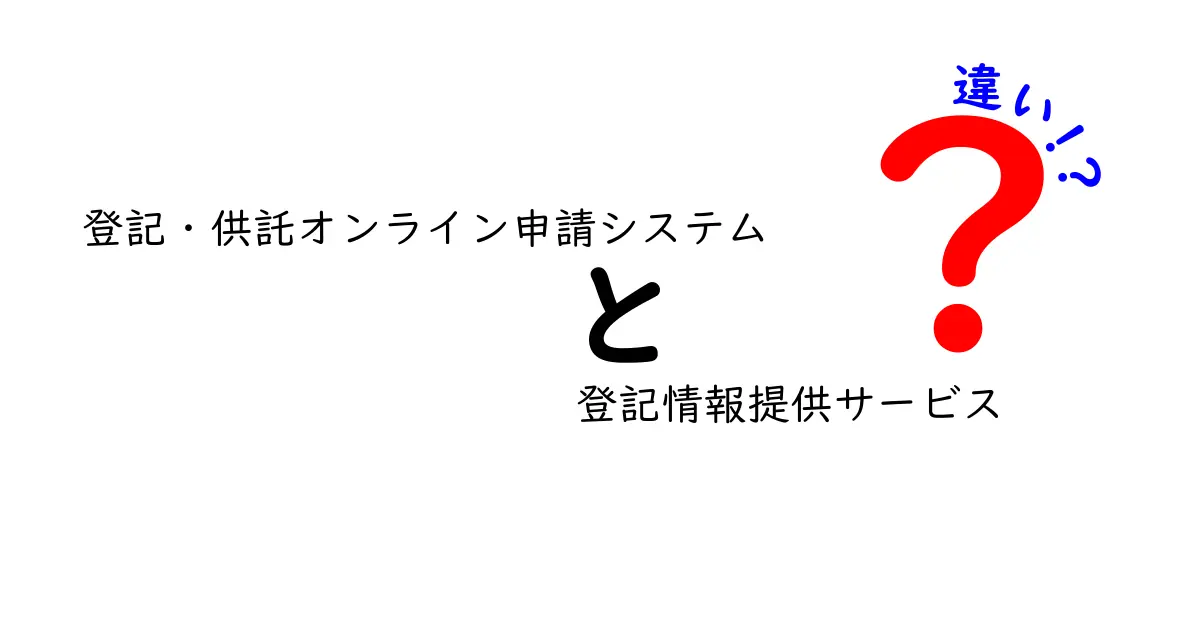

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
登記・供託オンライン申請システムと登記情報提供サービスの基本的な違いとは?
皆さんは「登記・供託オンライン申請システム」と「登記情報提供サービス」という言葉を聞いたことがありますか?どちらも法務局が提供しているオンラインサービスですが、その目的や使い方はかなり違います。
まず、登記・供託オンライン申請システムは、名前の通り土地や建物の登記、会社の設立登記、さらに供託というお金や書類を預ける手続きをオンラインで申請できるシステムです。これは、登記手続きを自分で行いたい人や、専門家が使うためのサービスです。
一方、登記情報提供サービスは、すでに登記された情報を誰でも簡単に調べられるサービスです。つまり、土地や建物の所有者や面積などを知りたいときに使います。
まとめると、オンライン申請システムは「申請や手続きの送信」を目的としており、登記情報提供サービスは「登記データの閲覧や取得」に使うものです。
登記・供託オンライン申請システムの特徴と使い方
登記・供託オンライン申請システムは、自宅や事務所のパソコンから法務局に登記や供託の申請を電子的に提出できるサービスです。通常、登記手続きは窓口で書類を提出して行いますが、このシステムなら時間や場所を気にせず手続きできます。
使うためには事前に電子証明書(電子署名のためのデジタルID)を用意し、システムにログインします。そして申請したい手続きの種類を選び、必要事項を入力し、添付書類をアップロードして送信します。
これにより手続きの効率化ができ、特に専門家や不動産業者によく使われていますが、一般の人でも利用可能です。ただし、操作には少し慣れや知識が必要なので、初心者は注意が必要です。
登記情報提供サービスの特徴と利用シーン
登記情報提供サービスは、ネットを通じて土地や建物の登記情報を調べられる便利なサービスです。例えば、家を買うときに土地の面積や所有者を確認したり、会社の所在地や役員情報を調べたりするときに使います。
利用方法は簡単で、法務局のサイトにアクセスして検索したい物件の情報を入力し、閲覧や写し(登記事項証明書)を取得します。閲覧は無料ですが、写しを取得するときは料金がかかります。
このサービスのおかげで、法務局に直接行かなくても必要な情報を素早く入手できるため、不動産取引や契約の際にも役立っています。
主な違いをわかりやすくまとめた比較表
ここまでの説明をふまえ、両サービスの違いを表にまとめました。
| ポイント | 登記・供託オンライン申請システム | 登記情報提供サービス |
|---|---|---|
| 目的 | 登記・供託の申請をオンラインで行う | 登記情報をネットで検索・取得する |
| 利用者 | 申請者(専門家、個人どちらも可) | 一般の利用者や企業 |
| 必要な準備 | 電子証明書の取得などやや専門的な手続き | 特に準備不要、誰でも利用可能 |
| 利用目的 | 新しい登記申請や供託手続きのため | 土地・建物や会社の情報確認のため |
| 料金 | 申請手数料などがかかる場合がある | 閲覧は無料、証明書取得は有料 |
これを見れば、どんな目的でどちらのサービスを使うべきかわかりやすくなります。
今回は「登記・供託オンライン申請システム」と「登記情報提供サービス」の違いについて話しましたが、特に面白いのは電子証明書の役割です。
電子証明書はネット上の本人確認のためのデジタルの“身分証”のようなもので、これがないと登記・供託オンライン申請システムは使えません。逆に、登記情報提供サービスは情報を見るだけなので、誰でも気軽にアクセスできます。
実はこの差が、初心者にとって一番のハードルになっているんですよね。安全に申請するための仕組みがしっかり整った分、使う前に少し学習が必要というわけです。
前の記事: « 家屋番号と物件番号の違いとは?初心者にも分かりやすく徹底解説!





















