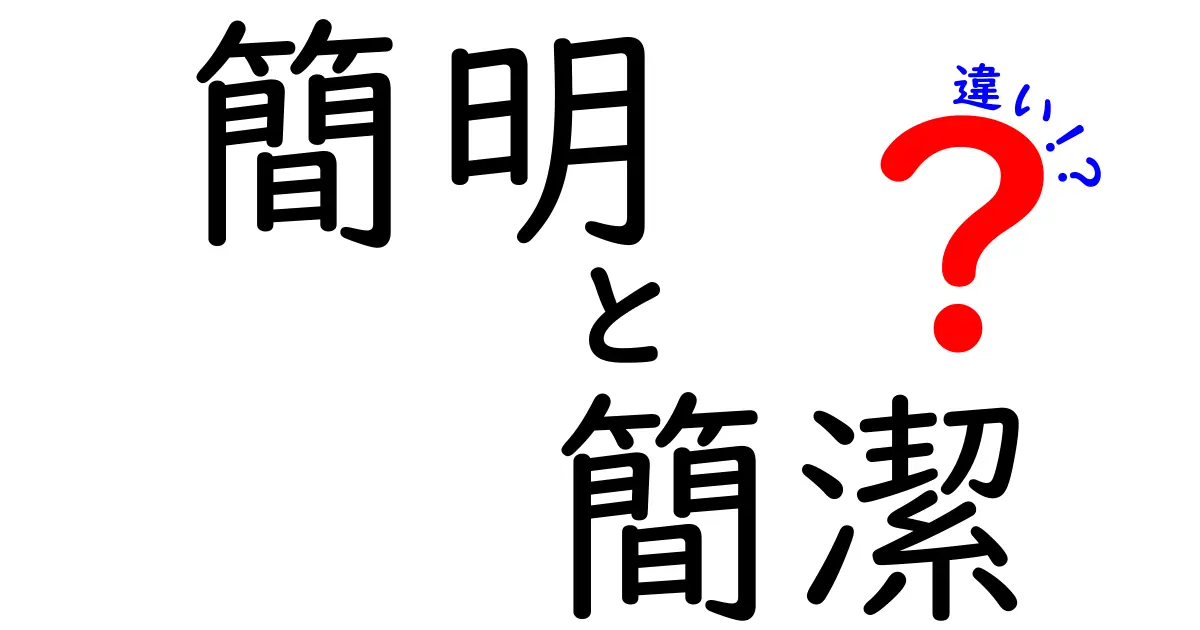

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
簡明と簡潔の違いを徹底解説:違いを理解して使い分けるための最短ガイド
このテーマは、ひと目には似ている二つの言葉を分けるためのヒントになる。まず「簡明」は要点をはっきり示して、読む人が短い時間で全体像をつかめることを目的にします。対して「簡潔」は言葉の数を抑えて、同じ意味を保ちながら文章を短くする技術のことを指します。簡明は情報の設計の観点、簡潔は表現の技術の観点と理解すると把握しやすいです。これらは必ずしも排他的ではなく、良い文章や説明を作るときには両方をうまく組み合わせる場面が多いのです。
学校や職場でよく耳にする「簡潔にまとめて」という指示は、簡潔さを強く求める場面ですが、伝えたい内容の簡明さが欠けていると、読者は結局何が一番大事なのか分からなくなってしまいます。
意味と使い分けのポイント
文書を作るときは、まず読者の知識レベルと目的を見極めることが大切です。簡明な説明を目指すなら、読み手が初めて触れる概念でも迷わないよう、前提知識を過不足なく配置し、核心となる結論を先に示します。続いて背景や根拠の説明を短く補足しますが、それらはすべて「結論を支える根拠として意味がある部分」に限定します。反対に、簡潔な表現を選ぶ場面では、文章の長さを最小限に抑えつつ、意味が曖昧にならないよう慎重に言い換えを行います。例として、長い説明文を「何を伝えるか」を一文で置き換え、二文目以降はその文意を補完するだけに留める方法があります。
日常表現の落とし込み
日常生活では、簡明と簡潔を混同して使いがちですが、会話の相手や場面に応じて使い分けると伝わりやすくなります。例えば友人に道順を説明するときは、簡明さを意識して「ここを右に曲がって、次の信号で左折して下さい。目的地は三つ目の角にある赤い建物です」というように、要点を先に示します。一方、メールの一節を短くまとめるときは簡潔さを重視して「日程はいついつ、場所はここ、用件はこれです」と、余計な説明を削ぎ落として伝えます。このような実践を積むと、聞き手の負担が減り、情報の取りこぼしも減ります。
実用の比較表とケーススタディ
この章では、実際の文章でどのように二つの概念を使い分けるかを、具体的なケースに沿って解説します。まず、要点を明確に伝えるときには簡明さを優先し、情報の範囲を意図的に狭めて読み手が迷わないようにします。次に、同じ内容を表現する別の言い方として簡潔な語彙を選ぶことで、文の長さを削減します。以下の表は、日常的な文章の比較例を示しています。
最近、友達と雑談していて簡潔と簡明の違いがどう伝わるか話題になりました。私は、説明が長くなるほど人は情報を取りこぼしやすいと感じ、まず要点をひとつに絞って提示する簡明の力を思い出しました。次に、その要点を支える説明を不要な言葉で膨らませず、短く結論へ導くのが簡潔の技術だと考えています。結局のところ、場面を選び、伝えたい核心を先に置く練習を積むことが、コミュニケーションをスムーズにするコツだと思います。
前の記事: « クイックとスピーディの違いを完全解説!使い分けのコツと例文で学ぶ





















