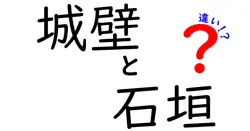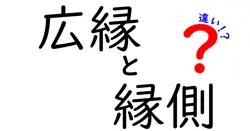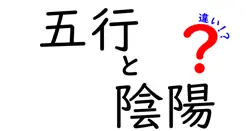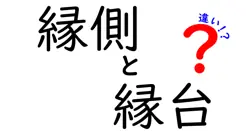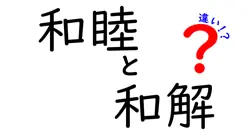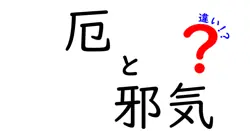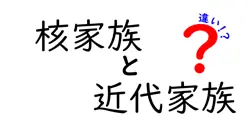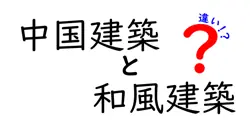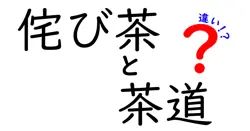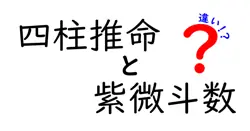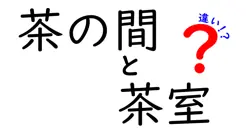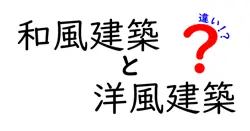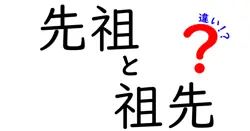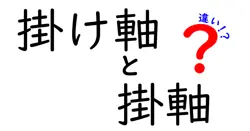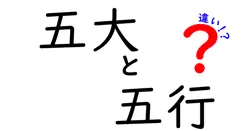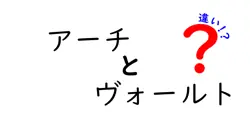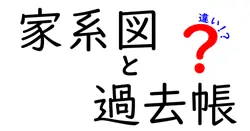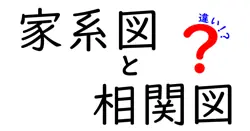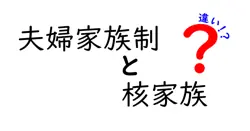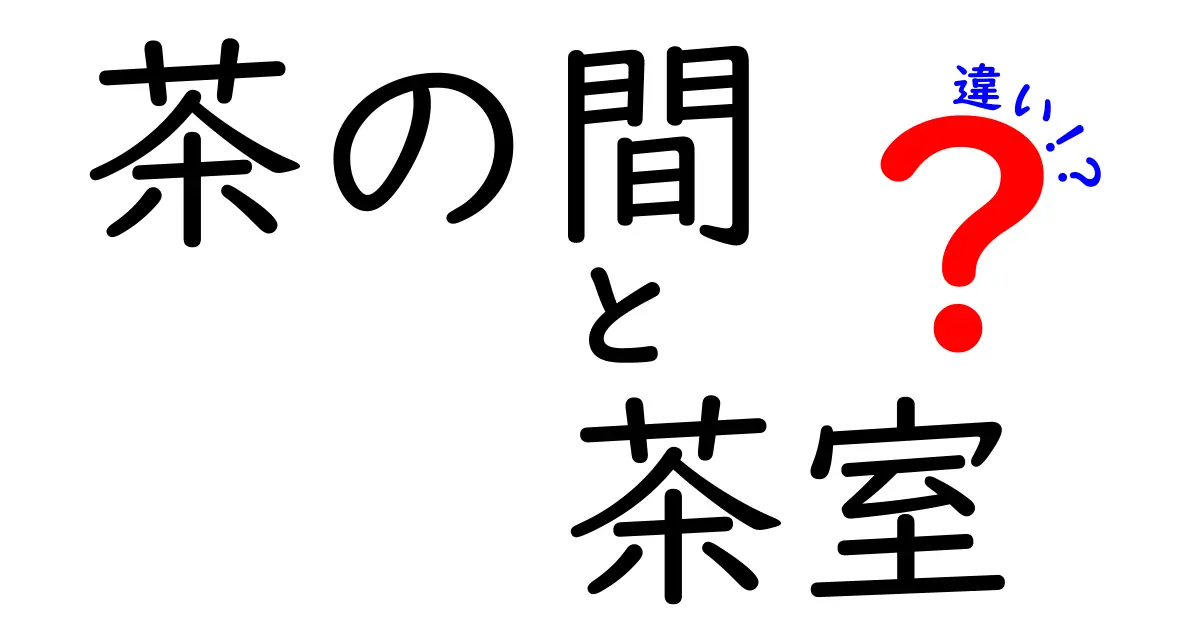
はじめに:茶の間と茶室って何が違うの?
日常生活の中で「茶の間」と「茶室」という言葉を聞いたことがありますか?
どちらも「茶」という言葉が入っていますが、その意味や使われ方は全く違います。今回は『茶の間』と『茶室』の違いについて、歴史や用途、特徴などを詳しくわかりやすく解説します。
日本の文化や生活に触れる良い機会となりますので、ぜひ最後までお読みください。
茶の間とは?
茶の間(ちゃのま)とは、日本の一般家庭でリビングや居間として使われる部屋のことを指します。
昔の日本家屋で、「茶の間」は家族が集まってお茶を飲んだり話をしたりする場として使われてきました。
現在ではリビングという呼び方が一般的ですが、昔はこの「茶の間」が生活の中心となっていました。
特徴としては以下のような点があります:
- 畳(たたみ)が敷かれていることが多い
- 床の間(とこのま)という装飾用のスペースがあることもある
- 家族の団らんや日常的な食事、お茶の時間などに利用される
また、茶の間は日本の家庭生活の象徴とされ、昔のアニメやドラマの舞台でもよく登場します。
茶室とは?
茶室(ちゃしつ)は、日本の伝統的な茶道を行うための特別な部屋や建物を指します。
茶道はお茶を点てて人にふるまう文化であり、茶室はそのために作られた厳密な空間です。
茶室は非常にシンプルで質素な造りが特徴で、自然素材が多く使われ、精神を落ち着ける空間として設計されています。
主な特徴は以下の通りです:
- 面積が狭く、小さな入り口が特徴的な「にじり口」
- 畳の数は一般的に3畳または4畳半
- 床の間があり、掛け軸や花が飾られる
- 茶道の作法に従った一定のルールや形がある
茶室は茶道のもてなし精神を表す場であり、使う人の心を整える役割を持っています。
また、茶室は単なる部屋ではなく、茶道の深い哲学や美学を表現した建築とも言えます。
茶の間と茶室の違いを表で比較
| 項目 | 茶の間 | 茶室 |
|---|---|---|
| 用途 | 家族の日常生活の場、リビング | 茶道のための儀式的な空間 |
| 広さ | 一般的に広めで靴を脱いで自由に使う | 狭く3畳から4畳半程の小さなスペース |
| 建築の特徴 | 畳敷き、床の間があることもある | にじり口、質素で自然素材 |
| 歴史的背景 | 江戸時代以降、庶民の家で用いられた | 茶道発展と共に武家や茶人が設計 |
| 精神性 | 日常の生活や交流の場 | 精神を集中しもてなす空間 |
まとめ:どう違うのかを理解し使い分けよう
茶の間と茶室は名前が似ていますが、その役割や雰囲気、作り方が全く違います。
茶の間は家族が集まる生活の中心地として日常的に使われる部屋です。
一方、茶室は茶道のために特別に設計された静謐(せいひつ)な空間であり、茶の湯の精神やおもてなしの心が息づく場所です。
どちらも日本文化の大切な部分ですが、目的や使い方を誤らないことが重要です。
今後、茶の間や茶室の話題が出たときに、この違いを自信を持って説明できるようになると良いですね。
ぜひこの機会に茶の間と茶室の違いを身につけて、日本文化をより深く楽しんでください。
「茶室」と聞くと、普通の部屋より小さくて静かなイメージがありますよね。実は、茶室の入り口には「にじり口」といって、頭をかがめて入るとても小さな入口があります。これは、すべての人が身分の差を忘れ、平等な気持ちで茶道を楽しむための工夫なんです。だから、茶室に入るときは自然と心が落ち着き、そしてお茶の時間が特別なものになるんですね。こんな細かなデザインひとつにも日本の茶道の奥深さが見えてくるんですよ!
次の記事: 糸入り襖紙と普通の襖紙の違いとは?特徴と選び方を詳しく解説! »