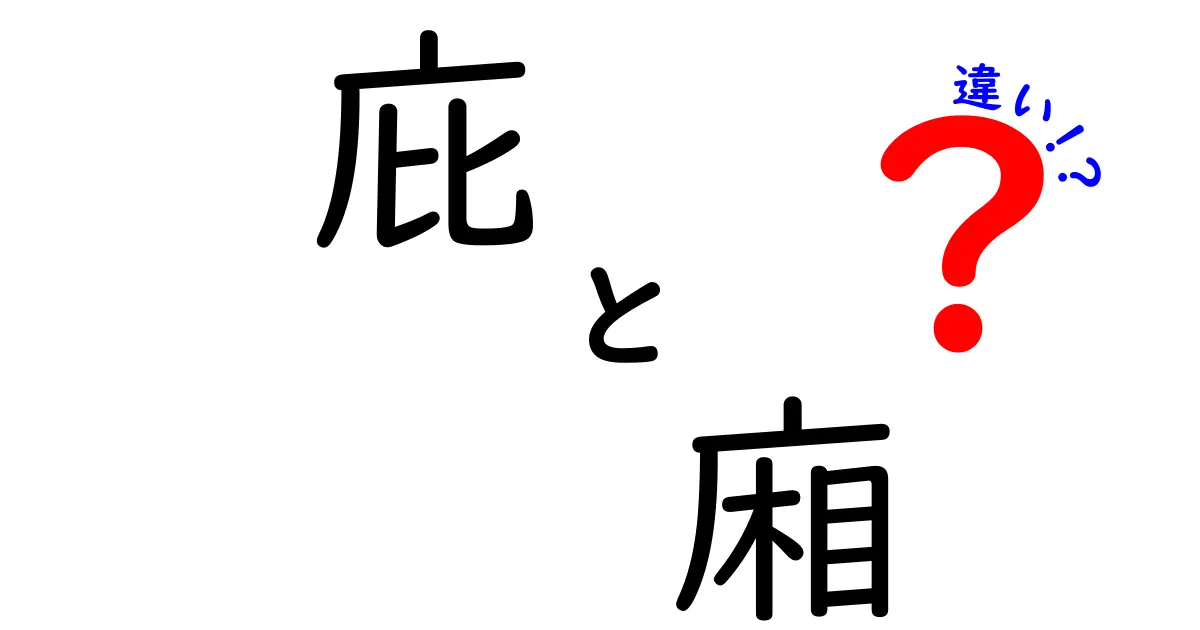

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
庇と廂って何?どちらも屋根の一部?
建物の屋根には、雨や日差しを防ぐために屋根の先端から突き出ている部分があります。この突き出た部分が「庇(ひさし)」と「廂(ひさし)」です。
しかし、どちらも「ひさし」と読みますが、その意味や使い方には違いがあります。中学生でもわかりやすく、
「庇」と「廂」の違いを建築の基本から見ていきましょう。
庇(ひさし)とは?
「庇」は、主に建物の窓や玄関の上に取り付けられた小さな屋根のことを指します。
雨よけや日よけとして機能し、外に付けられる小型の突き出し屋根です。
材質は金属製や樹脂、木製などさまざまで、現代の住宅に多く使われています。
庇は人の出入り口や窓の上に付けることで雨を避け、快適な生活をサポートします。
廂(ひさし)とは?
「廂」も「ひさし」と読みますが、建築用語としては主に伝統的な日本建築に用いられます。
本格的な「廂」は屋根が母屋(主屋根)から水平に伸びた部分で、建物の側面を覆う長い屋根の張り出しを意味します。
一般的には軒先や回廊のように広めの屋根の突き出しを指し、母屋の屋根を延長した形で建物の一部として存在するのが特徴です。
庇と廂の違いを表でまとめると?
| 項目 | 庇(ひさし) | 廂(ひさし) |
|---|---|---|
| 用途 | 窓や玄関の雨除けや日除け | 建物の側面を覆う広めの屋根の張り出し |
| サイズ | 小さい、突き出し部分が短い | 大きい、屋根の延長の役割 |
| 建築様式 | 現代住宅、多様な素材使用 | 伝統的な日本建築で使用 |
| 構造 | 独立した部材で後付けも多い | 母屋の屋根から延長された屋根部分 |
まとめ
「庇」と「廂」はどちらも「ひさし」と読まれますが、その役割や建築的な位置付けに違いがあります。
庇は主に窓や玄関の小さな雨よけ、廂は母屋の屋根から伸びた長い張り出し屋根と覚えておくと、建物を見るときに役立ちます。
使い分けや意味を理解することで建築知識が深まり、住宅や歴史ある建物の魅力をより楽しめますよ。
「廂」は日本の伝統建築でよく見られる屋根の遷延部ですが、実はその形状は地域や建物の種類によって多様なんです。たとえば、京都の古い町家では母屋から長く伸びる廂が独特の風情を作り出し、雨風をしっかり防ぐだけでなく、夏の暑い日には涼しい影をつくります。このように廂は日本家屋独特の工夫から発展した屋根の構造の一つなんですよ。
次の記事: 偏光と自然光の違いとは?簡単にわかる光の基本知識 »





















