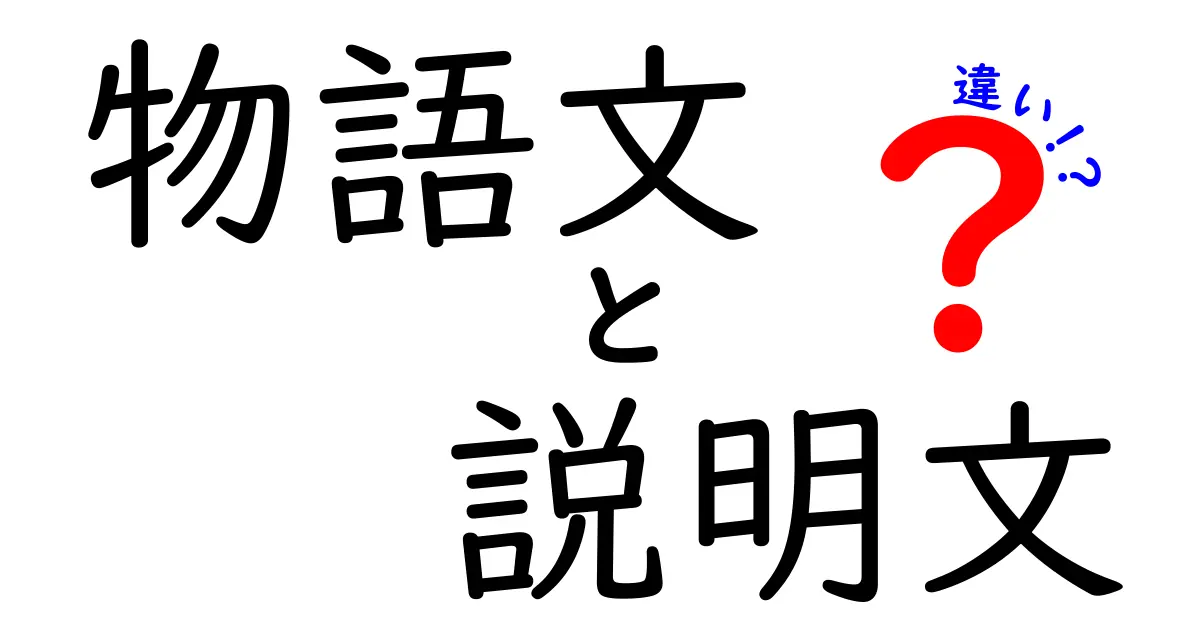

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
物語文と説明文の違いを徹底解説!中学生にも分かる読み方のコツ
物語を読むときと、教科書の説明を読むときでは、感じ方や読み方が少し変わります。
この違いを知ると、文章を読むスピードや理解の深さがぐんとアップします。
本記事では、物語文と説明文の基本的な違い、語り口の特徴、組み立て方の違いを、実践的な例や分かりやすい読み方のコツとともに紹介します。
中学生のみなさんにも分かりやすい言い回しで、日常の作文にも役立つポイントを丁寧に解説します。
この機会に、読み方のクセを身につけて、さまざまな場面で使い分けできるようになりましょう。
物語文と説明文の基本的な違い
物語文は「登場人物の動きや感情、場面の雰囲気」を中心に展開します。
物語を読むときには、誰が何をどう感じ、どんな出来事が起き、物語がどう進むのかを追うことが大切です。
一方、説明文は「事実・情報・しくみ・理由・手順」を伝えることが目的です。
読み手に正確な情報を提供し、理解を深めるための順序や論理の組み立てが重視されます。
文章のリズムはやや一定で、難しい用語が出てくるときは定義や例を添え、読み手を迷わせないように進めます。
この二つの特徴を押さえると、同じテーマでも全く違う読み方が必要だと分かります。
物語文は感情と場面の動きを追い、説明文は情報の正確さと論理の流れを追う、という基本線を覚えておくと、読み解く力がぐんと伸びます。
語り口と情報の組み立て方の違い
物語文では語り手の視点が重要な役割を果たします。
登場人物の心の動きや、場面の移り変わり、伏線の回収といった要素が、時間軸の流れとともに描かれます。
情景描写や比喩表現が多用され、読者は登場人物と一緒に体験する感覚を味わいます。
説明文では、語り口はやや客観的で、事実の提示と根拠の提示が中心になります。
情報は論理的な順序で並べられ、段階的に理解できるように構成されます。
この違いを意識するだけで、読み終えたときの理解の深さが変わります。
たとえば、同じ「地球の自転」を題材にしても、物語文なら登場人物が日常的に地球の動きを体感する場面を描き、説明文は自転のメカニズムと影響を順序立てて説明します。
このように、語り口と情報の組み立て方の違いを意識すると、文章の目的がはっきり見えてきます。
読み手としてのコツも併せて紹介します。
強調したい点を前半に置く、難しい語は分かりやすい言い換えと一緒に添える、段落ごとに1つの要点を持つ、などの基本を守ると、物語文も説明文も読みやすくなります。
また、読み始める前に「この文章は物語なのか説明なのか」を一度確認すると、読み方のクセを整えるのに役立ちます。
読書ノートをつける習慣もおすすめです。
どの表現がどの目的に適しているか、例とともに記録しておくと、作文にも使える知識になります。
実例で学ぶ:同じ内容を物語文と説明文で書くとどう変わるか
今回は「冬の公園で見つけた鳥の観察」をテーマに、同じ内容を物語文と説明文で書く練習をしてみましょう。 このように、同じテーマでも目的が変わると、文章の組み立ても大きく変わります。 読書のコツは、最初は全体像をつかむことです。 この練習を通じて、物語文と説明文の違いを体験的に理解し、使い分けられる力を身につけましょう。 ねえ、物語文と説明文の違いって、読み手が感じる感情の量と必要な情報の量の違いだと思うんだ。物語文は登場人物の気持ちの動きや場面の色を追って、心の振れ幅を楽しませてくれる。反対に説明文は、事実を並べ、手順を正確に伝え、読んだ人がすぐに理解できるように組み立てる。だから、友だちに映画の感想を語るみたいに読ませたいなら物語文、授業で新しい仕組みを覚えさせたいなら説明文と分けて考えるといいんだ。私が好きなのは、同じテーマを二つの形で書く練習。そうすると、伝えたいことが一段とクリアになる気がする。物語文の美しい表現と、説明文のはっきりとした論旨、それぞれの魅力を体験することが大切だよ。これからも、場面を描く力と論理を組み立てる力、両方を磨いていこう。
まず物語文では、鳥が飛ぶときを追い、木の枝で止まる瞬間の影や光の美しさ、そして観察している子どもの気持ちを描きます。
文体は感情を揺さぶる言い回しや比喩を使い、情景を立体的に表現します。
一方、説明文では、公園の地面温度の影響、鳥の行動の理由、観察の方法、注意点を整理して伝えます。
情報の正確さを担保するため、観察時の記録の手順や根拠となる事実に言及します。
同じ風景でも、物語文では読者の心情を動かす力が強く、説明文では理解を深めるための論理性が強く働きます。
このような切り替えを意識するだけで、文章を書くときの選択肢が広がり、読者に伝わる力も高まります。
以下の表は、物語文と説明文の比較を端的に示すものです。項目 物語文 説明文 目的 読者の感情を動かす 情報を正確に伝える 語り手 登場人物視点や作者の視点 中立な説明者 時間の扱い 場面の連続性や回想を使う 事実の順序をはっきりさせる 言い回し 比喩・情景描写が多い 要点を簡潔に伝える
物語文を読んで心を動かす力を育てつつ、説明文で情報を正確に伝える技術を並行して身につけることが、読解力と表現力の両方を伸ばす近道です。読み方のコツと練習法
見出し・段落の流れ・キーワードを拾い、どのような目的を持つ文なのかを自分なりに仮説づけします。
次に、要点をノートにまとめる練習をします。
物語文なら「登場人物の気持ちの変化と事件の因果関係」、説明文なら「根拠・手順・結論」の順に整理します。
また、読みながら声に出して読んでみると、リズムや語感が分かりやすく、理解が深まります。
最後に、他の教科の文章と比較する習慣を作ると効果的です。
例えば、科学の説明文と物語文を同じ現象で書き比べると、表現の幅が広がります。
この練習を地道に続けると、文章の見方と書き方の両方が鍛えられます。
ぜひ、今日は長さや難易度を少しずつ上げて、読書ノートを活用していきましょう。カテゴリ 物語文 説明文 文体 情感豊か、比喩多用 論理的、事実重視 読者の期待 共感と体験 知識と理解 構成 導入・展開・結末のドラマ性 序論・本論・結論の論理性
次の作文の課題で、同じテーマを両方の形式で書いてみると、さらに深く学べます。
言語の人気記事
新着記事
言語の関連記事





















