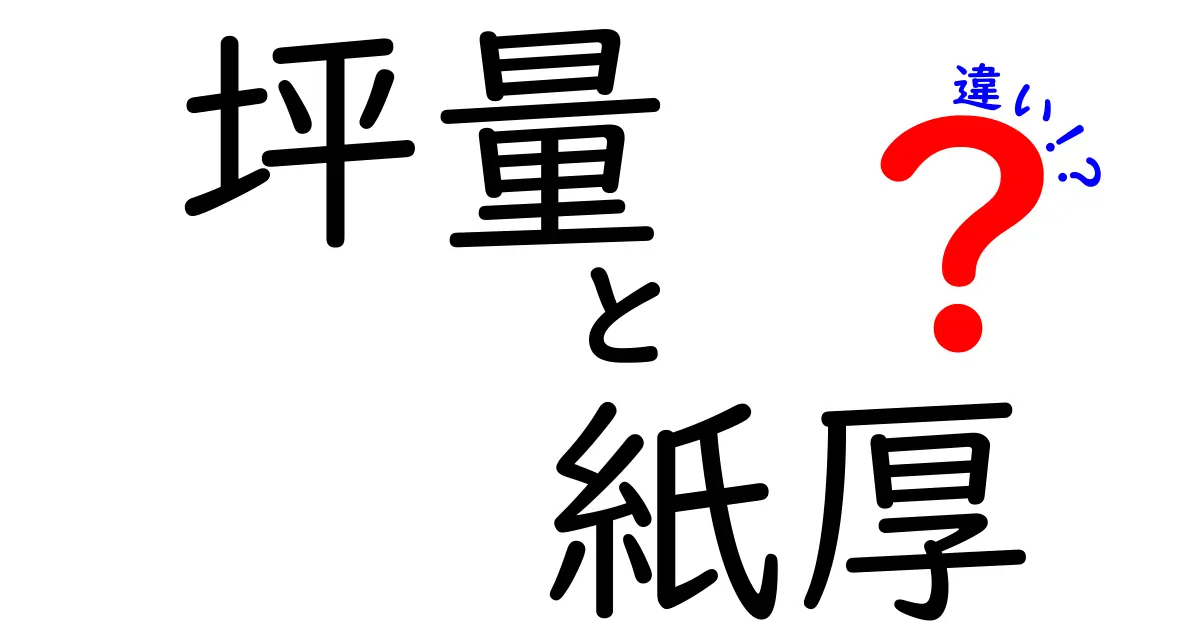

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
坪量と紙厚の違いを理解する基本のポイント
まずは前提となる用語を整理します。坪量とは紙の1平方メートルあたりの重さを表す指標で、単位は通常「g/m2」で表します。坪量が大きいほど、同じサイズの紙でも重く感じられます。ただし、紙の材質や製法によっては同じ坪量でも手触りに差が出ることがあります。次に
紙厚、つまり紙の薄さを示す指標は「ミクロン(µm)」や「mm」で表され、坪量と紙厚は必ずしも比例関係にはありません。薄い紙でも高密度に作られている場合は厚さが出ることがあります。これらの違いを知ると、印刷物や梱包材、ノート作りなど、さまざまな場面で適切な紙を選ぶ手助けになります。
坪量と紙厚の関係を直感で掴むコツは、実際の用紙を手に取り、握ってみることです。同じ坪量の紙でも、製紙工程での気泡を減らす技術や繊維の配列の違いにより、手触りや反り、透けやすさが変わります。印刷では、坪量の高さがインク受けや乾燥に影響します。紙が重く厚いと、インクの乾きが遅くなることがあります。一方で薄くて軽い紙は反りやすく、印刷機での搬送性が悪くなることも。
このような違いを把握することで、仕上がりのイメージを崩さずに、コストと品質のバランスをとることができます。特に名刺や案内状、パンフレット、ノートなど、用途に応じて坪量と紙厚を選択することが大切です。ここでは、坪量と紙厚の代表的な使い分けを見ていきましょう。
坪量と紙厚の違いを実務で使い分けるコツ
まず、印刷物の用途を決めることが第一歩です。高級感を出したい場合は、重い坪量の紙を選ぶと見た目がしっかりします。実際には、坪量が90〜120 g/m2程度の紙が一般的な印刷物でよく使われる範囲ですが、デザイン次第で上げ下げします。
価格と供給の観点でも検討します。同じ坪量でも紙のメーカーやロットによって価格が大きく異なることがあります。また、環境配慮の観点から recycled paper の選択肢も増えています。選ぶ際には、透け・白色度・表面の仕上がりの三点をチェックしましょう。
最後に、実務での使い分けのポイントを総括します。用途と求める美観・使い勝手・コストのバランスを見ながら、坪量と紙厚を組み合わせることが大切です。印刷物だけでなく、包装材、ノート、資料用ファイルなど、いろいろな場面で紙の特性を理解して選ぶと、完成物の仕上がりにムラが出にくくなります。紙選びは難しく感じるかもしれませんが、基本の考え方を覚えると迷いが減ります。
ある日、ぼくは友人とカフェでノートの紙について話していた。友人が『同じサイズのノートなのに、片方はずっしり重く、もう片方は軽い。これは坪量の違い?』と聞いてきた。僕は答えた。『坪量は紙1枚あたりの重さの目安だけど、同じg/m2でも紙の密度や繊維の方向で手触りは変わるんだ。つまり、同じ重量でも厚さが薄い紙は反って見えたり、印刷の乗り方が変わったりする。』会話は続き、店員さんが実際の紙を見せてくれると、私たちは『この紙は坪量が高いのに薄く感じる理由は、密度が高く繊維がきちんと詰まっているからだ』と納得。こうした雑談は、紙の選び方を楽しく理解するヒントになるんだよ。





















