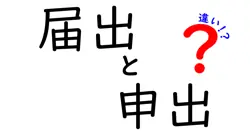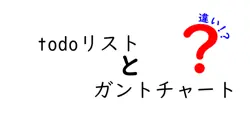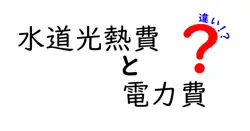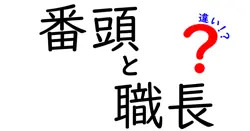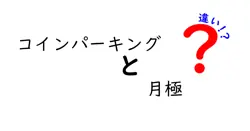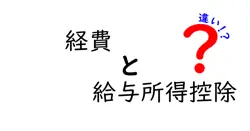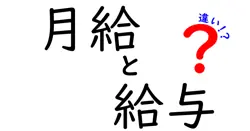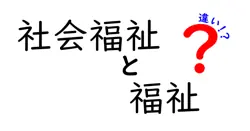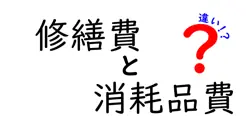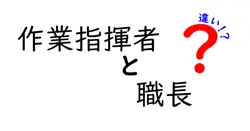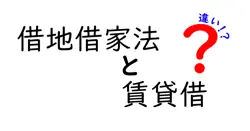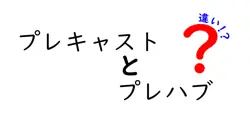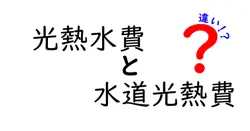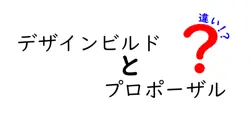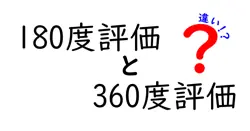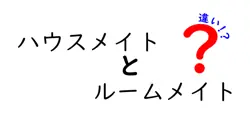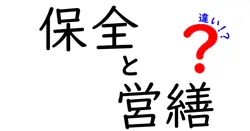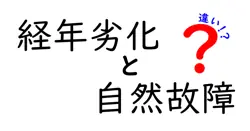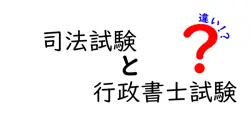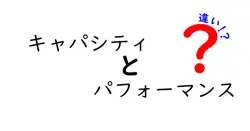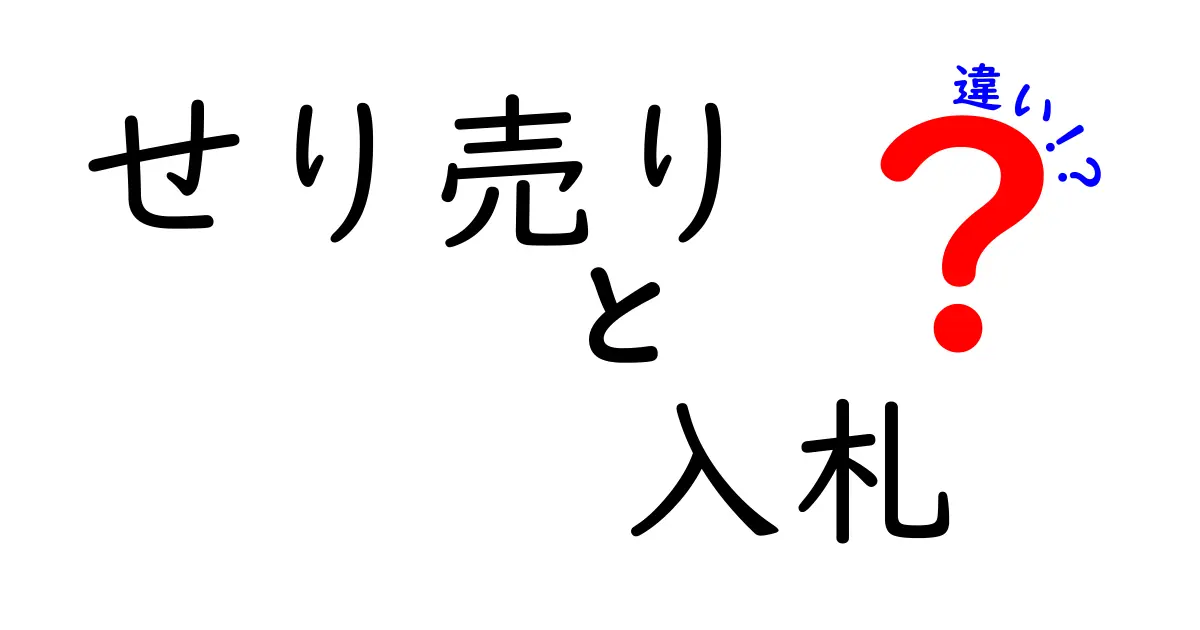
せり売りと入札の基本的な違いとは?
まずはせり売りと入札の基本的な違いについて説明します。せり売りは主に市場などで行われる競り上げ方式の販売方法です。参加者が価格をどんどん上げていき、最も高い価格を提示した人が買い手になる仕組みです。
一方、入札は多くの場合、公共事業や不動産の売買、または商品の購入時に使われる方法で、事前に提示された条件のもとで参加者がひそかに価格や条件を提出します。その中で最も条件が良いと判断された提案者が選ばれます。
このようにせり売りは会場でリアルタイムに価格が決まるのに対し、入札は決められた期間内に価格や条件を提出してから選考される点が大きな違いです。
せり売りの特徴とメリット・デメリット
せり売りでは、参加者がその場で競い合うため、商品やサービスの価値がリアルタイムで明らかになります。メリットは次の通りです。
- 商品の適正価格が見つけやすい。
- 参加者が直接競争するため、市場の動向が分かりやすい。
- スピーディーな取引が可能。
しかし、デメリットもあります。
- 価格が急激に上昇すると予算オーバーになる恐れがある。
- 購入者が焦ってしまい、冷静な判断ができにくい場合がある。
さらに、せり売りは現場の雰囲気や心理的な駆け引きが大きく影響することも特徴です。
入札の特徴とメリット・デメリット
入札は提案条件を提出してから審査や選考が行われるため、より計画的で客観的な取引が可能です。メリットとしては、
- 予算や条件に合わせた提案が可能。
- 公正で透明性の高い取引が期待できる。
- 購入者側が比較検討しやすい。
一方、デメリットは、
- 審査が必要なので時間がかかる。
- 参加者が条件を過度に調整して複雑になるケースがある。
入札方式は特に公共の仕事や大型取引でよく使われるため、公平さが求められます。
せり売りと入札の簡単比較表
| ポイント | せり売り | 入札 |
|---|---|---|
| 価格決定方法 | リアルタイムで競り上げ | 条件提出後選考 |
| 取引スピード | 速い | 遅い |
| 透明性 | 競争で見えやすい | 審査を経て公正 |
| 利用場面 | 市場、オークション | 公共事業、不動産 |
| リスク | 価格高騰の可能性 | 時間と手続きの負担 |
まとめ
せり売りと入札は、どちらも競争を通じて売買を行いますが、その形式や進め方に大きな違いがあります。せり売りは主にリアルタイムで価格が決まるのに対し、入札は条件を提出して比較・選定されます。
それぞれメリット・デメリットがあるため、用途や状況に応じて使い分けられているのです。
理解しやすい例として、せり売りは青果市場や競馬の馬の売買のような即時取引、入札は公共の建設工事の依頼や不動産の売買など、計画的かつ公正な取引によく利用されます。
この違いを押さえることで、社会の仕組みや経済活動の理解が深まりますね。
せり売りの面白いポイントは、会場の雰囲気や参加者の心理戦が大きく影響するところです。例えば、価格が一気に跳ね上がることもあれば、誰も手を挙げないで商品が売れ残ることもあります。これは人の感情や戦略が直に取引に反映されるためで、単なる金額のやり取り以上のドラマがあります。こうしたリアルタイムのやりとりは、オンラインや事前提出で行う入札にはない独特の魅力と言えるでしょう。