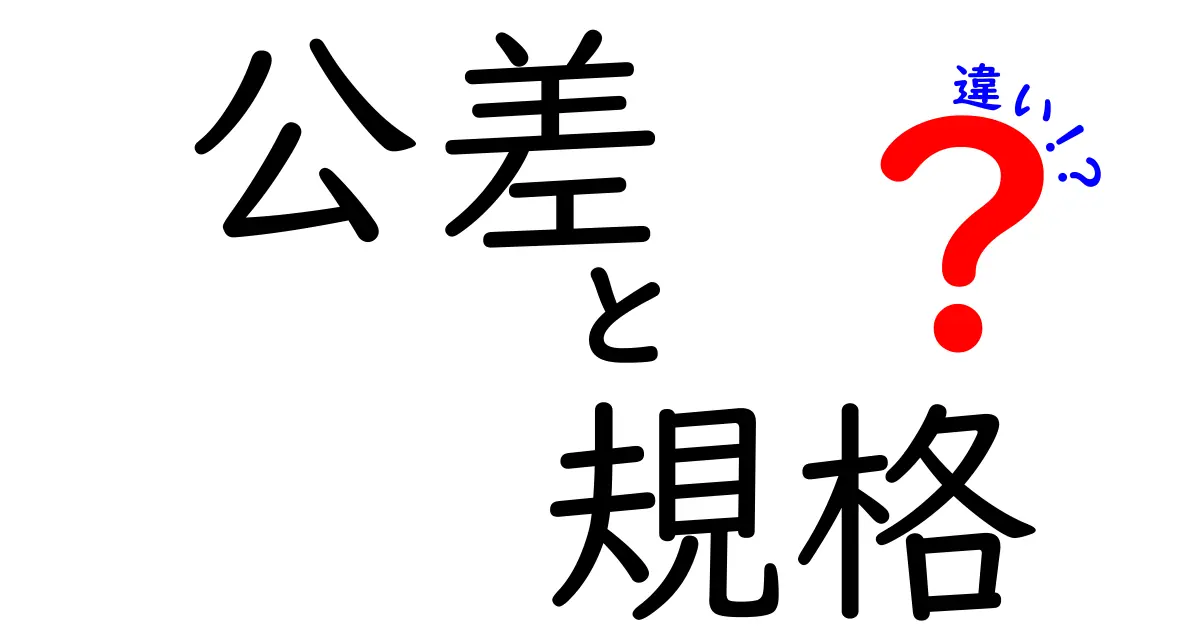

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
公差と規格の基本を押さえる
公差は製品のサイズがどれだけ「正確」に作られているかを表す数値です。製作工程で測定誤差や加工具のたわみなどが起こるため、部品同士が「現実に入るかどうか」を判断する基準として用いられます。公差の目的は部品の機能と組み立てを安定させること、したがって規格が厳しいほど公差は小さく、自由度は低くなります。例として長さを公差±0.05mmと指定すると、指定の寸法から±0.05mmの範囲に収まる部品だけが許容され、取り付け時の遊びや過大な圧力の発生を防げます。
一方、規格とは“標準の基準”のことです。規格は団体が決める道具や寸法の基準値の集合であり、国際的にはISO、国内ではJISや各業界団体の規定が使われます。規格が明確であれば異なるメーカーの部品同士を組み合わせる際の互換性が保たれるのが大きな利点です。例えばネジ山のピッチやボルトの規格が揃っていれば、別のメーカーのナットを使っても問題なく締結できます。
ここで混同しやすい点を挙げると、規格は必須ではなく任意の取り決め、しかし公差は設計上の必須事項という点です。部品の型式や用途によっては、規格を超えた特別な公差を設定することもあります。図面には通常、公差の種別(寸法公差、形状公差、位置公差など)と適用範囲が記され、
規格は適用される標準の名称や番号が併記されます。
以下の表は、よく出てくる公差と規格の例を簡単に比較したものです。実務ではこのように「寸法公差」と「規格名」を並べて書くことで、製造と検査の現場が同じ言葉で話せるようになります。
このように、公差と規格は別の意味を持ちながら、製品の品質や機能を決めるために協力して働きます。初心者の人は最初に「公差は作る側の許容範囲、規格は使う側と作る側の約束事」と覚えると理解しやすいです。
友人と理科の話をしていたとき、突然“公差”の話になりました。私は「公差は“ここまでならOK”という部品の許容範囲のことだよ」と説明しました。彼は最初、“規格”とどう違うのかを混同していましたが、私が日常の例えでこう伝えると腑に落ちたようです。たとえばスマホのケースを作るとき、ケースの穴の位置を少しずらしてもギリギリ入る範囲を公差といい、ケースの素材や接続部のサイズが世界中で同じであるべきというのが規格です。公差はその場の都合で調整可能な設計の余白、規格は長く安定して使えるための約束事。現場ではこの二つが噛み合って、部品同士がぴったり合う喜びを生むんだと実感しました。こうした現場の工夫が、品質とコストのバランスを取るコツになるんですよ。





















