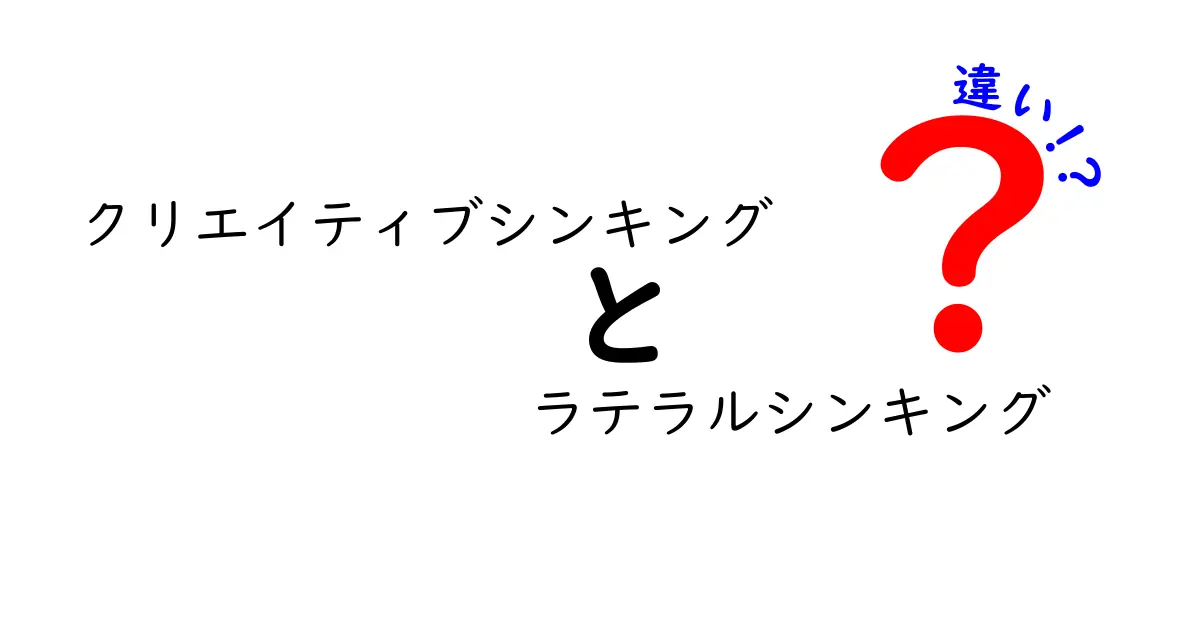

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
クリエイティブシンキングとラテラルシンキングの違いを知るための基礎
クリエイティブシンキングとは新しいアイデアを生み出す心の方法で、既存の枠にとらわれず、多様な情報を結びつけて新しい可能性を探すプロセスです。想像力を広げるためには、まず問題を複数の角度から見る練習が必要です。発想の起点は自由であり、何が正しいかを最初から決めつけず、あえて仮説をたくさん立ててみることが大切です。物語風に考える、比喩を使う、他の分野の事例を持ち込む、こうした方法で頭の中の壁を外します。
これに対して、ラテラルシンキングは「直線的な解決策」を避け、別のルートや見落とされたルールを探す発想の転換です。通常の論理展開を崩し、問題を別の前提へ移動させて、意外な組み合わせから答えを見つけ出します。例えば、ある課題を"反対の問い"として逆転させてみる、枠組みの外側から材料を選ぶ、常識を疑う手法などが挙げられます。
つまり、クリエイティブシンキングは「新しいものを作る力」を指し、ラテラルシンキングは「新しい見方で解決する力」を指すと覚えると分かりやすいです。両者は競争するものではなく、むしろ補完的な関係にあります。創造的な成果を出したいときには、まず前者で大量のアイデアを生み出し、その後後者を使って現実的な解決策へと絞り込むと効果的です。
日常の学習や仕事での活用例として、授業の課題、部活動の企画、友人との協力プロジェクトなど、さまざまな場面が挙げられます。 クリエイティブシンキングはたとえば物語づくりや新しい学習法の提案、既存の教材の組み替えなど、創造的なアウトプットを生むのに向いています。ラテラルシンキングは日常の問題解決を楽にする道具で、困難な課題を「どうすれば別の角度で解けるか」を常に問う癖を養います。
ここで重要なのは、両方とも練習と習慣が大切だという点です。思考の癖を変えるには、意識して練習日記をつける、アイデアの数を増やす、意図的に異分野の情報を取り入れる、失敗を恐れずに試す、などの工夫が必要です。
実践で差がつく具体例と活用シーン
学校の課題や部活動の企画、友人とのグループワークなど、具体的な場面を想定して考えると、クリエイティブシンキングとラテラルシンキングの使い道が見えてきます。クリエイティブシンキングは新しい視点でのアイデア出しに強く、物語を作る、教材を再設計する、難しいテーマをわかりやすく伝えるための比喩を考えるなど、アウトプットの質を高める力になります。ラテラルシンキングは解決策を絞り込むときに役立つ力で、問題の前提を変えたり、別の素材や方法を組み合わせて新しい解を生むときに有効です。
例えば、イベントの企画をするとき、クリエイティブシンキングで見たことのないテーマやストーリー性を作り込み、来場者の心をつかむ演出を考えます。その上でラテラルシンキングを使い、費用や時間、場所といった現実的な制約を乗り越える具体策を見つけ出します。
このように、頭の中でうまく「二つの道具」を使い分ける練習を重ねることで、発想力と現実性の両方を高めることができます。日常の授業やクラブ活動、将来の職業選択にも、創造性と実行力を同時に鍛える良い機会になるはずです。
- アイデア創出の段階: まず大量の案を出し、後で絞り込む。クリエイティブシンキングの真髄は「量を確保すること」にあります。
- 問題の前提の見直し: ラテラルシンキングは「この前提は本当に正しいのか」を問う力で、無意識の偏りを避けるのに役立ちます。
- 異分野の結合: 他の教科や分野の考え方を組み合わせると、驚くような組み合わせが生まれやすくなります。
- 実行可能性の評価: アイデアを現実の制約と比較して、実現性の高いプランへと落とし込むプロセスが重要です。
このように、創造力と実行力を同時に育てることが、学習や社会生活での大きな武器になります。
思考を鍛える練習として、日々の学習日記へ「新しい角度」「別の前提」「実現性のアイデア」の三つを意識的に書き留めると良いでしょう。
継続は力なり、即ち毎日少しずつ訓練することが、最終的に大きな差を生む鍵になります。
koneta: ラテラルシンキングって、直線的な発想を飛び越える雑談型の思考だよね。友だちと新しい遊びを生み出すとき、正解を急がず、ありえない組み合わせをいくつも口にしていくと、突然、ひらめきが生まれるんだ。身近な例で言えば、部活の練習メニューをただ繰り返すのではなく、違う道具や場所を使って、同じ目的を別の角度から達成する案を出す感じ。ちょっとした奇想天外な案でもとりあえず挙げてみる。そうして「じゃあこれをどう現実的にするか」を話し合ううちに、実行可能なアイデアへと絞り込める。こんな雑談の積み重ねが、普段の学習や生活の中で新しい発想を作る力になる。





















