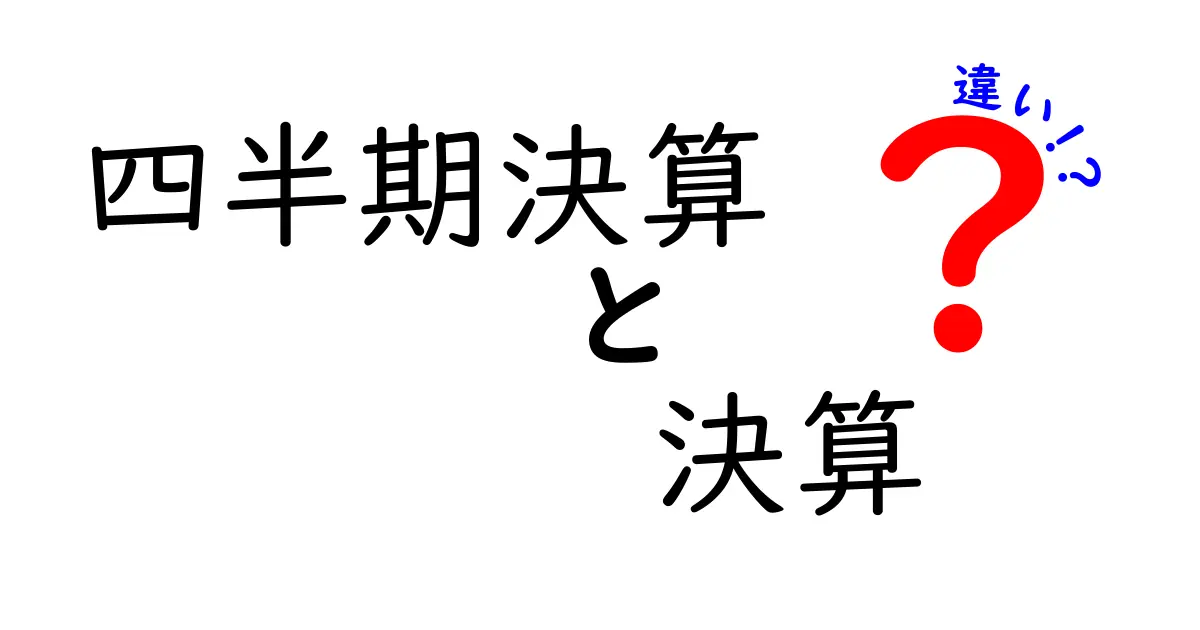

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
四半期決算と決算の違いを知るための基本
四半期決算と決算の違いを学ぶと、株式投資や会社のニュースが理解しやすくなります。この記事では、四半期決算と決算の基本的な意味から、実務での使い方、どんな人がどの場面で意識すべきかまで、中学生でも分かるようにやさしく解説します。まずは「期間の違い」「開示の頻度」「含まれる指標」「市場の受け方」という4つのポイントを軸に整理します。
四半期決算は3か月ごとの報告で、決算は1年分の報告という考え方が基本です。企業の業績を短期間で把握したいとき、投資家は四半期決算を特に注目します。反対に、企業の長期的な成長性や安定性を判断するには決算の年次データが重要です。この記事を読めば、ニュースの文脈で「四半期決算が出た」「決算発表があった」という言葉の意味がすぐに分かります。
四半期決算とは何か
四半期決算とは、企業が四半期ごとにまとめた業績の報告のことです。日本の上場企業では通常、3か月ごとに財務状況を公表します。具体的には売上高、営業利益、経常利益、当期純利益、1株当たりの利益(EPS)などの指標がその四半期の期間にどれだけ動いたかが示されます。四半期決算は「 quarterly 」と訳され、期間が短い分、急な業績の変動が反映されやすいという特徴があります。季節の影響を受けやすい業種(小売、観光、エネルギーなど)では、四半期ごとの数字の上下が大きく動くことも珍しくありません。これにより株価は短期的に反応します。
また、四半期決算はIR資料として公開され、投資家だけでなくメディアやアナリストにも注目されます。公表日が決まっており、事前に予想が出されることも多いです。
企業は会計基準に従って数字を算出しますが、四半期の「ずれ」が生じる理由として、在庫評価の方法、為替の影響、事業再編の効果などが挙げられます。これらを理解していれば、ニュースで「○○社は四半期決算で増収増益」といった見出しを読んだとき、どの程度実態を反映しているのかを判断しやすくなります。
決算とは何か
決算とは、企業の1年間の財務状況と経営成績をまとめた報告のことです。通常、会計年度の終わりに作成され、売上高・営業利益・当期純利益・総資産・株主資本などの数値が、1年間を通じてどのように推移したかを示します。決算は年次報告としての意味が強く、長期的な成長性や財務健全性を判断するための核となる資料です。上場企業は「決算短信」や「有価証券報告書」などの正式文書を開示します。公表タイミングは会社によって異なり、年度末直後にリリースされることが多いですが、決算説明会を開催して詳細な説明を行う企業も多いです。
この年次データは、投資家や分析家が株価を評価する際の基礎情報として使われ、財務諸表の読み方を理解する力が必要になります。経営戦略の方向性、借入の水準、キャッシュフローの安定性など、数字だけでなく背景にも目を向けることが大切です。
四半期決算と決算の違いを整理してみよう
要点として、期間、頻度、指標、投資家の注目ポイント、ニュースの読み方の違いがあります。期間の違い: 四半期決算は3か月、決算は1年間。
開示の頻度: 四半期は年4回程度、決算は年に1回か2回(決算短信と有価証券報告書)
扱う指標: 四半期は四半期の動きを中心に、決算は累計の通期データが重要。
影響の受け方: 四半期は株価が反応しやすい短期要因、決算は長期の評価要因。
読み解くコツ: 四半期は季節要因や一時差が影響することが多い。年次データは財務健全性・成長性の総合評価に役立つ。
ある日の休み時間、友だちと『四半期決算って何がそんなに大事なの?』と話していた。私はこう答えた。四半期決算は“最近の業績の勢いを見る窓”であり、決算ほど長期的な評価には直結しづらい。だが、企業が“今、どう動いているか”を知るには最適な窓口だ。数字の背景には季節要因や新製品投入、為替の変動などがあり、単なる数字の大小だけで判断してはいけない。結局は、短期と長期のバランスを読む練習なのだ、という雑談だった。
次の記事: 営業費と販管費の違いを徹底解説!実務で使える見分け方と事例 »





















