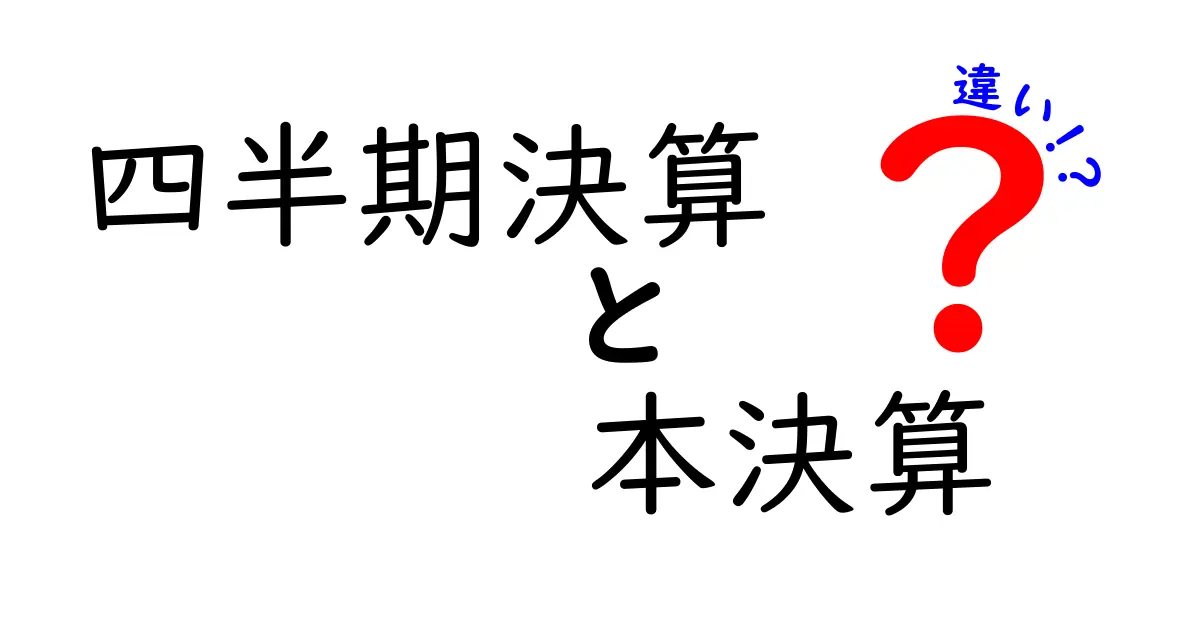

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
四半期決算と本決算の違いを徹底解説|投資初心者が知っておくべき基本と読み方
四半期決算とは、企業が四半期ごとに作成する財務報告のことです。通常は売上高、営業利益、経常利益、当期純利益などの主要指標が開示されますが、四半期決算は多くの場合監査が限定的であるか、監査を受けていない場合もあります。これは企業の成長ステージや監査方針によって異なります。
本決算は会社の年度末に作成され、外部の監査法人による監査を受けた後に公表されることが多く、より信頼性が高いと判断されます。四半期決算と本決算の違いを知ることで、数字の良し悪しを誤解せず、時系列での業績推移を正しく読み取ることができます。
また開示のタイミングにも違いがあり、四半期決算は年4回、四半期ごとに公開されるのに対して、本決算は年1回の開示が基本です。企業が公表する際には、決算短信という文書が使われ、他にも有価証券報告書やIR資料が出されます。
この違いを正しく理解するには、指標の意味と開示の仕組みを押さえる必要があります。そこから読み解くポイントとして、「期間の違い」「監査の有無」「開示の頻度と信頼性」の3点を意識すると、数字の裏側にある実力を掴みやすくなります。
セクション1:概要と基本の違い
四半期決算は、現在の事業がどのように進んでいるかを、短い期間の視点で確認するための報告です。売上が想定以上かどうか、費用は計画通りか、在庫や売掛金の動きはどうかといった点を、「3か月という短い期間で切り取って」示します。これに対して本決算は1年間の経営成績をまとめ、会社全体の持続可能性や長期的な成長性を評価する材料になります。
重要なのは、四半期決算は「今、この瞬間の状況を伝える」ことが目的であり、通期の計画と乖離があるかどうかの評価にも活用される点です。一方、本決算は「1年を通じてどれだけの成果を上げたか」を示し、監査を受けた正式なデータとして市場の信頼を高める役割を担います。
この違いを理解することで、同じ会社の別の決算発表を比較するときに、単一の数字だけで判断せず「期間の背景」や「監査の有無」を意識した読み方ができるようになります。
セクション2:指標の読み方と時期の違い
四半期決算と本決算で最も見るべき指標は似ていますが、意味の捉え方が微妙に異なります。売上高は成長の度合いを示す核となる指標ですが、四半期決算では季節要因や一時的な要因が影響しやすく、前年同期比が大きく動くことがあります。したがって、四半期決算だけで判断せず、前年や前四半期との比較をセットで見ることが大切です。
本決算では、年度を通じた安定性や費用管理の健全性が評価されます。当期純利益やEPS(1株当たり利益)などの利益指標は、長期的な成長ストーリーと資本配分の適切さを示す材料として重視されます。
また、通期のガイダンス(今後の見通し)と実績の乖離を確認することで、会社が市場の期待に対して現実的な見積もりを出しているかを判断できます。四半期と本決算を同時に見ることで、季節性と長期トレンドの2軸で企業の実力を読み解く力が養われます。
セクション3:実務での注意点と表の読み方
実務では、決算の文書を読む順番を工夫すると理解が深まります。まず決算短信の主要指標(売上高・営業利益・当期純利益)をサラッと把握し、その後に前年同期比・前期比、セグメント別のデータ、そして連結と個別の区別を確認します。
比較の際は、短期の伸びだけで判断せず、「持続可能な成長か」「費用の増減はどこから来ているか」をチェックします。表を見るときは、まず総額の動きを追い、次に構成比の変化(売上構成の変化、費用の内訳)を見ます。
表には多くの数字が詰まっていますが、最初に全体の傾向を掴み、次に細部の内訳へ進むのが読み方のコツです。最後に違いを理解するための簡易メモとして、四半期決算と本決算のポイントをまとめたチェックリストを頭の片隅に置いておくと、ニュースやIR資料を読んだときに混乱しにくくなります。
今日は友達と雑談するように四半期決算と本決算の違いについて深掘りしてみた。友人Aが四半期決算の速報を見て『なんかよく分からない』と言った。そこで私は、四半期決算はスナップショットみたいなものだと説明した。つまり三か月の間に起こった“良い出来事”も“悪い出来事”も、1年の長い流れで見れば歪みの一部に過ぎないという考え方だ。
「でも弟君、どうして監査の有無が大事なの?」と友人が尋ねた。私はこう答えた。監査の有無は信頼性の指標であり、年末の本決算は外部の専門家が検証する。だから長い目で見ると、四半期の数字が過大評価されているのか、実力通りなのかを判断する手がかりになる。
さらに、四半期と本決算の両方を見比べると、企業の計画と現実のギャップが見えてくる。私たちは日常のニュースで「売上が伸びた」「利益が減った」といった言葉を耳にするが、そこには季節性や特定のイベントの影響が潜んでいる。だから総合的な判断には時期の違いを理解することが不可欠だと伝えた。最後に彼は表を一緒に見て、長期のトレンドを掴む練習を約束してくれた。
前の記事: « 販売費と販管費の違いを徹底解説!中学生にもわかる経理の基礎ガイド





















