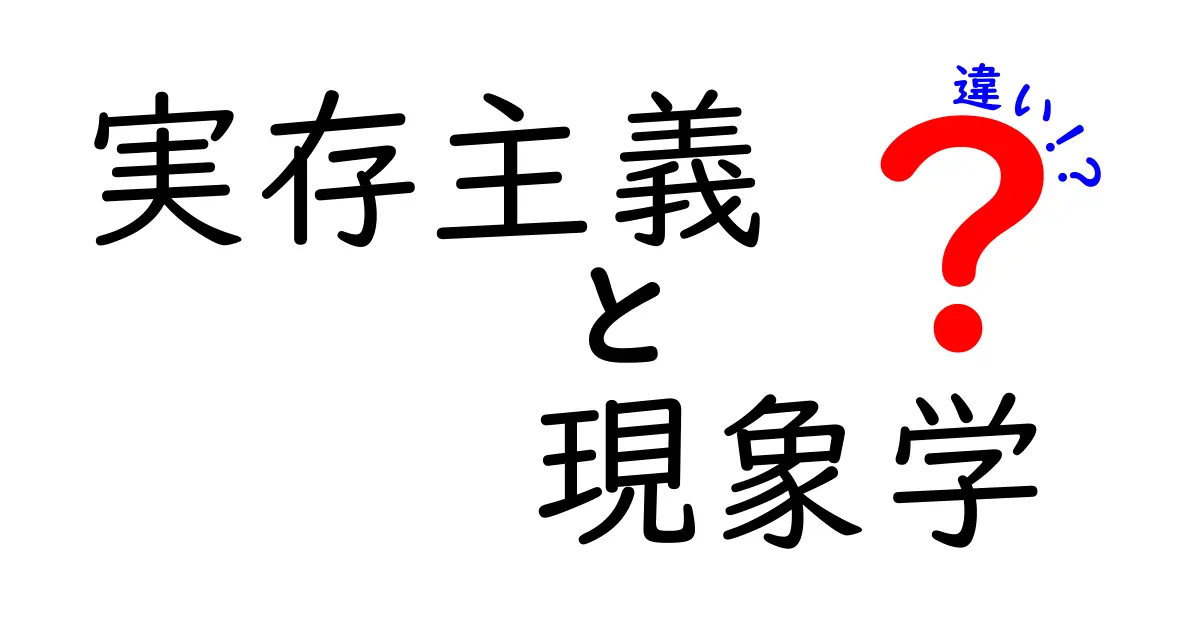

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
導入:実存主義と現象学の世界へようこそ
ここでは実存主義と現象学の基本を、中学生にも伝わる言葉で紹介します。
哲学というと難しく感じるかもしれませんが、日常の体験と深くつながっています。
実存主義は「自分の存在と自由な選択」を中心に考え、現象学は「私たちが世界をどのように感じ取り、経験として現れるか」を大切にします。
この二つは同じ哲学の道具箱の中の異なる道具のようなもので、同じ事柄を別の視点から見つめます。
例えば、朝起きて学校へ行く日常を考えてみましょう。眠気や緊張、友だちの顔色、授業の進み方などをどう感じ、どう受け止めるか。これらの場面を通して、二つの考え方がどう働くのかを見ていきます。
まずは実存主義の“まなざし”から。存在そのものを前提とする生き方を考えると、私たちはいつも「自分がどう生きたいか」「何を選ぶべきか」という問いに直面します。
そのときの気持ちや選択の重さは、他の人がどう感じるかよりも自分の心に強く響きます。
この観点は、学校の部活選びや将来の夢を決めるときに、自由と責任をどう結びつけるかを考える手がかりになります。
次に現象学の視点を見てみましょう。
実存主義と現象学の違いを詳しく見る
二つの考え方は似ているようで、焦点と方法が異なります。
まず焦点の違いを押さえましょう。実存主義は主に「自分の存在と自由」を中心に考え、人生の選択に注目します。現象学は「世界の現れ方」や「経験の構造」に着目します。
次に方法の違いです。実存主義はしばしば人の生い立ちや選択の物語を語ることで意味を見つけようとします。現象学は私たちが何を感じ、どう気づくかを、体験を書き起こすように詳しく分析します。
補助的な例として、二人の登場人物を想像しましょう。ある人が朝の通学路で感じる緊張と安心感を、実存主義の視点では「自由な選択の演出」として、現象学の視点では「視覚や聴覚など感覚を通じて作られる現象」として見分けます。
- 焦点:実存主義は存在と自由、現象学は経験の構造と現れ方を重視する
- 方法:実存主義は個人の選択の物語化、現象学は意識の中の経験の分析を重視する
- 問いの立て方:実存主義は「私はどう生きるべきか」を探る、現象学は「私は何をどう感じ取るか」を観察する
表を使って比較すると理解が深まります。以下の表は二つの考え方の基本を並べたものです。
実際には両者を組み合わせて使うこともあり、日常の見方を豊かにしてくれます。
日常生活への影響と実用的な学び方
実存主義と現象学の違いを知ると、友だちとのやりとりや自分の気持ちの扱いが変わってきます。
例えば、部活の仲間にどんな支えを求めるか、将来の進路をどう選ぶか、困ったときに自分の内面と向き合うヒントになります。
現象学の視点は、日常の出来事をただ流すのではなく、感覚や思い込みを分析して、物事の真の姿を少しだけでも近づける練習になります。
実存主義の視点は、自分の自由と責任を自覚することで、周りの意見に流されず自分の選択の理由もしっかり伝えることが大事です。
もし友人が悩んでいるとき、二つの視点を使って話を組み立てると、相手にも伝わる言葉が生まれます。
この学びは授業だけでなく日常の会話にも役立ちます。
たとえば授業中の出来事を振り返るとき、何を感じたのか、なぜそう感じたのかを自分自身に問い直す習慣がつきます。
また友人と意見を分かち合うときも、相手の感じ方を尊重しつつ自分の考えを伝える練習になります。
こうした小さな学びの積み重ねが、将来の大きな判断力につながるのです。
現象学という言葉を、友だちと朝の教室で話す場面に置き換えてみよう。先生が黒板に消しゴムの跡を描くとき、周りの人のざわつきがどう現れるかを感じ取る。現象学はそんな“現れ方”を丁寧に観察する学問だ。私たちの感じ方はいつも変わる。腹がすいたときの空腹感、天気が悪い日に沈む気分、それらをそのまま受け止めず、どうしてそう感じるのか、どんな状況で変わるのかを考える。現象学はその“現れ方”を順序立てて観察します。実存主義は、そんな感覚の奥にある自由と責任を意識させ、私たちが自分の人生を選ぶ力をくれる。会話の中で、友だちは現象学の視点を借りて相手の気持ちの変化を観察し、実存主義の視点で自分の選択の意味を見つけようとする。こうした雑談を続けるうちに、難しい言葉が自然に身についていくのです。
次の記事: 質的研究と量的研究の違いを徹底解説:中学生にもわかる入門ガイド »





















