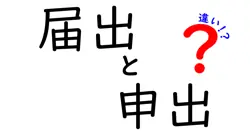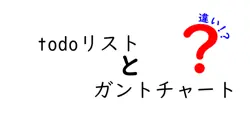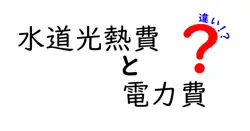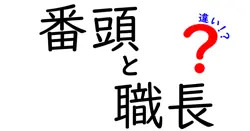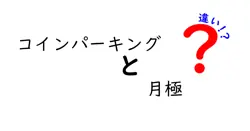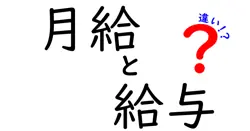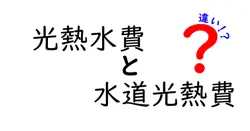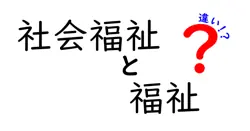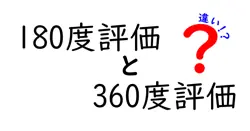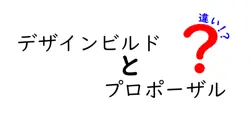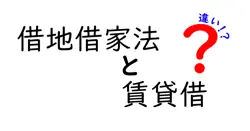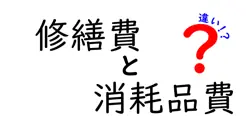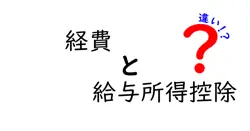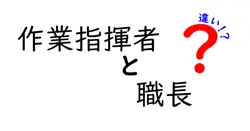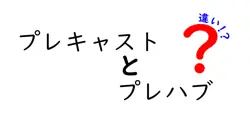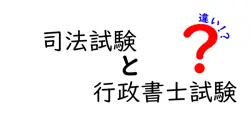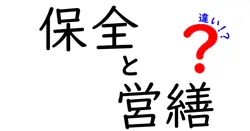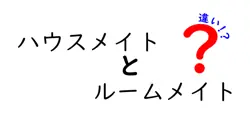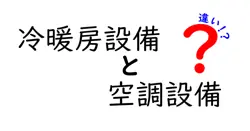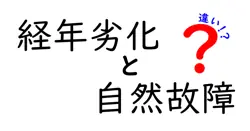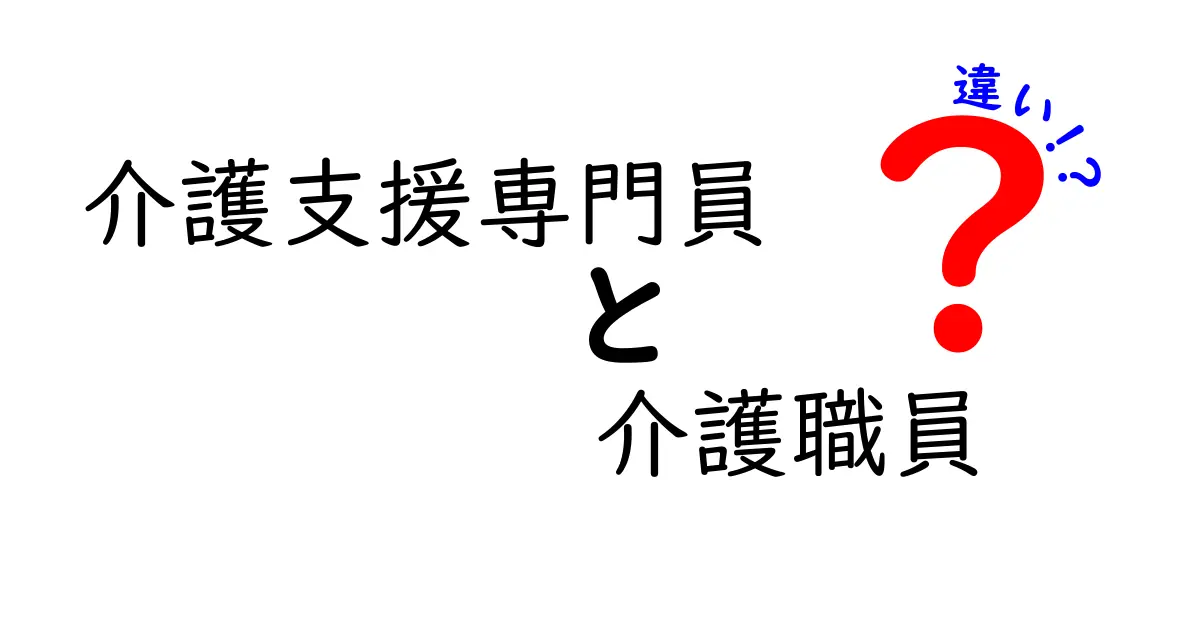
介護支援専門員と介護職員とは?基本の理解から始めよう
介護の現場には様々な職種がありますが、今回は特に介護支援専門員と介護職員の違いについてわかりやすく説明します。
まず、介護職員は実際に高齢者や障害者の日常生活のサポートを行う方々です。身体介護や生活援助が主な仕事で、利用者の身の回りの世話を担当します。
一方で、介護支援専門員は、利用者が適切な介護サービスを受けられるように計画を立て、調整する専門家です。ケアマネージャーとも呼ばれ、介護計画(ケアプラン)の作成やサービス提供の調整を担います。
このように、介護支援専門員は介護職員の仕事がスムーズに行われるように支援する役割で、両者は役割や仕事内容に明確な違いがあります。
介護支援専門員と介護職員の資格の違い
介護支援専門員は法律に定められた国家資格で、取得には一定の条件があります。
・まず、介護職員や医療・福祉関係の仕事で実務経験が5年以上必要です。
・その後、養成講座を受講し、国家試験に合格することで資格が得られます。
対して、介護職員には国家資格である介護福祉士や実務者研修、初任者研修など複数の資格がありますが、無資格でも働くことが可能です。
つまり、介護支援専門員は専門的な資格を持ち経験豊富な方が担う専門職であるのに対して、介護職員は比較的入りやすい職種と言えます。
仕事内容と役割の違いを具体的に説明
介護職員の主な仕事は、利用者の食事や入浴、トイレの介助など身体的なサポートや、掃除や買い物など生活面の支援です。
一方で、介護支援専門員は利用者の状態を把握し、必要なサービスを選んで計画を作成。その計画を基に介護職員や医療機関と連携し、介護サービスの提供が円滑に行われるよう調整します。
このため、介護支援専門員は利用者と介護サービスの橋渡し役として、とても重要な役割を果たします。
下の表に両者の主な違いをまとめました。
| 項目 | 介護支援専門員 | 介護職員 |
|---|---|---|
| 資格 | 国家資格が必要(ケアマネジャー) | 無資格でも可。介護福祉士など複数資格あり |
| 主な仕事 | ケアプランの作成・調整・連絡調整 | 身体介護・生活援助 |
| 役割 | 介護サービスの調整や計画立案 | 利用者の日常生活のサポート |
| 必要な経験 | 一定の実務経験が必須 | 特に経験は必須ではない |
まとめ:それぞれの役割を理解して介護現場を支えよう
介護支援専門員と介護職員は仕事内容や資格、役割に明確な違いがあります。
介護職員は利用者の生活を直接支える現場の力、
介護支援専門員はサービス全体の調整役として動いています。
両者が協力して初めて安心で質の高い介護サービスが実現するのです。
この違いを知ることは、介護の仕事を目指す方やご家族がサービス利用を考える際にも役立つ情報です。
これからも介護の現場で大切な役割を担う両者の違いを理解し、そのおかげで私たちの生活が支えられていることに感謝しながら見守っていきましょう。
「介護支援専門員」という言葉は堅苦しく聞こえますが、実はケアマネジャーの正式名称なんです。この人たちは単に資格が必要なだけじゃなく、現場での経験が豊富でないと受験資格すら得られません。だからこそ利用者に最適なケアプランを作ることができ、介護現場の“まとめ役”として機能しているんですよ。実は介護職員の実体験から得た知識を活かして仕事するため、現場をよく知っているのが大きな強みなんです。