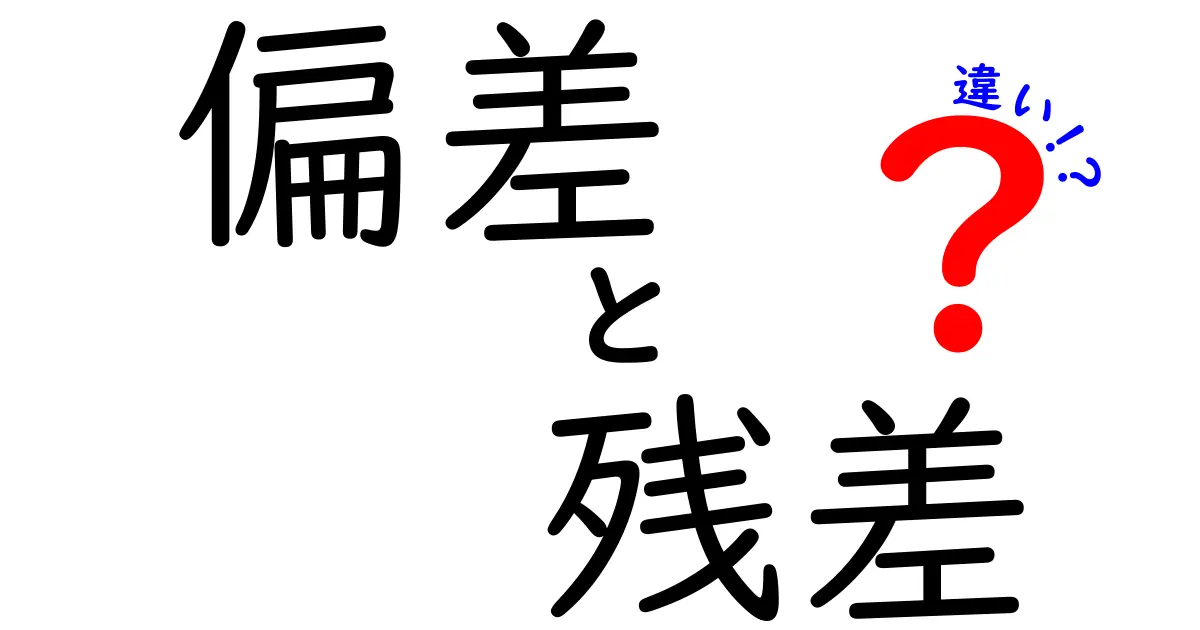

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:偏差・残差・違いの基本を整理する
長い学習の中で「偏差」「残差」「違い」という言葉はよく出てきますが、意味を誤解して使ってしまうことも多いです。ここでは中学生にも分かるように、3つの用語の基本を丁寧に整理します。
まず大事なのは「偏差」と「残差」が別のものだという点です。
偏差はデータ点と平均の差を表す値で、散らばりの程度やデータの偏り方を示す手がかりになります。平均そのものを基準にして、各データがどの位置にあるかを示すため、プラスかマイナスかの符号にも意味があります。数学の教科書では「データ点 - 平均」という計算式で表されます。これを蓄積すると、全体の分布の形が見え、偏差のばらつきから標準偏差や分散といった指標に発展していきます。
一方残差は「実測値 − 予測値」の差です。モデルや予測の精度を評価するために使われ、回帰分析では残差の分布を見て、適切なモデルかどうかを判断します。とくに回帰直線を引いて予測した値と実際の値の差が大きいときは、そのモデルがデータをうまく捉え切れていないサインです。残差はデータの個別の性質とモデルの限界を同時に示す、現場の“検査結果”のような役割を果たします。
そして違いは、2つ以上の概念や値の差分そのものを指す一般的な言葉です。日常の会話でも「この2つの方法の違いは何ですか」といった問いに使われますが、統計やデータ分析では、同じ作業の別の言い方や、比較の切り口を明確にするために使います。つまり、違いを正しく使うことで、比較の対象や意味合いを相手に伝えやすくなるのです。
偏差と残差の違いを実例で理解する
身近な例を使って、3つの語の違いを実感してみましょう。まず「偏差」について。学校の成績データを例に取ると、各生徒の点数と全体の平均点との差が偏差です。偏差値はこの偏差をある規則に沿って変換したものですが、本質は「個々の成績が平均からどれだけ外れているか」を示すことにあります。たとえば、テストである人の点数が78点、平均が65点なら、偏差は+13となり、その人が平均より上にいることを意味します。ここで注意したいのは、偏差自体には「正しい・間違い」の評価は含まれず、単に位置情報を与えるだけだという点です。次に「残差」の考え方。予測モデルとして直線を使う場合、実際の成績をこの直線が予測した点と比較して差を出します。実測が85点、直線の予測が80点だった場合、残差は+5となり、モデルの予測が少し低かったことを示します。残差はデータがどうモデルに適合しているかを示す鏡であり、残差がランダムに広がるほどモデルの良さが高いと考えられます。最後に「違い」の使い方。偏差と残差は同じデータに関する別の視点を与える異なる指標ですが、違いを意識して比較することで、データの性質やモデルの弱点をより深く理解できます。
以下の表は、3つの概念の違いを整理するのに役立つ基本的な比較です。
| 用語 | 意味 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 偏差 | データ点と平均の差を示す値 | データのばらつき・分布の理解 |
| 残差 | 観測値とモデルの予測値の差 | 回帰分析のモデル評価・改善 |
| 違い | 2つ以上の概念の差分そのもの | 比較の明確化・言語的整理 |





















