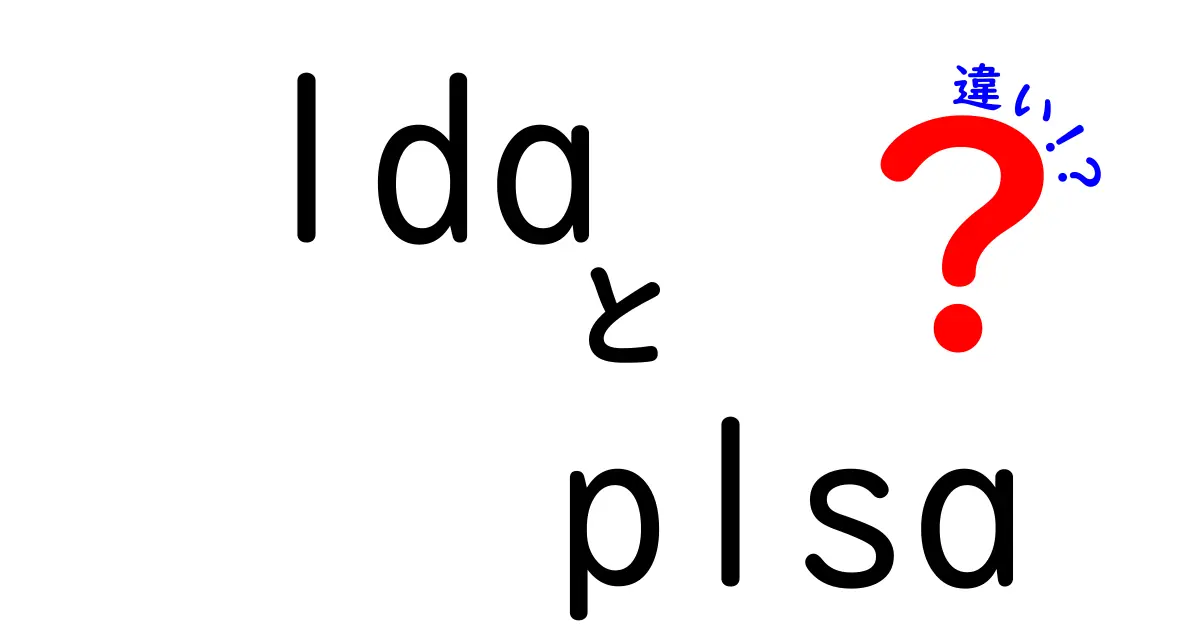

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
lda plsa 違いを理解するための基礎知識
ldaとplsaは、テキストデータから意味のあるトピックを見つけ出す代表的な手法です。LDAは Latent Dirichlet Allocation の略で、文書をいくつかのトピックの混合としてモデル化します。文書は事前に決められたトピックの組み合わせで生成されると仮定され、それぞれの文書がどの程度の割合でどのトピックを含むかを確率的に推定します。
PLSA は Probabilistic Latent Semantic Analysis の略で、文書ごとに独立したトピック混合を仮定します。つまり同じトピックが別の文書にもどの程度現れるかは文書ごとに決まるという発想です。ここで大きな違いが生まれます。LDA は文書ごとのトピック分布に Dirichlet と呼ばれる確率分布の priors を導入し、データが少ない文書や新しい文書でも安定して推定できるよう設計されています。PLSA はこのようなベイズ的な前提を取り入れていないため、学習データの範囲を超えた新しい文書へ適用するには適切な一般化が難しくなりがちです。
実務ではこの点が大きな分岐点となり、データ量が多く新規文書の利用が多い場合は LDA がよく使われます。また、推定手法の違いも結果に影響します。PLSA は主に最適化アルゴリズムで解を探しますが、LDA は変分推論やギブスサンプリングといったベイズ的な手法を使って潜在トピックを推定します。これらの違いは、学習時間、解の安定性、解釈のしやすさに直結します。
まとめると、LDA は新しい文書にも強く、ベイズ的前提で安定性を取りにいくのが特徴。PLSA はシンプルなモデル設計でデータ量が十分ある場合に強みを出しやすいが、未知の文書への一般化は苦手な場面が多い、というのが大筋です。
アルゴリズムの背後にある考え方の違い
LDAとPLSAの根本的な違いは、文書ごとのトピック分布の扱いと、未知の文書に対する一般化の考え方です。PLSA は文書ごとにトピック分布を別々に決める設計なので、同じトピックが別の文書でどの程度現れるかを直接的に共有しません。これに対して LDA は文書全体のトピック分布に確率的な前提を与え、未知の文書にも一般化できるようにするのが狙いです。Dirichlet priors がこの一般化を支えるコア要素になります。
このため、PLSAはデータ量が増えるとより自然に適合しますが、学習データの外へ出ると過剰適合の恐れが出てきます。LDAは事前分布のおかげで、少ないデータでも「何となくこういうトピックが混ざるはず」という感覚を保ちながら推定できることが多いのです。
推定方法の違いも重要です。PLSA はエポックごとにパラメータを更新する最適化法を使います。一方LDAは変分推論やギブスサンプリングといったベイズ的推定で、潜在トピックを確率的に探索します。これにより、LDAは不確実性を扱いやすく、出力の解釈にも影響します。
実務での使い分けと学習のポイント
実務でLDAとPLSAを選ぶときには、以下のポイントを押さえると判断がしやすくなります。まずデータ量と新規文書の扱いです。新しい文書を頻繁に追加する場面では LDA が向いています。次に解釈の安定性です。ベイズ的な前提のおかげで LDA の方が安定して解釈しやすい場合が多いです。反対に、データ量が非常に少なく、すぐに結果を出したい時は PL SA の方が実装がシンプルで手早く動くことがあります。さらに、ハイパーパラメータの設定も重要です。トピック数K、文書分布のα、語分布のβといった値を適切に調整することで、結果の意味づけが大きく変わります。
実装時の具体的な流れは次のとおりです。まず前処理としてテキストの正規化と分かち書きを行い、単語の出現頻度を整理します。次にトピック数を決めてモデルを学習します。学習後はトピックごとの語リストを解釈して意味づけを行い、文書ごとのトピック分布を確認します。モデルの評価にはコヒーレンスや再現性を使うと良いでしょう。最後に新しいデータに適用する際は、LDAのようなベイズ的推定を使って文書ごとのトピック分布を推定します。これにより、実務での活用の幅が広がります。
私と友人の部屋での雑談から生まれた小ネタです。友人が plsa は昔の手法だから今は使わないのかと聞いてきたので、私はこう説明しました。PLSA は文書ごとにトピックの混ざり方を個別に決めるだけなので、同じトピックが別の文書でどのくらい現れるかを共有して考える発想が弱いんです。対して LDA は文書全体のトピック分布に前提を置き、未知の文書にも適用しやすいようにするのが特徴。友人はそれを聞いて、データ量が増えたらLDAの方が安定して良い結果を出せるねと納得しました。二人は結局、データがたくさんある現場では LDA が強い、という結論に達しました。話はさらに進み、ハイパーパラメータの設定の話題へ。Kの数を増やすと意味の細かい分解ができるが解釈が難しくなる、逆に少なすぎると全体像がぼやける、という現象を実感したのです。結論はいつも同じ、道具選びは目的とデータ量次第ということ。





















