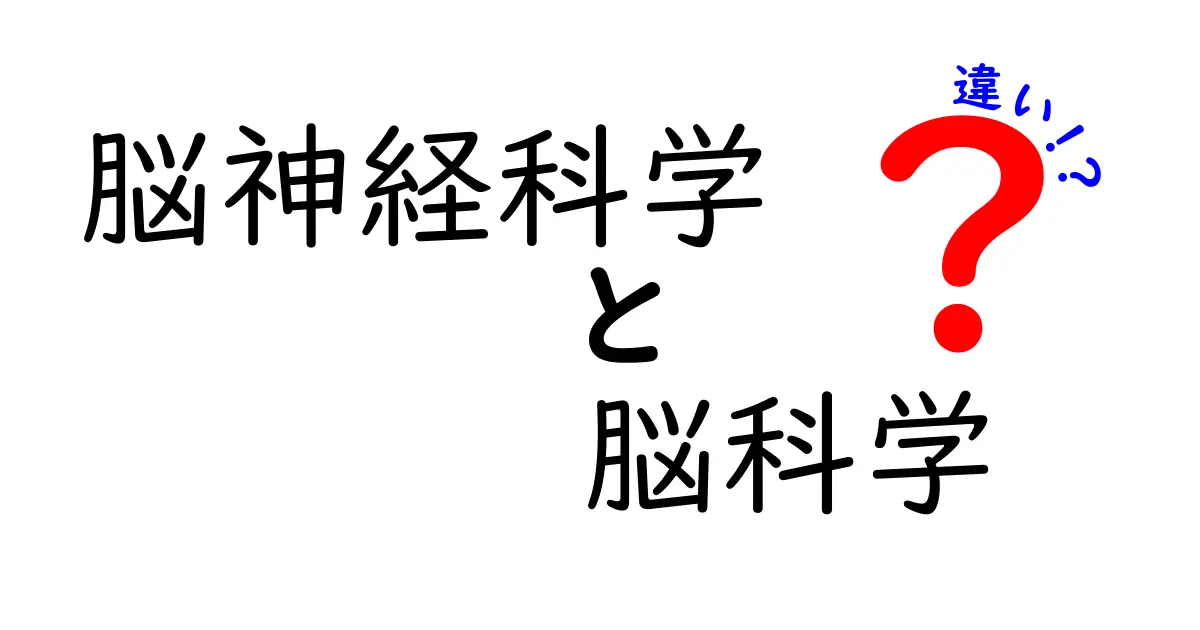

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
脳神経科学と脳科学の違いを知ろう:混乱を避ける基本ポイント
中学生にも分かるように、脳神経科学と脳科学の違いを丁寧に解説します。まず前提として、脳は私たちの頭の中にある大きな器官で、思ったことを感じたり動いたりする司令塔です。 ふだんの会話では「脳科学」という言葉がよく使われますが、授業や論文の現場では「脳神経科学」が好まれる場面が多いです。これには理由があり、脳神経科学は神経系のしくみを深く掘り下げる研究を指す専門用語だからです。
この2つの言葉は日常やニュース、学校の授業で混同されがちですが、学問の分野の広さと焦点の違いに着目すると区別が見えてきます。
脳神経科学は神経系のしくみや機能を細かく解き明かす学問で、神経細胞の働き、神経回路の結びつき、脳の活動がどう行動や感情に現れるかを研究します。
一方、脳科学はもう少し広い意味で使われることが多く、心理学や認知科学、人工知能の分野も含む場合があります。
つまり速報性の高いニュースでは「脳科学」という言葉が幅広く使われがちですが、研究室の話題では「脳神経科学」がしばしば専門的な分野名として用いられます。
この違いを覚えるコツは「対象の幅」と「手法の多さ」に注目することです。
この点を次の表で整理しておきましょう。
以下の表は、ニュースで見かけるときの混乱を解く助けになります。項目 脳神経科学 脳科学 対象 神経系の分子〜回路〜行動 脳を中心とした広い概念 手法 電気生理、イメージング、分子技術、動物実験、計算 複数分野の総称、学際的研究を含む 主な目的 神経のしくみを基本から解く 心・思考・行動の理解を幅広く追求 日常用語と学術用語のすみ分け
ただし、教学・報道の現場では両者が混同されることもよくあります。その場合は「対象が神経系のどの範囲を含むのか」を聞くか、文脈から判断します。小学生や中学生に説明するときは、脳の中にある「神経細胞」とそれらがつくる回路が、私たちの感じ方や動きにつながる、というイメージで伝えると伝わりやすいです。
このように、用語の使い分けを意識するだけで、話がぐんとすっきりします。
結論として、脳神経科学は神経系の深い機構を研究する専門分野、脳科学は脳を中心とした広い学問領域を指すことが多い、という点を覚えておくとよいでしょう。項目 脳神経科学 脳科学 対象 神経系の分子〜回路〜行動 脳を中心とした広い概念 手法 電気生理、イメージング、分子技術、動物実験、計算 複数分野の総称、学際的研究を含む 主な目的 神経のしくみを基本から解く 心・思考・動作の理解を幅広く追求
脳科学と脳神経科学の実務的な使い分けのコツ
実務では、論文を書くときやプレゼンをするとき、読み手が何を知りたいかを最初に決めると混乱を避けやすいです。
もし対象を「神経系の構造と機能のしくみ」として深掘りするなら脳神経科学、
「脳そのものと、それが生み出す心の働き全般」を説明する場合は脳科学という形で使い分けると、伝わり方がより正確になります。
また、ニュースやテレビでは“脳科学”と書かれていても、話の内容次第で実際には神経科学の話題であることが多いので、必要なら補足説明をつけると良いです。
学習を進めるときには、教科書の章題や研究チームの論文タイトルを手掛かりに、対象の幅と手法の広さを2つの視点で確認する癖をつけましょう。
こうした理解が深まれば、専門用語に惑わされず、脳の世界をより正確にイメージできるようになります。
要するに、脳神経科学は神経系の深い仕組みを研究する専門分野、脳科学は脳を中心とした広い学問領域を指すことが多い、という点をしっかり押さえることが大切です。
ねえ、今日は『脳神経科学と脳科学の違い』についてざっくり話してみよう。僕が最初に混乱したのは、ニュースの見出しだけを読んで“同じものかな?”と思ってしまうことだったよ。友だちと話していても、どちらの言葉を使えば正確なのか迷う場面がある。そんなとき先生は「対象の幅と研究手法の広さをまず考えるといい」と教えてくれた。
脳神経科学は神経系の分子の動きから回路の働き、さらには行動までを結びつけて理解する学問。具体的にはニューロンの信号伝達を測る電気生理、脳の活動を映すfMRI、細胞レベルの実験、動物モデルを使った研究など、様々な手法を組み合わせる。これに対して脳科学は、脳そのものを中心に、時には心理学や記憶、認知の研究も含む広い分野。ニュースの見出しでは“脳科学”とだけ出ることが多いけれど、詳しくは対象の深さとどんな方法で研究しているかを見れば分かる。つまり、脳神経科学は“神経系のしくみを深く追究する専門領域”、脳科学は“脳を軸にした広い学問領域”という使い分けが正しいのだ。
この違いを意識すると、授業ノートを書いたり友だちと話をするときに、話の内容を正しく伝えられるようになるはず。自分の理解が深まると、難しそうな論文や学術ニュースも、少しずつ読めるようになるよ。





















