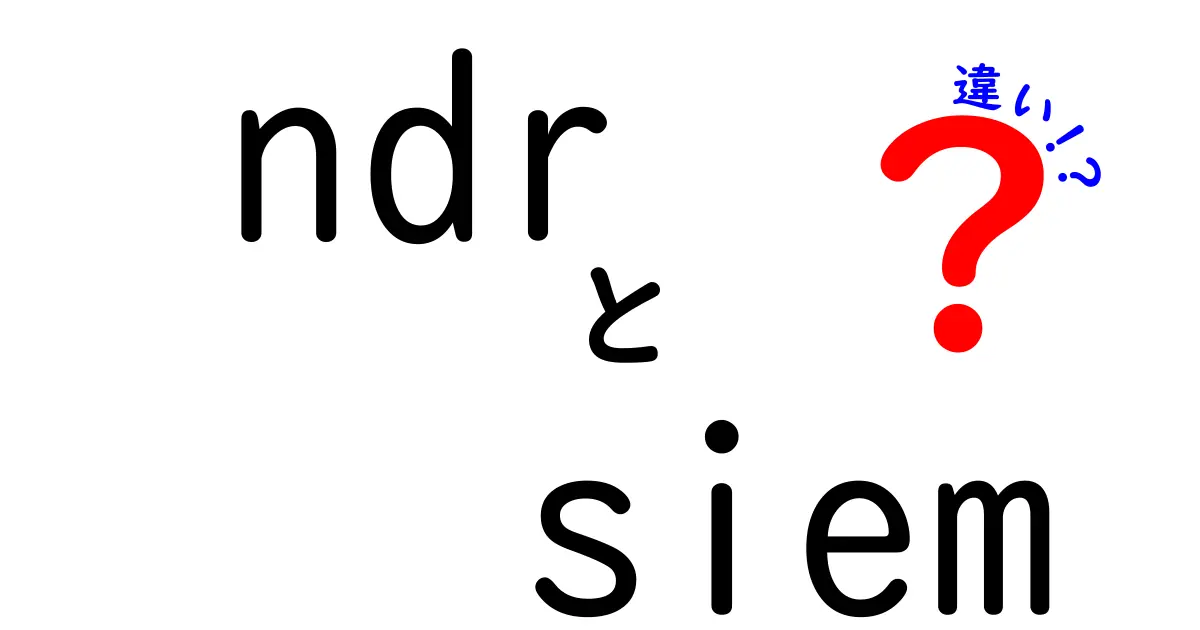

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:NDRとSIEMの違いをざっくり把握する
セキュリティ対策の現場では、よく耳にする用語の一つに「NDR」と「SIEM」があります。NDRはNetwork Detection and Responseの略で、名前のとおりネットワークの挙動を中心に監視・検知します。対してSIEMはSecurity Information and Event Managementの略で、各種機器やアプリケーションが出すログやイベント情報を集約して分析します。この二つは、似ているようで視点が異なり、使い分け方次第で防御の厚みが大きく変わります。
本記事では、2つのツールがどんな場面で有効か、どのように組み合わせるべきかを、現場の運用を想定しながら中学生でも理解できるようにわかりやすく解説します。
また、NDRとSIEMを混同してしまいがちな点にも触れ、両者の違いを明確化します。読み進めるうちに「自分の組織に最適な組み合わせはどれか」という具体像が見えてくるはずです。
NDRとSIEMの実務での使い分け
現場でNDRとSIEMをどう使い分けるかは、組織の規模や運用体制、法令要件など多くの要因で変わります。NDRはリアルタイム性とネットワークの挙動の可視化に強みがあります。侵入の初期段階や横展開の兆候を素早く検知し、即座に対応を開始できる点が魅力です。一方、SIEMは複数のデータソースを横断して相関分析を行い、事件の原因を特定したり長期的な傾向を把握したりする力が強いです。監査や法規制対応、過去の事例の再現など、長期的な視点が求められる場面で力を発揮します。
この二つを組み合わせると、現場は大きく動き出します。例えばNDRが「今起きていること」を知らせ、SIEMが「過去の関連イベントと現在の挙動を結びつけて原因を特定する」のような連携です。実際の運用では、データの入口を整理し、アラートの優先順位を決めるルールを作ることが大切です。データドリブンな運用を目指すなら、データ源の洗い出しと正規化、データ品質の管理を最初の課題として設定しましょう。
また、統合ダッシュボードを用意すれば、NDRのネットワーク視点とSIEMのイベント視点を一つの画面で俯瞰できます。これにより、セキュリティ担当者の意思決定が速くなり、対応の一貫性も高まります。NDRとSIEMを別々に走らせるのではなく、データの流れを意識した設計を心掛けることが成功の鍵です。
NDRの特徴と導入のメリット
NDRの最大の強みは、ネットワークの挙動をリアルタイムで可視化できる点です。従来のパターンベースの検知に加え、機械学習を用いた異常検知や、内部ネットワークの横展開の兆候を拾う能力があります。これにより、未知の脅威や内部不正の兆候を早期に捉えることが可能です。運用面では、24時間の監視体制と自動化されたアラートが組み合わさり、担当者の反応を迅速化します。
TLSなどの暗号化トラフィックの挙動も分析対象に含められるケースが多く、通信相手の新規性や異常なパターンを検知しやすいのも特徴です。さらに、内部セグメント間の通信を可視化できるケースが増えており、内部不正の早期検知や侵入時の横展開の特定が期待できます。
ただし、NDRの導入には時間がかかることがあります。学習データの準備、適切なしきい値の設定、ノイズとなるノンセキュリティの通信を除外するフィルタリングなど、導入初期の設計が重要です。短期的な効果だけでなく、中長期的な運用設計を意識して導入を進めるべきです。
SIEMの特徴と導入のメリット
SIEMは、エンドポイント、サーバ、クラウド、ネットワーク機器など、異なるデータソースからのイベントを統合して分析します。相関分析によって、単一のイベントだけでは分からない「なぜこうなったのか」という原因を追跡できる点が強みです。監査証跡の作成や法規制対応、長期的な攻撃傾向の把握にも適しています。ダッシュボードや検索機能を活用すれば、時系列での変化や関係性を視覚的に追跡でき、インシデント対応の迅速化につながります。
導入の際には、データ品質が鍵です。データが不揃いだと正確な分析が難しく、誤検知や見逃しのリスクが高まります。そのためデータ正規化、データカタログの整備、取り込み方の標準化が不可欠です。SIEMは“事件の連鎖を見つけるための証跡”を作る道具として強力であり、適切なルールと運用によって防御の厚みを大きく高められます。
比較表:NDRとSIEMの主な違い
以下の表は、NDRとSIEMの主な違いを要約したものです。
ねえ、NDRとSIEMって結局どう違うの?と聞かれたとき、僕ならこう答えるよ。NDRは“今この瞬間の動き”を追う高性能な警察官、SIEMは“過去の事件の全体像をつなぐ探偵”みたいな役割。ネットワークの中で何が普通で何が怪しいかを見分けるのがNDR、ログの断片をつなぎ合わせて原因と影響を特定するのがSIEM。だから一緒に使うと、いま起きていることと、その前後の関係まで見えるようになる。実務なら、まずデータ源の整理、次にアラートルールの現場適性を調整、最後にダッシュボードで一元管理。こうした設計が防御ラインを格段に強くするんだ。





















