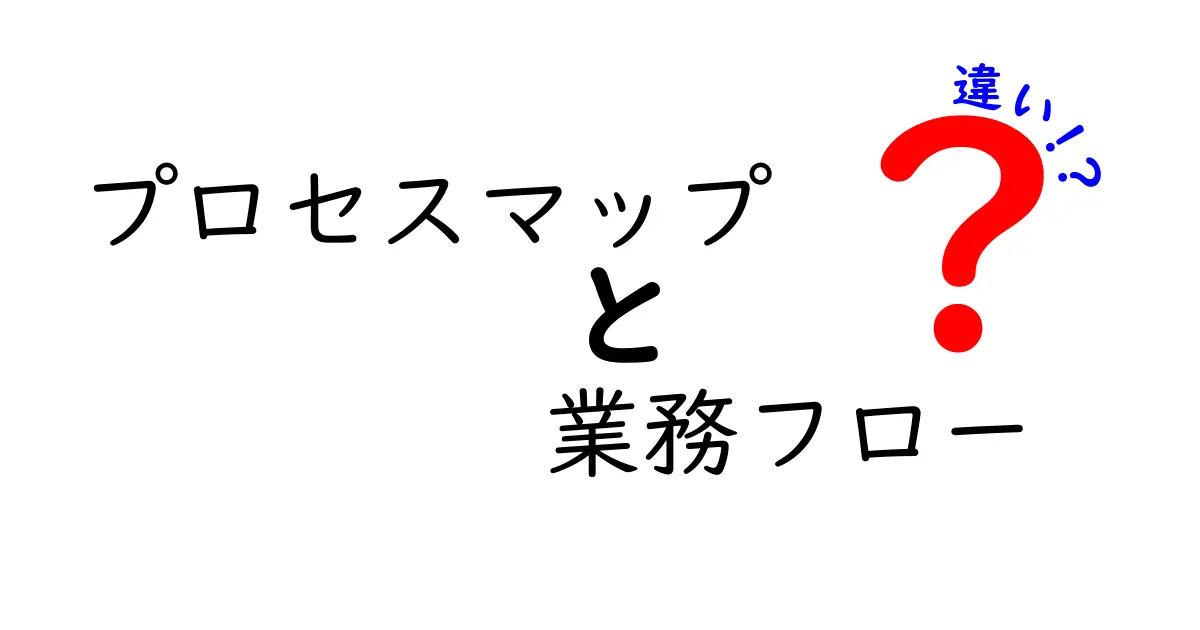

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
プロセスマップと業務フローの違いを理解するための基本と誤解を解く道標
ここではまずプロセスマップと業務フローの意味をそもそも分かりやすく整理します。どちらも「仕事の流れ」を表す道具ですが、使う人や目的が異なる点が混乱の原因になりがちです。まず前提として覚えておきたいのは、プロセスマップは横断的な視点で複数の部門や担当者の動きを結びつけ、全体の流れと責任の所在を一枚の図にまとめることを目的とすることが多いという点です。これに対して業務フローは特定の業務の「手順書のようなもの」や一連の作業の流れを指し、実務での手順を明確にすることに重点を置く傾向があります。
つまり、プロセスマップは“全体像を見える化する大きな地図”であり、業務フローは“個別の仕事の手順を示す道順”と例えると分かりやすいです。
この違いを理解すると、なぜ同じ言葉が混同されやすいのかが見えてきます。多くの現場では、改善の入口としてプロセスマップを作って全体像を共有し、個別の作業については業務フローで詳細を整理するという組み合わせが自然です。
次のポイントを押さえると、両者の使い分けがぐんと見えやすくなります。まず目的が違うこと、次に表現形式が変わること、さらにスコープと更新頻度の観点が異なることです。これらを理解するだけで、会議での誤解を減らし、改善案を的確に伝えられるようになります。
また実務での活用場面を見据えると、プロセスマップは経営層や横断部門の合意形成、リスクの洗い出し、標準化の推進に強力であり、業務フローは実作業の標準化・自動化、新人教育の手順共有、業務の検証・教育用資料として有効です。
この二つを混同せず、適切な場面で使い分けることで、業務の透明性と改善のスピードが両立します。
具体的な違いを表と例で整理する
ここからは具体的な違いを実務的な観点で整理します。目的としては、プロセスマップが「組織横断の流れの全体像を共有する」こと、業務フローが「個別作業の手順を明確化する」ことが多いです。
表現形式は、プロセスマップは多くの場合 swimlanes や BPMN 的な表現を取り入れて複数部門の関係を示すことが多く、業務フローは箇条書きや手順図、簡易なフローチャートなど“実務で再現性の高い形”が用いられます。
スコープはプロセスマップが企業全体や大きなプロセスの全体像を扱うのに対し、業務フローは特定の業務やタスクの範囲を厳密に限定します。
さらに更新頻度も異なり、プロセスマップは戦略的な見直しのタイミングで更新されることが多く、業務フローは日常の運用での修正に合わせて頻繁に更新されることがあります。
このような違いを理解することで、現場での混乱を抑え、目的に沿った資料作成が可能になります。
実務上の活用例として、顧客サービスの全体プロセスを示すプロセスマップを作ることで部門間のボトルネックを特定し、個別の処理手順を記した業務フローを整備することで新人教育の効率を上げることができます。
最後に、実務で迷いやすい点として「データの粒度」が挙げられます。プロセスマップは作成時に全体の粒度を揃え、業務フローは実作業の現実的な粒度に合わせることが重要です。
以上の点を押さえると、現場での誤解が減り、会議での説明がスムーズになり、改善案の検討が現実味を帯びて進みやすくなります。特に初期の整理段階では、プロセスマップを用いて部門間の責任と流れを共通認識として共有することが第一歩です。そのうえで、各業務の具体的な手順を業務フローとして落とし込むと、実務での適用性が高まり、教育・運用・自動化のいずれにも良い効果が出てきます。
実務で役立つ作成のコツ
作成時のコツとしては、まず関係者のヒアリングを丁寧に行い、開始と終了の「境界」を明確に設定すること、次にデータの粒度を揃えること、最後に一度「完成図」として上長や現場の担当者にレビューしてもらい、改善案を取り入れることです。
ツール選びも重要で、紙の図だけでなく、デジタルツールを用いると更新が楽になり、検索性も向上します。
特に新しい人が現場で混乱しないよう、教育用の業務フローとプロセスマップをセットで提供すると理解が早く進みます。最終的には、プロセスマップと業務フローを組み合わせた「ハイブリッド型の資料」が最も現場に馴染みやすく、改善の循環も生まれやすくなります。
今日は<プロセスマップ>と<業務フロー>の違いを雑談風に掘り下げてみました。私たちが学校の行事運営を例にすると、全体の流れを地図に描くのがプロセスマップ、各係の具体的な役割分担と手順を細かく示すのが業務フローです。最近は部活の新歓イベントを例にして考えると、プロセスマップは「新入生の受け入れプロセス全体像」を示し、業務フローは「入門ガイドの配布作業の手順」を詳しく書くといった感じですね。つまり、全体像を把握する力と、日常の作業を正しく進める力の両方を育てるツールです。だからこそ、適切な場面で使い分ける練習を日常的にしておくと、将来の仕事でも役立ちます。難しく感じても、まずは「全体像と個別手順の違い」を頭の片隅に置くだけでOKです。





















