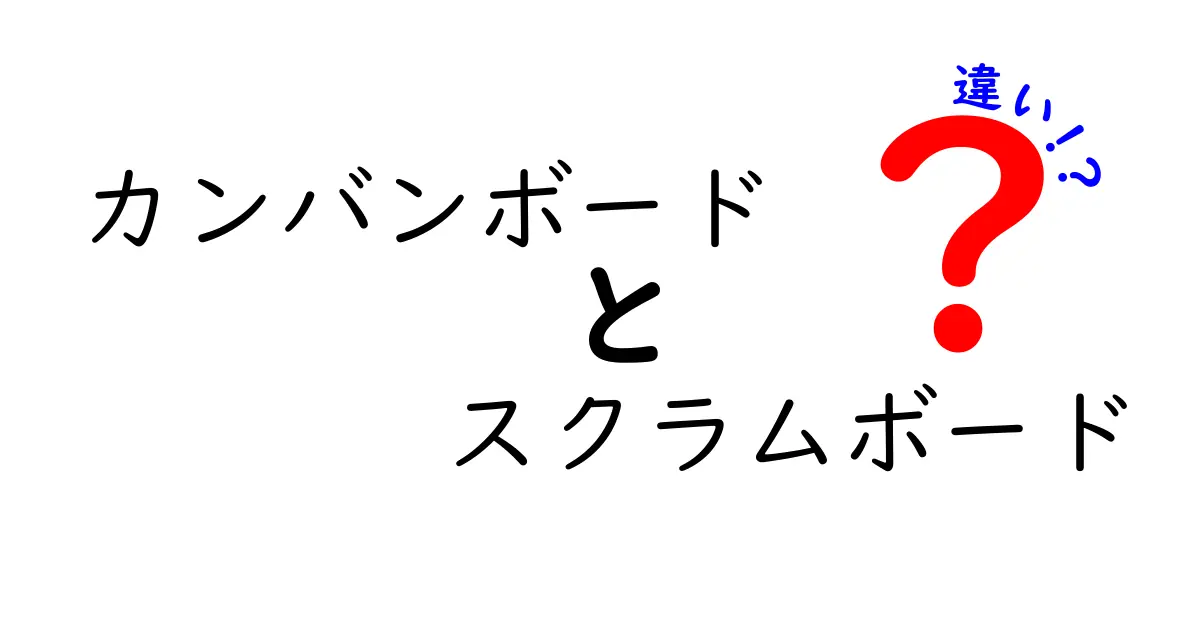

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
カンバンボードとスクラムボードの基本を理解する
カンバンボードとスクラムボードは、作業を「見える化」して、チームの作業状況を把握するための道具です。まずはそれぞれの基本概念を押さえましょう。
カンバンボードは、元々製造業で生まれた考え方で、作業を「これからやること」「現在進行中」「完了済み」などの列(カラム)に分け、カードには作業の内容を記入します。
このボードは、作業がどのくらいの速さで動いているか、どこで滞っているかを一目で見られるようにするのが目的です。
重要なのは、固定されたスプリントなしで、継続的な流れを作る点、そしてWIPリミットを必要に応じて設定する点です。
対してスクラムボードは、スクラムという開発手法の一部で、スプリントとバックログと呼ばれる時間枠と優先順位の管理を組み合わせて使います。
スクラムボードは、スプリントごとに整理された「何を完了させるか」という目標を可視化します。
通常は「To Do」「In Progress」「Done」などの列を使い、スプリントバックログと定義の完了(Definition of Done)を基準にして進めます。
この違いを理解することは、プロジェクトの性質にあわせて道具を選ぶ第一歩です。
実務での使い分けと具体的な例
現場では、2つのボードをどう使い分けるかが大事です。
「継続的な改善と安定した流れを重視するならカンバン、定期的な成果物と短期間の計画を重視するならスクラム」というのが基本的な指針です。
カンバンは、リードタイム(仕事を開始して完了までの時間)を短縮するのに向いています。新しい機能の追加が頻繁で、要件が流動的な場合、WIPリミットを設定してボトルネックを解消します。実務では、顧客の要望が絶えず入ってくる場面や、運用の改善タスクを同時に進めたい場合に有効です。
スクラムは、明確な期間(通常は2週間や1か月)を設け、その期間の成果物をきっちり仕上げる力強さがあります。
新機能のリリースサイクルが規則的で、優先度がはっきりしている場合に適しています。
ただし、現場ではこの2つを組み合わせて使う「Scrumban」のような手法も現実的です。例えば、日々の作業はカンバンボードで管理し、スプリント計画のための大枠だけはスクラムボードで追跡するといった運用です。
以下の表は、初心者にもわかりやすい比較です。
このように、使い分けのコツは「作業の性質とリズム」を理解することです。小さな改善を積み重ねることが長期的な成功につながります。
最近、私がカンバンボードを使い始めた話の続きです。3つのカラムに分けて、未着手・作業中・完了のカードを動かすだけで、作業の流れが見える化され、遅れの原因をすぐ特定できました。友人と話すと、誰が何をやっているかが日々のミーティングなしでも把握でき、会議の回数が減りました。カンバンボードの良さは、視覚に訴える力です。





















