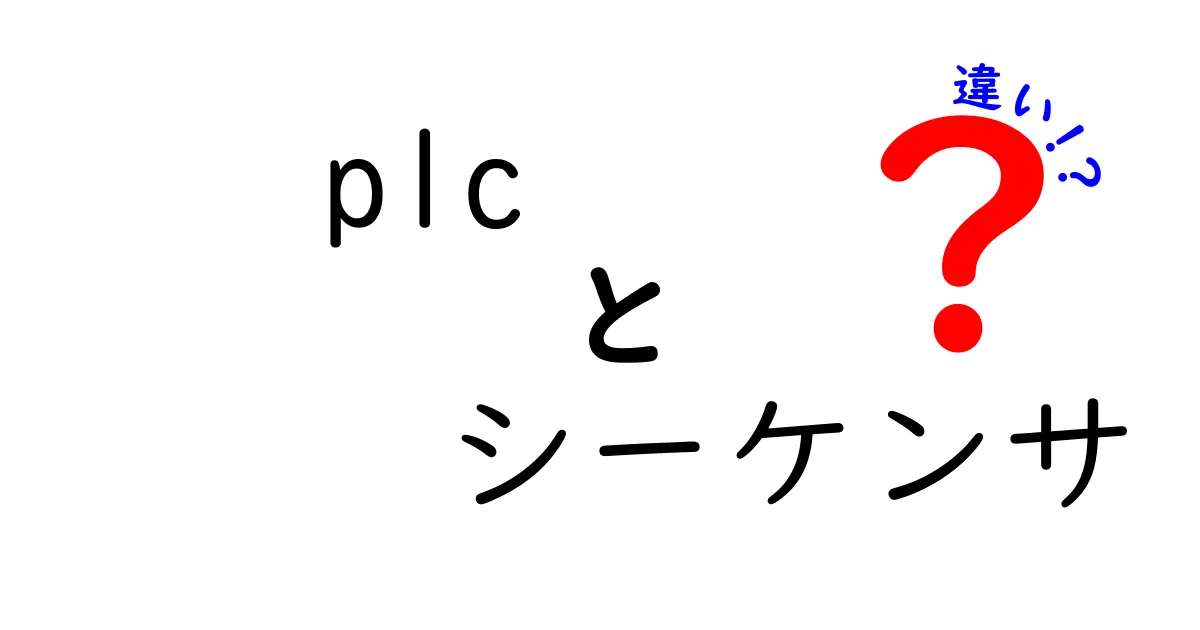

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
PLCとシーケンサの基本的な役割の違いを知ろう
プログラミングや自動化の現場でよく耳にする用語のひとつに PLC とシーケンサがあります。PLCは現在の工場や設備の脳に近い存在として広く使われていますが、シーケンサは昔からの制御機構を指す言葉で、現在の機器にもその名残が残っています。まずはこの二つの役割を分けて考えることが大切です。
PLC は多くの場合、複数の入力や出力を組み合わせて複雑な動作を実現するためのプログラムを実行します。機械の開始、停止、順序の制御、安全機能の実装などをひとつの装置で担います。
一方でシーケンサは、元々はリレーや接点を組み合わせて順序を実現する仕組みの総称として使われてきました。シーケンサの本質は「時間や順序の制御」であり、現代の PLC もこの考え方を取り込みつつ、より柔軟で複雑な条件分岐を扱えるようになっています。
この違いを理解すると、現場での設計時に「どの機器を使えば良いか」「どう組み合わせれば効率よく動かせるか」が見えてきます。
つまり PLC は現代の制御プラットフォームとしての総合力、シーケンサは基本的な順序制御の思想を担っている、という捉え方が分かりやすいです。
用語の定義をすり合わせよう
まずは双方の定義を日常の言葉に置き換えて整理します。PLC は「プログラム可能な論理回路を現代的な形で実装する装置」です。ここには「入力を読み取り、条件を判断し、出力を動かす」という流れが含まれます。シーケンサは「時間の経過や順序を意識して、どの順番で出力を変えるか」という設計思想を指します。重要な点は、両者の目的は同じく“機械を動かすこと”ですが、実装の自由度と設計の視点が異なるということです。プログラミング言語や開発環境が異なる場合でも、基本的な考え方はつながっています。
現場で混同しやすいポイントとして、「制御の粒度」と「拡張性」をどう捉えるかがあります。粒度が細かいほど、細かな条件分岐が増え、作業の自由度は上がりますが、メンテナンス性は難しくなることもあります。逆に粒度を大きくするとシンプルになりますが、細かな制御が難しくなることがあります。
現場での使い分けと実例
現場では、まず「何を自動化したいのか」「どの程度の信頼性と拡張性が必要か」を確認します。新規の小規模設備ならPLC を軸に据え、後から追加機能を増やす設計が現実的です。
一方で、昔からある機械を改修する場合には、シーケンサの発想を取り入れて既存回路を読み解くことが役立つ場面があります。具体的には、動作の順序を整理する際にシーケンス図や順序表を作成してから、PLC のプログラムに落とし込む方法が効果的です。
また安全機能や非常停止などの重要なポイントは、どちらの機器を使う場合も必須の設計要素として最初に検討します。ここをおろそかにすると事故や機械トラブルの原因になります。
実務では「どの入力がどの出力につながるのか」「どんな条件で動作を変えるのか」を、現場の人と共に整理することが成功の鍵です。これにより、後の保守や教育も楽になります。
比較表とポイント整理
以下の表は、PLC とシーケンサの特徴を分かりやすく比較したものです。
なお、実務では機器の組み合わせ方やメーカーの仕様によって差が出ることがありますので、実際の機器のマニュアルを確認しながら設計してください。
この記事の要点は、使い方の自由度と現場での適用範囲をどうバランスさせるかです。
新しい設備を作るときはPLC を軸にして、既存機を活かすときはシーケンスの発想を活用して設計を進めると良いでしょう。
理解を深めるためには、実際の現場の動作を観察し、入力と出力の関係を自分の言葉で整理してみるのが一番です。
学習を続けると、現場での意思決定も早くなり、トラブル時の対処もスムーズになります。
放課後、友達と工場の話をしていたときのことです。 PLC とシーケンサを混同している人が多くて、僕はこう説明してみました。 PLC は機械全体の“頭脳”みたいな役割を持っていて、どんな動きをどうやって実現するかをプログラムで決めます。一方でシーケンサは“順序の設計図”のようなもの。動作の順番を決める発想は昔からあり、今の PLC でもその考え方が生きています。だから新しい設備を作るなら PLC を中心に、古い機械の動作を読み解くときはシーケンスの考え方を用いると理解が進みます。最終的には、両者の良いところを組み合わせて使うのが現場のコツだと感じました。
前の記事: « 国際出願と外国出願の違いを徹底解説|中学生にもわかる実務ポイント





















