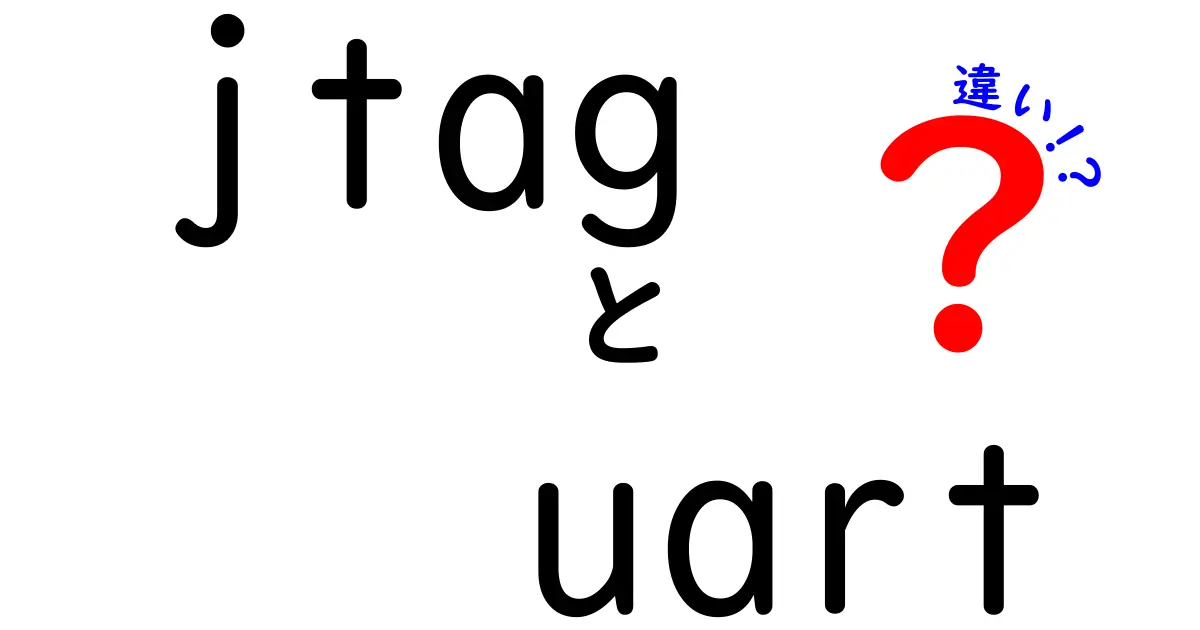

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
JTAGとUARTの違いを理解するための総合ガイド
JTAGと UART は、電子機器を動かすための道具箱のような存在です。
プロジェクトを進めるとき、どちらを使うべきか迷う場面は多く、初心者には難しく感じられがちです。本記事では、初心者の方にも分かりやすい言葉で両者の役割を整理し、実務での使い分けのコツを3つのポイントに絞って解説します。
まず前提として、JTAGはデバッグとプログラミングを主目的とした高機能なインタフェースであり、UARTはシリアル通信を実現する基本的な手段です。これらは同じ電子機器の世界にあるものですが、用途・接続方法・速度・信頼性といった観点で大きく異なります。
通常は、ボードの開発段階やファームウェアの書き込み、境界をまたぐ検証にはJTAGが活躍します。一方、現場の組み込み機器や通信モジュール間のデータ転送にはUARTが使われることが多く、日常的なログ出力にも適しています。
この記事を読み進めると、なぜJTAGが「開発者の道具」、UARTが「現場の会話道具」と呼ばれるのか、感覚的にも理解できるはずです。
JTAGとは何か
JTAGはTest Access Port/Boundary-Scanの略称で、デバイス内部の状態を外部から直接検証・操作できる仕組みです。
基本的にはTCK、TMS、TDI、TDOの4本の信号線が中心となり、場合によってはTRSTなどの追加線が使われます。
この仕組みの最大の特徴は、境界スキャンと呼ばれる検査機能によってチップの内部配線や論理の動作を外部のツールで検証できる点です。
開発現場では、ファームウェアの書き込み、CPUコアのステップ実行、メモリの読出しといった作業を行う際にJTAGが強力な味方になります。
JTAGは複数のデバイスを同時にデバッグすることも可能で、複雑な組み込みシステムの検証に最適化された設計となっています。
UARTとは何か
UARTはUniversal Asynchronous Receiver/Transmitterの略で、非同期のシリアル通信を実現する基本的な手段です。
「非同期」というのは、送信側と受信側が同じ時計を共有しなくてもデータを伝えられることを意味します。TXとRXの2本の線(時にはGNDを含む追加線)を使い、ボーレート、データビット数、パリティ、ストップビットなどの設定でデータをやりとりします。
UARTはシンプルで低コスト、ログ出力やデバッグの定番として広く使われます。ボードに標準搭載されていることが多く、パソコンや他のデバイスとの接続も容易です。ただし、ノイズに弱い点と、複数デバイス間の同時接続には工夫が必要なことがあるため、現場では適切なケーブル配線とノイズ対策が欠かせません。
速度はJTAGより遅いことが一般的ですが、実務の多くの場面では十分な性能を持ちます。
違いのポイントと実務での使い分け
ここでは、現場で迷わず使い分けができるよう、3つのポイントを整理します。
ポイント1: 目的の違いを最初に押さえましょう。デバッグ・プログラミングを主眼にするならJTAG、機器間のデータ伝送やログ取得が目的ならUARTが適しています。
ポイント2: 接続と機材を考えると、JTAGは複数線を使うケースが多く、専用のプログラマやデバッグツールが必要です。一方UARTは多くのボードに標準搭載され、ケーブルも安価です。
ポイント3: 安定性と速度は現場の要求次第です。高速なデバッグが必要ならJTAGを選び、日常の運用やモニタリングにはUARTの安定性とシンプルさが強みになります。
次に、実務での使い分けを具体的なケースで見てみましょう。
組み込みボードのファームウェアを書き換える作業はJTAGが適しており、境界スキャンを使って内部配線の検査を併用すると品質が上がります。
システムの起動ログを取りたい場合や、遠隔地の装置と簡易デバッグをしたい場合はUARTが最適です。
ただし、UARTのボーレートやパリティ設定、フロー制御の有無といった微妙な違いが、データ取りこぼしの原因になることもあるため、設定は丁寧に行いましょう。
このように、使い分けのコツは「目的・接続・速度・安定性」を軸に判断することです。
現場のニーズに合わせて、JTAGとUARTを組み合わせて使うケースも多く、複数のツールを持っておくと柔軟に対応できます。
最終的には、あなたのプロジェクトの性質と、デバッグの難易度、納期に応じて最適な選択をすることが重要です。
ある日の部活後の雑談。友達にJTAGとUARTの違いを話していたら、私の話が徐々に熱を帯びてきて、結局「JTAGは工房の道具箱、UARTは会話の道具」という結論に落ち着きました。JTAGは内部状態に直接アクセスできる強力な手段で、ファームウェアの開発・デバッグには必須です。一方UARTは機器同士のやり取りの基本形で、ログの取得や簡易デバッグにぴったり。似て非なるこの2つを、使い分けのルールとして覚えておくと、次のプロジェクトの準備が一気に楽になります。





















