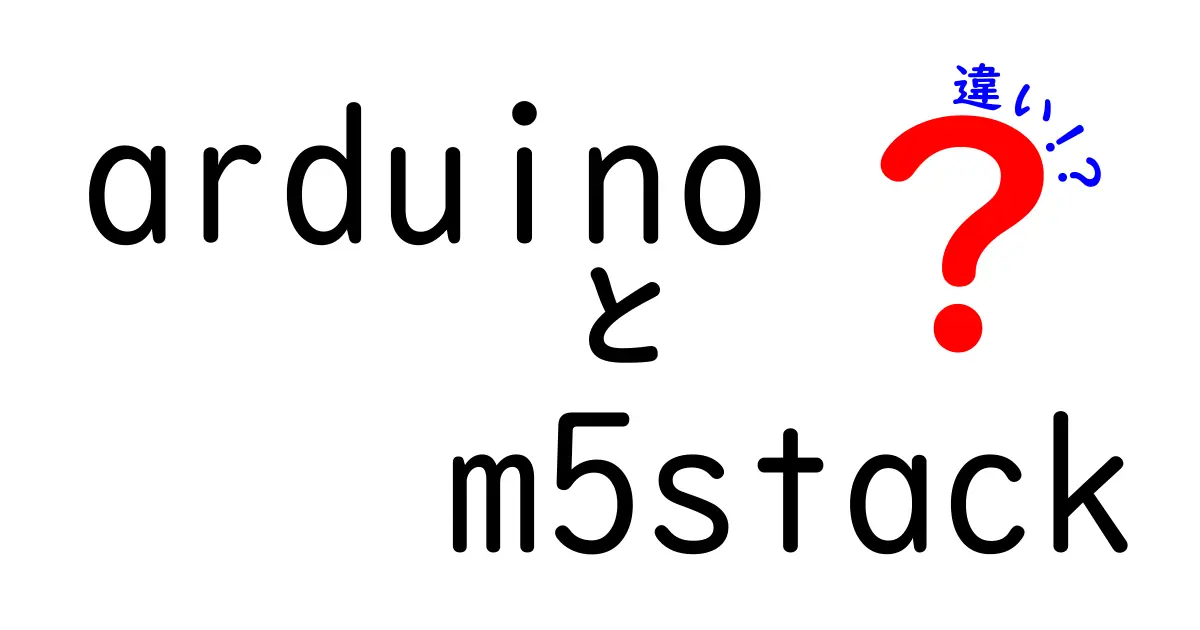

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ArduinoとM5Stackの違いを徹底解説
Arduinoはオープンソースのハードウェアプラットフォームであり、たくさんのボードと拡張部品が揃っています。主に教育現場や趣味の工作で使われ、初心者にも比較的優しい設計です。プログラムの書き方はC/C++ベースで、「動くかどうか」を最優先に考えた設計思想が特徴です。組み立ては自分で部品を選び、回路を作り、配線を引く必要がありますが、部品が安価なため試行錯誤を繰り返しやすいのが魅力です。
ここではArduinoの基本的な考え方と、どんな場面で向くのかを丁寧に見ていきます。
M5StackはESP32をコアにした“箱入りのIoTボード”です。内蔵ディスプレイや電源、センサー群を本体に備え、すぐに動かせる点が大きな利点です。Arduino IDEやPlatformIOなどの環境を使ってプログラムを組むことができますし、M5Stack独自のUIFlowというビジュアル開発環境も用意されています。
「すぐに動く」「配線を最小限にする」という設計思想が、学校の課題やイベントでのデモ作成を助けます。
両者の違いを要約すると、Arduinoは自由度が高く部品を自分で組み立てる「組み立ての喜び」が強い一方、M5Stackはすぐに使える統合ソリューションとしての強みがあります。教育では両方を併用するのが効果的です。例えば、基礎の回路と電子部品の扱いを学ぶ段階ではArduino、完成版のデモやIoTの実証実験にはM5Stackを使うと効率が良くなります。
技術スペックと使い方の違い
まずCPUとメモリの話から。Arduinoの代表的なボードはATmega328P系で動作周波数が16MHz前後、RAMは数キロバイト程度です。対してM5Stackの芯はESP32で32-bit、速度は約240MHz級、RAMは数百キロバイトから数MB程度の幅があります。これにより、複雑な計算やネットワーク通信、同時処理の扱いが大きく違います。
この差は実際の用途に直結します。
使い方の面では、Arduinoは主に「コードを書いて回路を組む」スタイルが基本です。Arduino IDEやPlatformIOを使ってボードに直接プログラムを書き込み、シンプルな回路とセンサーの組み合わせから始めやすいのが特徴です。対してM5Stackは「環境がすでに整っている」点が魅力で、UIFlowのようなビジュアル開発ツールを活用すれば初心者でも直感的に動かせます。もちろんC/C++での開発にも対応しており、柔軟性を捨てずに使えるのが強みです。
ディスプレイ、電源、センサー、通信機能の組み合わせも大きな差です。Arduinoの多くのボードは、外部ディスプレイやバッテリーパック、通信モジュールを自分で追加していきます。一方M5Stackは本体に2インチ程度のカラーLCD、内蔵バッテリー、カメラやセンサーが組み込まれているモデルもあり、外部部品を最小限に抑えてデモを作るのに向いています。
このような差を理解すると、初めてのプロジェクトで何を選ぶべきかが見えやすくなります。
このように要点をおさえるとどちらを選ぶかの判断がつきやすくなります。実際の開発では、初期学習にはArduinoを使い、デプロイやデモにはM5Stackを併用するのが効率的です。
この表を見れば、どちらを選ぶべきかの判断材料がまとまります。教育現場では両方を使い分けるのが効果的であり、初学者にはまずArduinoで基本を身につけ、そのうえでM5Stackを使って実務的なデモを作ると学習効果が高まります。
今日はM5Stackの話題を雑談風に深掘りします。M5Stackは箱入りのIoTボードのような存在で、ディスプレイや電源、センサーが本体に詰まっています。Arduinoと同じくプログラムで動くけれど、初期設定が少なく、すぐに動かせる点が魅力です。学校の課題でIoTデモを作るとき、配線の迷いが減り、発表のクオリティも上がることが多いです。設計思想の違いを知っておくと、次に作るときの選択肢がはっきりします。
次の記事: UARTとUSBの違いを解説!中学生にもわかる実践ガイド »





















