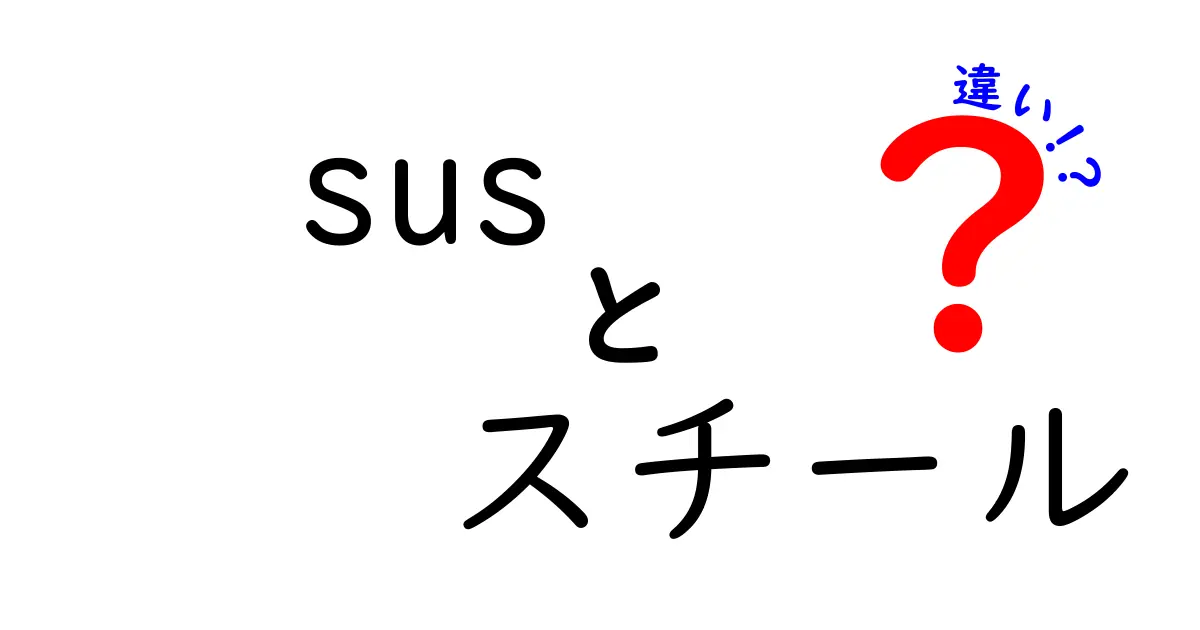

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
susとスチールの違いを理解する基本
金属の世界には似たような言葉が多く混ざっていて、初心者には少し混乱します。特に日本では「SUS」や「スチール」という言葉を同じ文脈で見かけることがあり、何が違うのか迷うことがあります。ここでは、中学生にも分かるように、SUSとは何か、スチールとは何か、そして両者の違いを実生活の例とともに丁寧に解説します。まず前提として知っておきたいのは、鉄は主に「鉄」として存在し、加工の仕方や含まれる他の成分によって性質が大きく変わるという点です。SUSはこの鉄を加工して、錆びに強く、手入れが楽な形にした材料の総称で、日本の規格で呼び方が決まっています。一方、スチールという言葉はとても広い意味を持ち、炭素を多く含む鉄を中心とした材料全般を指すことが多いです。私たちが日常で触れる多くの金属部品や刃物、建材、工具などは、SUSかスチールか、あるいはその両方の発展形に近い材料です。
このセクションの要点は三つです。第一に“SUS”は主にステンレス鋼を指す日本の表記で、表面が酸化されにくく、錆びにくい特性を持つ点です。第二に“スチール”は炭素鋼を中心に、強度や硬さ、加工性を高めるためにさまざまな合金で作られるという点です。第三に、価格・耐食性・加工難易度は材料ごとに大きく異なるため、用途に応じて使い分けることが大切です。これらの違いを知ると、部品選びがぐっと楽になり、作業効率も上がります。
さらに重要なのは、同じ表記でもブランドや規格、製造工程によって特徴が変わることです。例えばSUS304とSUS316では耐食性や耐熱性に差がありますし、炭素鋼と合金鋼の間にも強度や粘り気の違いが生まれます。日常の買い物で「SUSなのに錆が出た」「鋼なのに錆びない」という混乱を避けるには、具体的なグレード番号を確認することが最も確実です。
このように、SUSとスチールの違いを正しく理解するには、成分・性質・用途・表記の点をしっかり押さえることが大切です。今後の記事では、それぞれのグレードの特徴をさらに詳しく見ていき、どう選ぶべきかの実用的なポイントも紹介します。
SUSとは何か?
SUSとは日本の規格で用いられる「ステンレス鋼」の略称です。SUSは英語の“Stainless Steel”を表す日本語の略称で、主に錆びにくい性質を目的に選ばれる材料です。代表的なグレードにはSUS304やSUS316があり、それぞれにクロムやニッケルの含有量が異なります。クロムの存在により表面に不動態皮膜が形成され、外部の酸化を防ぐ仕組みが働きます。
この性質が強力な耐食性につながり、台所用品、医療機器、化学設備、建築物の外装部材など、長期間の使用が想定される場面で広く使われます。
またSUSにはいくつかの結晶構造があり、代表的なものはオーステナイト系(304/316など)です。この系は磁性を持ちにくく、加工性が良く、熱処理後も粘り強い特性を保つことが特徴です。逆にフェリティック系やマロブデンティック系は磁性を帯びることが多く、用途が限定される場合があります。
さらに重要なのは、「SUS」はあくまで表記の一つで、実際には同じグレード番号でも製造元や熱処理、仕上げ方法によって微妙に性質が変わることです。つまり、SUS304でも表面処理が異なれば耐食性や見た目が変わることがあります。グレード番号を確認するときは、用途と環境(室内/屋外、温度、薬品の有無など)を考慮して選ぶのがコツです。
このように、SUSは「錆びにくさと加工のしやすさを両立させた stainless steel の総称」であり、SUSが示す性質は dependent on grade and processing で決まる点が理解の要点です。
スチール(鋼)とは?
スチールとは鉄を基本とした材料全般を指す広い言葉です。鉄に炭素を適量加えることで硬さや強度を調整します。さらにニッケル・クロム・モリブデンなどの添加によって、耐久性や耐熱性、靭性を高めることができます。炭素含有量の違いによって、鋼は「炭素鋼」「合金鋼」「工具鋼」などに分類されます。炭素鋼はコストが低く、加工性が良い一方、耐食性はSUSほど高くありません。合金鋼は特定の性能(硬度、耐摩耗性、耐熱性)を狙って添加元素を増やします。
日常でよく目にするスチール製品には、建設用の梁や鉄骨、工具、車の部品、家電の筐体など、幅広い用途があります。これらは環境に応じて錆びやすいこともあり、外部で使われる場合には防錆処理やメンテナンスが欠かせません。
加工の面では、鋼は鋳造・鍛造・圧延・焼戻しなど、さまざまな加工法に対応します。熱処理によって内部組織を変え、硬さと靭性のバランスを作り出すのが特徴です。コストと性能のバランスを取るため、用途に合わせて適切な鋼種を選ぶことが重要です。
まとめると、スチールは「鉄を基本に、炭素や他の元素を組み合わせて作る幅広い材料群」であり、SUSのような高耐食性を必須としない場面でよく使われます。用途と環境に応じた設計判断が大切です。
見分け方と用途の選び方
用途に応じた材料選択の基本ルールを覚えておくと、現場での判断が楽になります。錆びを避けたい場所にはSUSが適しています。内装・キッチン流し場・医療機器など、湿度や薬品にさらされる環境ではSUSを選ぶと長寿命になります。一方、耐摩耗性や高い機械強度が求められる部品、コストを抑えたい建設部材にはスチールが適しています。
選定のポイントをまとめると、次のようになります。第一に耐腐食性とメンテナンス頻度、第二に加工性と製造コスト、第三に使用環境(湿気・薬品・温度)と長期耐久性。第四に重量と強度のバランスです。第五に表記のグレード番号の確認。これらを総合的に判断することで、実用性の高い選択ができます。
最後に、実務で迷わないためのコツとしては、具体的なグレード番号を事前に決めておくことです。SUS304なのか316なのか、スチールならば炭素鋼か合金鋼か、そして表面処理の有無はどうか、などを決めておくと、後のやり取りがスムーズになります。
この章では、材料の基本的な違いと実践的な選び方をまとめました。次の章では、表にまとめた具体的な特徴を、用途別の選択シナリオとともにさらに詳しく解説します。
友達とカフェでの雑談中の会話です。『SUSとスチール、どっちを選ぶべきか悩むんだ』と尋ねられたら、私はこう答えます。『SUSは錆びにくい、つまり長持ちするってこと。水回りの用品とか薬品の近くにはSUSが適している。一方で、コストを抑えたい場合や高い耐摩耗性が必要ない部品にはスチールが良い場面が多い。結局は環境と用途次第。グレード番号を見れば、耐食性や強度の目安がわかるから、製品の表記をよく確かめることが大切だよ』のようなニュアンスです。要は、用途とコストのバランスをどう取りにいくか、が決め手になります。





















