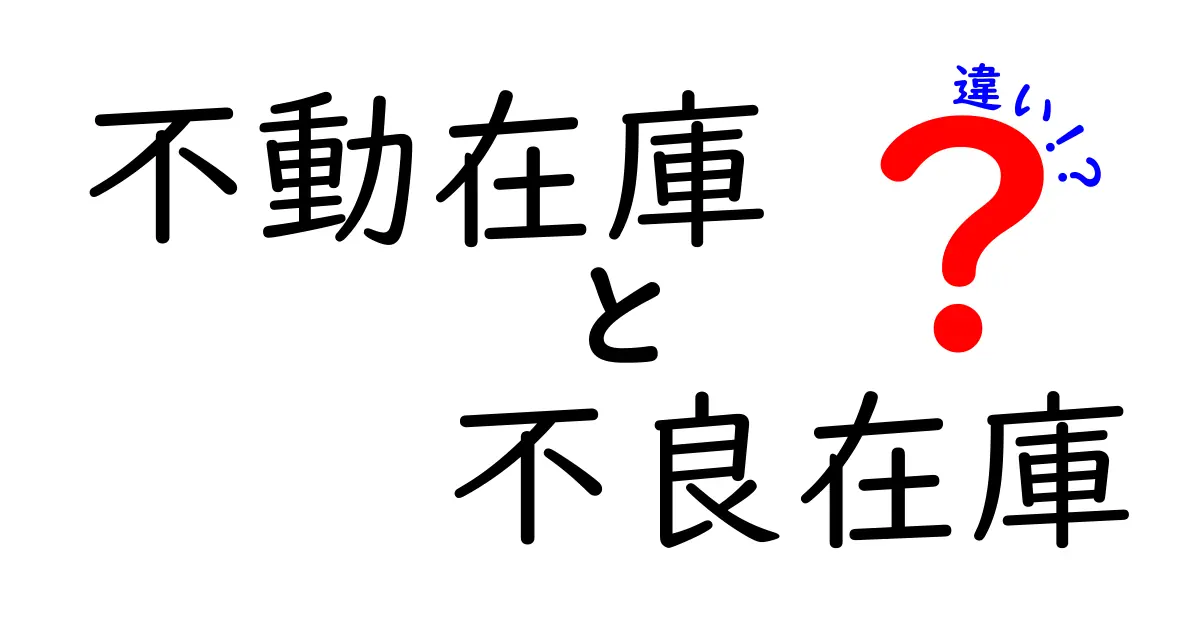

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
不動在庫と不良在庫の基本を押さえる
在庫は店の資産でありお金の素です。しかし同じ在庫でも「動かない在庫」と「使えなくなった在庫」は意味が違います。ここではまず不動在庫と不良在庫の二つを分けて考えます。
不動在庫とは、時間がたっても売れないまま棚で眠っている商品を指します。販売回転日数が長く、季節性の影響を受けつつも回転が戻らない状態を意味します。長く在庫として持つと保管コストがかさみ、資金の回収が遅れます。
一方不良在庫は品質に問題があり市場に出せない商品です。製造上の欠陥や傷み、賞味期限切れ、包装の破損などが原因で販売に適さなくなります。発生すると返品や廃棄のコストが増え、ブランドの信頼にも影響します。
この二つを混同せず正しく区別して管理することが、在庫の健全性を保つ第一歩です。これから具体的な見分け方と対策を見ていきましょう。
まず大事な考え方は三つです。動きの有無、品質の状態、そしてコストとのバランス。これらをセットで見ると自社の在庫がどうなっているかが明確になります。棚卸の際には期間ごとにデータを集め、売れ筋と売れない商品を分ける基準を決めておくと混乱が減ります。
実務上は日々の発注量と販売ペースを照合する習慣をつけましょう。発注過多を避け、売れ筋を補強するための促販を計画し、売れ残りの原因を分析します。保管環境の見直しや価格戦略の工夫も有効です。継続的な棚卸とデータの検証を続ければ、在庫は資産として機能しやすくなり資金繰りにも良い影響を及ぼします。
この章を読んだ後は、まず自社の在庫がどちらのタイプに該当するかを客観的に判断する練習をしてみてください。判断の基準を決めておくと、実務での意思決定が速く正確になります。
それぞれの特徴と見分け方
不動在庫と不良在庫の違いを見分けるには特徴を比較するのが一番です。
まず不動在庫は「時間の経過とともに売れなくなる」という性質を持っています。市場の需要が変化したり季節性が重なったりして、商品が棚で長く眠る状況が生まれます。回転日数が長くなるほど保管コストも増え、資金の回収が遅れていきます。
一方の不良在庫は「品質に問題があり市場に出せない」という性質です。傷や欠陥、賞味期限切れ、包装のダメージなどが原因で、消費者に渡せない商品を指します。発生すると返品や廃棄処理、リコール対応などの追加コストが生じ、場合によってはブランドに悪影響を及ぼします。
この二つを混同してしまうと対応が遅れてしまいます。見分けのコツはデータと現場の声を組み合わせることです。
例えば以下の指標を使って日常的に管理しましょう。
- 回転率と回転日数の計算
- 賞味期限や品質チェックの結果の記録
- 販売促進の効果と在庫の変化の関係
表を使って整理すると分かりやすいです。以下の表は比較の軸を整理しています。
また棚卸の結果は数字で示すとわかりやすいです。例えば売上の変化率や回転率などの指標を使い、改善の方向を決めます。
このように日々のデータと現場の実感を組み合わせることで、在庫の状態を正しく判断でき、適切な対策を選ぶことができます。
長期化する不動在庫には需要予測の改善や販売促進の工夫、在庫の再活用案が有効です。不良在庫には品質管理強化と適切な廃棄処理や返品交渉が重要です。いずれも現場のデータと実務の経験を組み合わせて、適切な判断と迅速な対応を繰り返すことが鍵です。
不動在庫の具体例と原因
不動在庫の具体例と原因を詳しく見ていきます。具体例としては季節外れの冬物ダウンジャケットが季節を越えて売れ残るケース、旧モデルの家電が新モデルの登場で需要を失い在庫が残るケース、流行の変化により需要が急減して長く倉庫に眠るケースなどが挙げられます。原因は大きく三つです。需要の過小評価、発注のしすぎ、販売機会の損失です。現場の対策としては発注量の見直し、価格の段階的な引き下げ、在庫の再活用(別市場への転用やリースなど)、クロスセルの提案、マーケティング戦略の改善などが考えられます。これらを組み合わせると不動在庫の減少につながります。現場の事例として、季節商品を season end に特価で販売する、在庫を地域限定で販売するなどの工夫が挙げられます。長期的には需要予測の改善と在庫の透明性を高めることが重要です。データを使って動向を理解することでリスクを減らせます。
不良在庫の具体例と対策
不良在庫の具体例としては賞味期限切れの食品、包装の損傷、製造時の欠陥品、返品検査で品質不良が見つかった商品などが挙げられます。不良在庫を放置すると売上機会を奪うだけでなく、廃棄コストや返品対応の負担も増え、最悪の場合法的リスクにもつながります。対策としては品質管理の強化、サプライヤーへの返品交渉、欠陥品の隔離と早期処理、法規制に沿った適切な廃棄、リファービッシュや部品取りなどの再利用方法を検討することが大切です。日常の現場では商品ラベルと有効期限の管理を徹底し、期限が近いものは先に販売する順序管理を実践します。これにより不良在庫の増加を抑え、ブランド価値を守ることができます。
友達と学校の購買部の棚を眺めながら話していた。
私は不動在庫の話をすると友達は「それは眠っているお金みたいだね」と笑いながら言った。私は「眠っているだけで価値があるが、眠らせておくとコストもかさむ」と返すと、友達は「需要を読んで動かせば資金の流れがよくなるんじゃないか」と気づく。そこからデータ活用の話になり、需要予測と販促の組み合わせが大事だと確認。さらに在庫の部門間で連携することの重要性を語り合い、最終的には在庫を資産として活かすコツは状態と需要をセットで見ることだと結論づけた。結局、在庫の正体は数字と現場の知恵の両輪で動くという気づきだった。





















