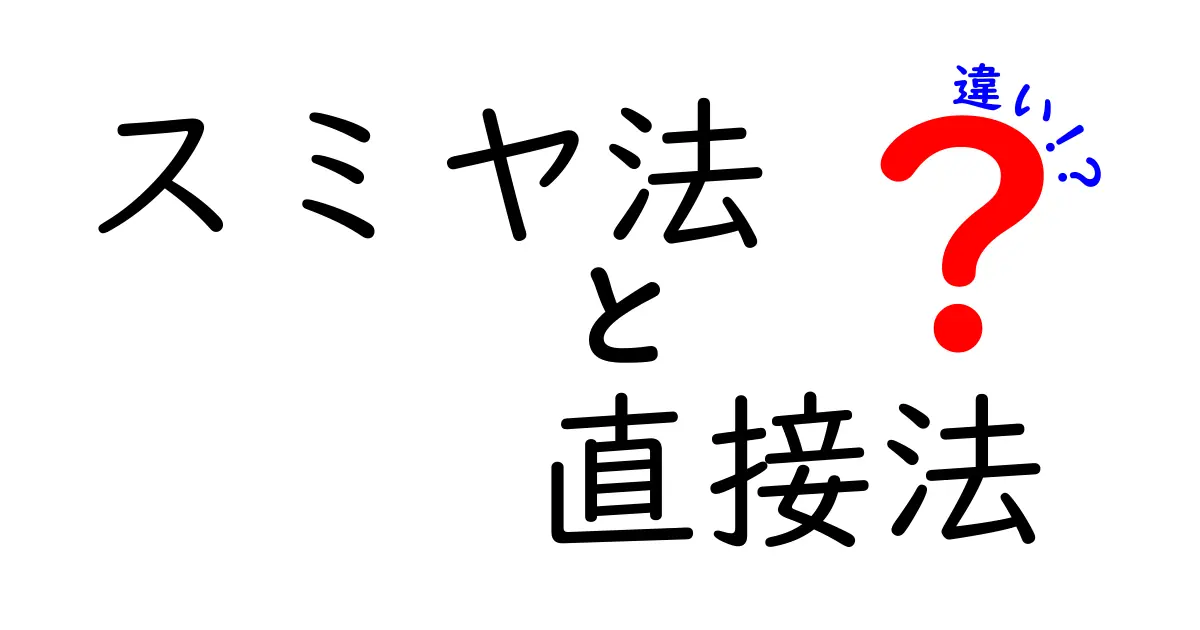

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
スミヤ法と直接法の違いを徹底解説
スミヤ法と直接法は、データをどう整理して結果を出すかという根本的な考え方の違いを表す言葉です。日常生活でも、情報をまとめるときには「総計から割り出す」タイプと「一つひとつ確認してから結論して結ぶ」タイプがあり、ビジネスの現場ではこの2つの考え方を適切に使い分けることが大切です。たとえば、クラス全体の成績を一度に平均して決めるときはスミヤ的発想に近い扱い方になります。一方で、個別の成績を一つずつチェックして、個別の補正をかける場合は直接法的な考え方が活きます。
以下では、まず基本の考え方を整理し、次に具体的な場面での使い分けのポイントを、分かりやすい例とともに紹介します。
最後には、実務でのコツや注意点もまとめます。
読み進めるうちに、「どちらを選ぶべきか」が自然と見えてくるはずです。
スミヤ法とは何か?基本的な考え方
スミヤ法は、データをまず大きな枠組みでまとめ、総額や総量を先に算出してから、個別の内訳を割り当てるやり方です。たとえば、学校の予算を決めるとき、各部門の必要な金額を個別に集めるより、全体の予算を先に決め、その後で各部門の比率を使って配分するようなイメージです。こうすると、全体としての調和が取りやすく、計算の安定性も高まります。もちろん、実務では「どこまでを集合データとして扱うか」という線引きが大切で、データの粒度をどこに置くかが成果の質を左右します。
スミヤ法の流れにはいくつかの共通パターンがあります。第一に「総額を決めてから内訳を埋める」方法、第二に「カテゴリ別の合計を作ってから同じ基準で比率を適用する」方法、第三に「過去データの傾向を使って比率を推定する」方法などです。
このうち、どのパターンを選ぶかは、データの安定性、更新頻度、説明する相手の理解度によって変わります。
また、スミヤ法は総計やカテゴリの合計を先に作る性質から、現場のデータを直接使わず、全体像を掴むのに向いていることが多いです。つまり、「全体像をすばやくつかむ力」が強みになります。
直接法とは何か?どんな場面で使われるか
直接法は、データの個々の要素をそのまま使って、結果を直接計算する考え方です。スミヤ法が先に総量を作るのに対し、直接法は現場のデータをそのまま結論へ結びつけます。例えば、製造ラインで作業時間を各作業に割り当てるとき、顧客ごとの売上をその場で集計する場合などです。
直接法の長所は「柔軟性」と「適用範囲の広さ」です。欠点としては「データ量が多いと計算が重くなる」ことや「誤差の原因を追いにくい」ことが挙げられます。現場の管理者は、入力データの正確さと更新頻度を重視し、場合によってはサンプリングやデータ整理の工夫をします。
直接法は、データが新鮮で個別に追える状況で強みを発揮します。
今日はこの話を友だちと雑談する形で深掘りします。スミヤ法と直接法、どちらを選ぶかは、データの性質と求める答えの形によって決まります。たとえば、イベント予算の話題を例にすると、スミヤ法は全体像の調整が速く、方向性をつかむのに適しています。逆に、直接法は一つひとつの要素を重視して細部の正確さを追求します。そのバランスを見つけるには、データの粒度と更新頻度を考えることが大事です。私たちが普段から使っている資料にも、この2つの考え方のエッセンスが混ざっていることに気づくと、資料の読み解き方が格段に上手になります。





















