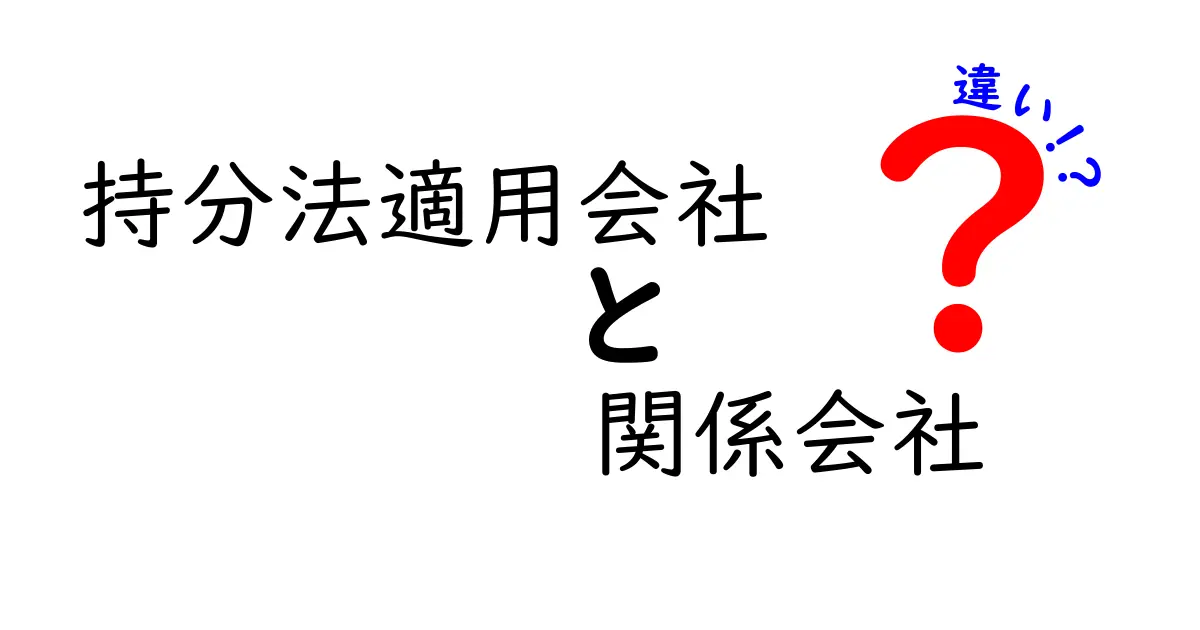

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
持分法適用会社と関係会社の基本を押さえる
持分法適用会社とは、企業グループの中で、他の会社の資本に一定以上の影響力を持つと判断された場合に適用される会計処理のことです。一般的には株式の持ち分が20%から50%程度の関係に当てはまることが多く、投資先の利益や損失を自分の決算に「持分法として」取り入れます。これに対して関係会社は、広い意味で“自分と何らかのかかわりがある会社”を指す用語であり、必ずしも株式の保有割合や会計処理を意味しません。つまり、持分法適用会社は会計処理のルールを伴う特定の関係、関係会社はその関係を広く示す言葉です。
実務的には、影響力の有無と関係の性質を正しく判断することが、財務報告の正確さにつながります。
持分法と関係会社の違いを押さえるポイント
多くの会社は「持分法適用か否か」で損益計算の見栄えが変わる点を知らないと、財務諸表の読み方が難しくなります。ポイント1:適用範囲は株式の割合だけで決まるのではなく、支配力と影響力の程度によって判断されます。
ポイント2:関係会社には何が含まれるかを理解することが大切です。例えば子会社、関連会社、共同支配企業など、名称は異なるものの「自分の企業活動に影響を与える」と判断されれば、開示対象になることがあります。
ポイント3:財務諸表の読み方を身につけるには、投資損益の表記を確認する習慣をつけることが役立ちます。
要点:持分法の適用は会計上の処理ルールであり、関係会社は関係性の総称である点を混同しないことが大事です。
実務での使い分けと注意点
実務では、まず自社がどのような関係を持つ会社と取引しているのかを洗い出すことから始まります。
もし投資先の株式を一定割合以上保有していれば持分法の適用対象となり、投資先の純利益の一部を自社の利益として計上します。反対に、株式の割合が低い場合や別の理由で「影響力があるが支配はしない」状態であっても、関連会社としての開示や特定の取引条件の表示が求められることがあります。
この区別は、財務諸表の信頼性と透明性を保つうえで非常に重要です。
また、企業結合の報告や、共同事業・提携先の契約条件の確認など、日常のビジネス判断にも影響します。
関係会社って、友達関係みたいなものだよね。株を多く持っているわけじゃなくても、共同開発や取引の約束、役員の人事の影響力など、会社同士のつながりは日常のビジネスの中でいくつも生まれる。実務の現場では“関係がある”=開示すべき情報が増える可能性がある、という感覚を持つことが大事だ。とはいえ、関係会社の範囲は広くて、場合によっては持分法適用対象にもなる。つまり、関係は関係でも、具体的な扱いはケースごとに判断する必要があるのだ。
次の記事: 税関と関税局の違いを徹底解説:現場の役割と混乱を解くポイント »





















