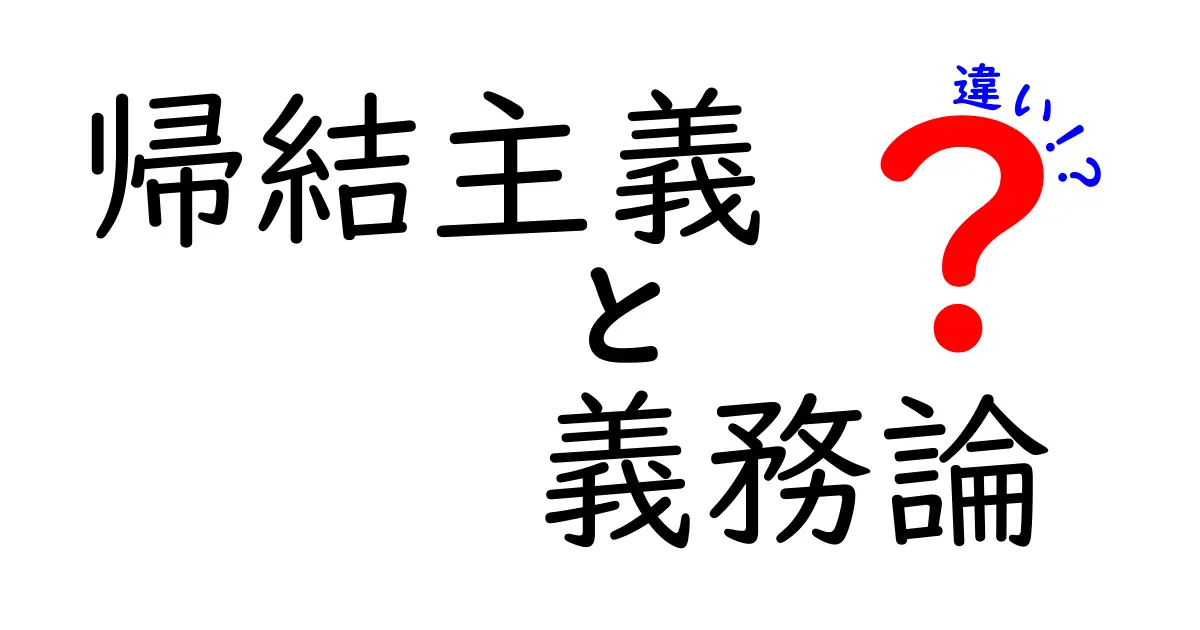

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
帰結主義と義務論の違いを総ざらいする
倫理学の大きな分かれ道のひとつ、それが帰結主義と義務論の違いです。以下で定義と直感を整理します。帰結主義とは、行為そのものよりもその結果を最重要とする考え方です。たとえば、たくさんの人を救う可能性がある行為なら、それが最善の選択だと判断されがちです。これは最大幸福原理と呼ばれることが多く、社会全体の利益を重視します。しかし、少数者の権利が犠牲になる危険性もあり、倫理的な論争の的になります。これに対して義務論は、行為自体が正しいか、道徳法則に適っているかを判断します。カントの理論で有名な普遍化可能性という考え方は、あなたがとるべき行為を「誰に対しても同じ基準で適用できるか」で判断します。つまり、結果の良し悪しよりも、行為の性質そのものが道徳的に正しいかどうかが決断の基準になるのです。こうした違いは、私たちの生活の中の判断にも大きな影響を与えます。
このような比較は、授業だけでなく日常の選択にも役立ちます。帰結主義は状況に応じた柔軟さを提供しますが、少数の権利を軽視する結論に至る可能性もあります。一方、義務論は普遍性を重んじるため、個別の事情を軽んじる場面が出てくることがあります。日常の言い換えをすると、帰結主義は「どうすれば一番良い結果になるか」という問いに近く、義務論は「この行為は普遍的に正しいかどうか」という問いに近いのです。
日常の例で理解を深める:具体的な判断の相違
日常の場面を想像してみましょう。友だちが危険な状況にあるとき、あなたは何をすべきでしょうか。帰結主義なら、最終的な幸福を最大化するために、最大の人を救う選択を正当化することがあります。ただし、誰を救うかの判断を誤ると不正が生まれます。義務論なら、たとえ結果がどうなるか予想が難しくても、嘘をつかない、命令を守るといった道徳法則を優先します。別の具体例として、大切な人を守るために嘘をつくかどうかというジレンマがあります。帰結主義は嘘が結果を改善するなら受け入れられる場面を作るかもしれませんが、義務論では嘘そのものが道徳的に許されないとされます。こうした場面を通じて、私たちは“結末と義務”の間の緊張を理解し、日常の小さな選択にも影響を与える考え方を身につけていきます。
最後に、表で見る違いとして、次のような要約が役に立ちます。
ねえ、帰結主義って言葉、学校の倫理の授業で習うと難しく感じるよね。実は私たちの毎日の小さな選択にも深く関係しているんだ。最近友だちとカフェでこの話をしていて、帰結主義的な判断と義務論的な判断が日常の場面でどう分かれるかを、身近な例で考えました。例えば、友だちが風邪をひいたとき、あなたはどう行動するべきか。帰結主義なら、相手を早く元気にするために、少しの手間をかけて買い物を代わりに済ませるといった“結果の幸福”を優先します。一方、義務論では、約束を守ることや他人の信頼を保つことを最優先にして、危険を避ける具体的な約束事を守ろうとするはず。私はこの二つの考え方がぶつかるとき、結局は「どういう結果が最も多くの人を幸せにするか」と同時に「この行為は普遍的に正しいのか」を両方意識して判断するよう心がけています。結末を変える力と、正しさそのものを守る力、この二つをバランスさせるとき、私たちはより成熟した倫理的判断に近づけると感じます。





















