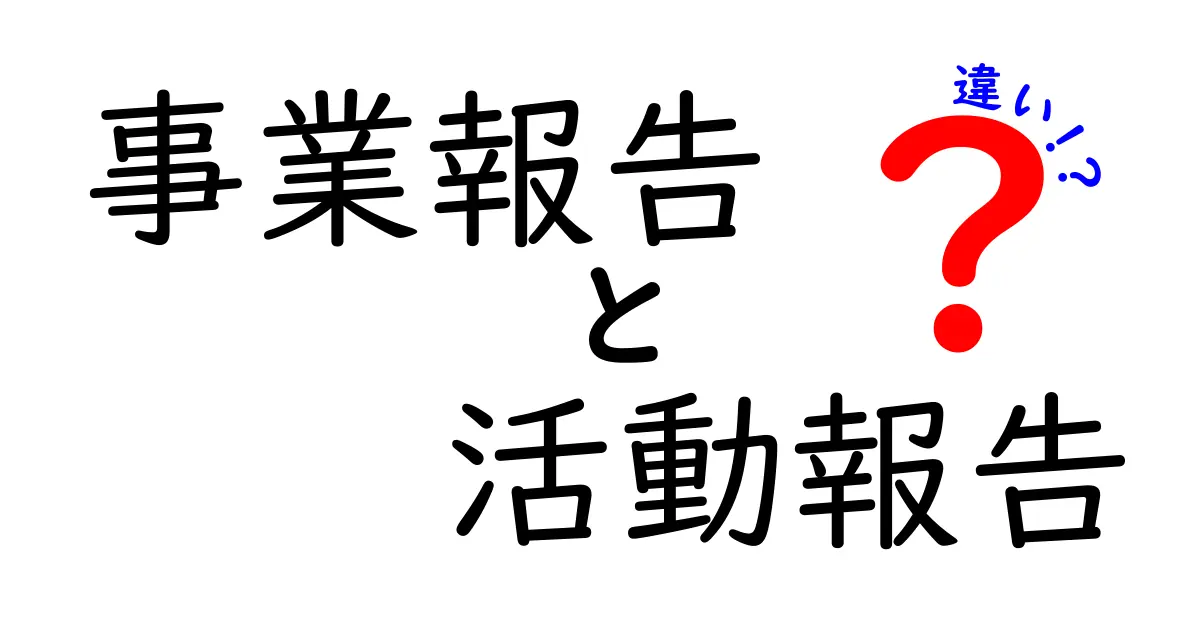

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:事業報告と活動報告の基本的な違いを知ろう
事業報告は企業や団体が一定の期間に行った「事業の結果」を伝える正式な文書です。株主や金融機関、取引先など資金の出入りや信頼関係を左右する読者を想定して作られ、売上や利益、投資の成果、リスクの状況、将来の計画といった事実ベースの情報を中心に並べます。ここでは数字の根拠を示すことが大切で、読み手が次の意思決定をしやすいよう、時系列や比較データを分かりやすく整理します。対して活動報告は、日々の活動そのものを伝える文書で、誰が何をしたのか、どんな成果があったのか、現場の雰囲気や関係者の声といった定性的な情報が重視されます。活動報告は自治体の助成金や寄付を受けている団体、地域の支援者、社内のスタッフなど多様な読者を想定するため、専門的な用語を避け、写真や具体的なエピソードを添えると伝わりやすくなります。さらに、両方を併記するケースも増えていますが、それぞれの読者が求める情報の深さと表現の仕方が異なる点を理解することが、正しい使い分けの第一歩です。
このガイドでは、事業報告と活動報告の違いを分かりやすく整理し、実務での作成手順やチェックリストを紹介します。初心者の方にもイメージしやすいよう、具体的な例や図表の使い方も併記します。結論はシンプルです。事業報告は「数字と戦略の透明性」を、活動報告は「活動の過程と人の関わり」を伝える文書であり、読み手が次のアクションを取りやすいように設計することが大切です。
本記事の要点は三つです。1つ目は読者ごとに必要な情報の粒度を調整すること、2つ目は表現を統一して読みやすさを確保すること、3つ目は図表や写真を活用して理解を深める工夫を持つことです。これから、それぞれのポイントを詳しく見ていきます。
事業報告とは?含まれる情報と読者の想定
事業報告は「事業の結果と今後の方向性」を数字と事実で伝える文書です。読者は主に株主・金融機関・投資家・取引先など、企業の資金の流れや成長性に関心を持つ人たちです。したがって、長さのある説明や具体的な指標の提示が重要で、期間内の売上高・利益・キャッシュフローといった定量的な指標、重要なプロジェクトの進捗、コスト削減の施策、リスク要因とその対応、将来の投資計画などを整理して示します。数字の裏付けと透明性を第一に考え、必要に応じて比較データ(前年同期比、予算対実績、他社比較)を添えると説得力が増します。加えて、事業戦略の要点を短い段落で整理し、読者が次の意思決定をしやすいように「この指標が意味すること」「次のアクションは何か」を明示します。読者によっては専門用語の解説や用語集が役立つこともあります。
とはいえ、長すぎる報告は読みにくくなります。要点を絞り、図表を活用して可視化する工夫が欠かせません。読者がどの程度の深さを求めているかを想像し、必要最低限の根拠とともに、補足資料へのリンクや添付資料の案内を付けるとよいでしょう。
活動報告とは?何を伝えたいのか、誰に読んでもらいたいのか
活動報告は「現場の動きと成果」を伝える文書で、読者は主に地域の支援者、ボランティア、寄付者、自治体関係者、さらには社内の仲間など、組織の活動に関心がある人たちです。ここでは「何をしたのか」「誰が参加したのか」「どんな成果が生まれたのか」を、できるだけ具体的な例やエピソードを交えて紹介します。定性的な情報が中心になる反面、写真・プロフィール・事例紹介・ケーススタディを組み合わせると読者の理解が深まります。例えば、イベントの成功要因や、困難に直面した場面とその乗り越え方、地域への波及効果などを整理すると、読み手は自分ごととして感じやすくなります。感情に訴える情報と具体性の両立を心がけ、読者が支援を続ける理由を見つけられるようにします。読者の信頼を得るには、データだけでなく関係者の声や現場の写真を添えると効果的です。
また、活動報告は頻度や公開タイミングを工夫することで、関係性の維持にもつながります。定例的なニュースレターや月次の報告、年度末の振り返りなど、読み手の生活リズムに合わせて届ける工夫が大切です。
使い分けと作成のコツと実務のヒント
使い分けのコツは、まず読者を想定して「何を知りたいか」をはっきりさせることです。読者が知りたい情報が決まれば、どの情報を前面に出すか、どの言葉を使うか、どの図表を入れるかが自然に決まります。以下の点を意識すると、読みやすく説得力のある報告が作れるでしょう。
・粒度の調整: 事業報告は全体像と財務指標のセット、活動報告は具体的事例と影響のエピソードを軸にする。
・構成の統一: セクションごとに「背景・現状・今後の方針・次のアクション」という順序を崩さない。
・言葉の選択: 専門用語を使いすぎず、読み手の立場に合わせた表現を選ぶ。
・視覚要素の活用: 図表・写真・アイコンを適材適所に配置して理解を促す。
・検証と修正: 閲覧者のフィードバックを受け、分かりにくい箇所はすぐに改善する。
例として、以下の表を使って違いを整理すると理解が早くなります。表を活用すると、文章だけよりも情報の関係性がはっきり見えます。
このセクションの後半では、読者別の具体的な作成手順を示します。
今日は友だちと話していて『事業報告と活動報告、どこが違うの?』と聞かれた。私は少し考えてから、違いは“読者が知りたい情報”をどう届けるかの違いだと答えた。事業報告は数字と戦略の透明性を重視する正式な文書で、投資家や取引先が今の実力を判断する材料になる。一方、活動報告は現場の取り組みや人の努力、社会に与える影響を伝える文書で、写真やエピソードを混ぜて読者の心に響く表現を使う。私たちはこの二つを使い分けて、読者が「次はこれをしてほしい」と思えるような情報の流れを作る。結局は、読者が何を知りたいかを想像して伝え方を変えることが大切だ。違いを理解することが、信頼を生む第一歩になる。





















