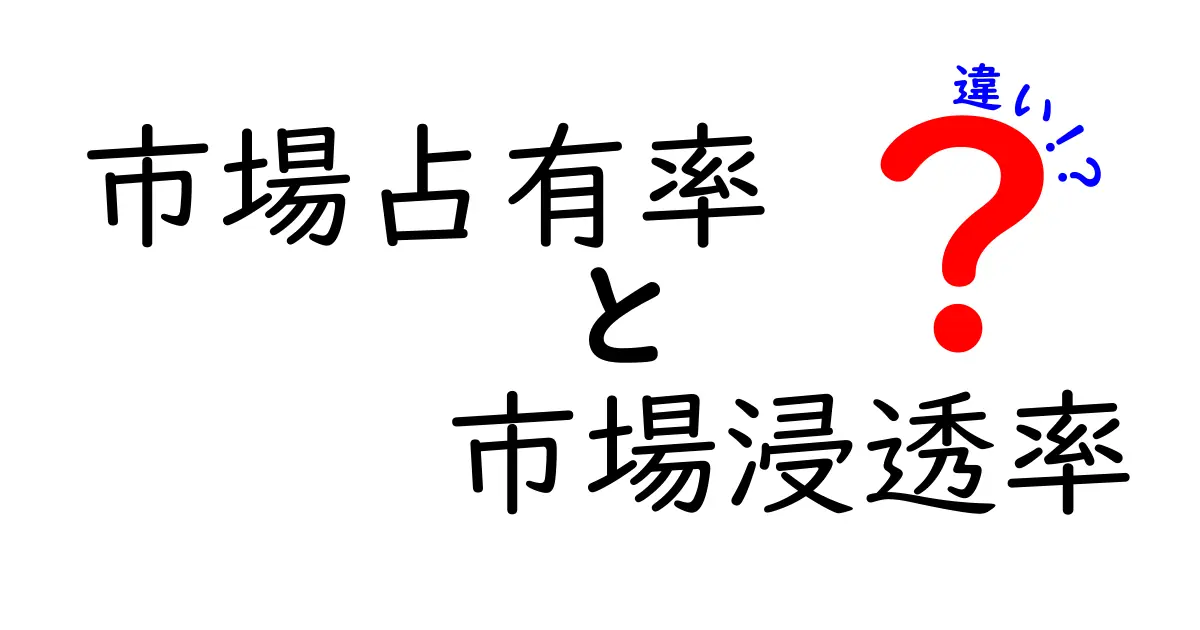

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
市場占有率と市場浸透率の違いを理解するための完全ガイド
このガイドは、中学生でも分かるように、市場占有率と市場浸透率の違いを丁寧に説明します。まずは両者の意味を整理しましょう。
市場占有率とは、ある市場の総額や総規模の中で、特定の企業や製品がどれくらいの割合を占めているかを示す指標です。たとえば、スマホ市場の売上のうちA社が占める割合、あるいは国内コーヒー(関連記事:アマゾンの【コーヒー】のセール情報まとめ!【毎日更新中】)市場での販売数量に対するB社の比率などがこれに当たります。
この指標は、主に競合との比較や自社のポジションを把握するのに役立ち、株主や経営者が戦略を決めるときの「第一の目安」となります。もちろん、売上ベースだけでなく出荷数量ベースや顧客数ベースなど、算出の方法は企業の目的や市場の特性によって変わります。
つまり、市場占有率は「この市場で自社がどれだけの存在感を持っているか」を測る指標であり、競合分析や価格戦略、製品ラインの見直しといった意思決定に直結します。以下では、具体的な例とともにその使い方を見ていきましょう。
市場占有率とは何か
市場占有率は、総市場規模に対して自社の規模がどの程度を占めるかを示す指標です。
例えば、国内のカップ麺市場の総売上が1000億円で、A社の売上が250億円なら市場占有率は25%です。この数字は、競合との位置関係を把握するのに使われます。
ただし注意点もあり、同じ売上高でも「市場全体の成長率」が高い場合には市場占有率は低下して見えることもあります。この点を踏まえ、次のような補足指標と一緒に見ると理解が深まります。
・市場の総規模の変化
・自社の成長率と競合の成長率の比較
・製品別の占有率と市場構造の変化
市場浸透率とは何か
市場浸透率は、ある市場に対して製品やサービスがどれだけ普及しているかを示します。
これは
具体的には、総市場規模ではなく潜在的な顧客数に対し、実際に利用しているユーザーの割合を指します。
例えば、国内のスマホ利用者が1億人、すでにスマホを使っているのが8000万人なら浸透率は80%です。このような数字は、今後の成長余地を示す「天井感」を教えてくれます。
市場浸透率が高い場合は、製品の追加拡張よりも新規市場の開拓が課題となることが多く、低い場合は新規顧客の獲得施策を強化すべき指針になります。
このように、市場浸透率は「どれだけの人が製品を使っているか」を表す指標で、製品ライフサイクルのどの段階にいるかを判断するのに役立ちます。
市場占有率と市場浸透率の違いと使い分けの実務ポイント
両者は似て非なる指標で、それぞれ使い道が違います。
市場占有率は競合比較のための“地図”を描くのに適しています。
一方、市場浸透率は市場がどれだけ成熟しているか、今後の成長余地を示す“天井の高さ”を示します。
実務的な使い分けのコツは次のとおりです。
1) 目的が「他社と自社の相対的位置づけを知る」なら市場占有率を重視する。
2) 目的が「市場全体の普及状況を把握する」なら市場浸透率を重視する。
3) 両方を同時に見ることで、短期戦略と長期戦略を揃えることができる。
4) 数字の間違いを避けるためには、測定の定義(売上基準か顧客基準か)を揃えることが大事です。
5) 成長局面では、浸透率の改善が先か、占有率の強化が先かを判断するための“閾値”を設定すると良いでしょう。
実務では、市場占有率の変化と市場浸透率の変化をセットで追跡することで、製品戦略と販促計画を同時にブラッシュアップできます。
ある日の放課後、友だちのマコトと市場浸透率について雑談をしていた。マコトは『浸透率が高いってことは、みんながその商品を“知っている”だけでなく“使っている”証拠だよね?』と聞いてきた。私は『そうだね。ただ浸透率が高くても、ブランド力が弱いと長期的にはリスクになる。大切なのは“使われ方の多様化”だ』と返した。私たちは日常の買い物の中で、浸透率と占有率の違いを探してみることにした。スーパーで新しい飲料を手に取るとき、まず市場浸透率を思い浮かべ、次に自社の占有率がどう変わるかを考える。結局、数字は人々の選択肢と行動の積み重ねで決まる。





















