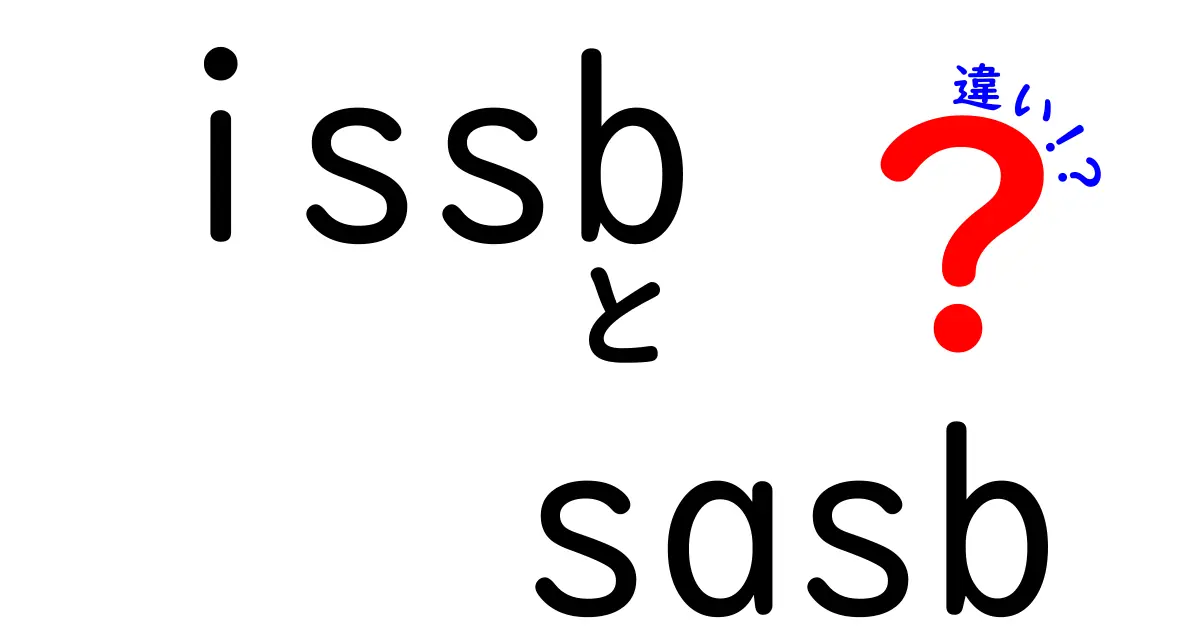

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
issbとsasbの違いを理解する基本ガイド
ESGの世界で「ISSB」と「SASB」はよく耳にしますが、混同している人も多いのが現状です。ISSBは国際的な統一基準を目指す枠組みで、財務情報とサステナビリティ情報を一体として開示できるよう設計されています。一方、SASBは産業別に特化した基準を提供し、主に財務影響を中心に情報を整理します。ここでは、それぞれの成り立ち、狙い、対象、そして実務での違いを丁寧に解説します。
最初に結論を言うと、ISSBは「グローバルな統一性」を目指しており、SASBは「産業別の具体性と財務影響の結びつき」に重きを置く点が大きな違いです。
この違いを正しく理解することで、企業は自社の報告戦略をどう組み立てるべきかを判断しやすくなるはずです。ここから詳しく見ていきます。
ISSBとは何か?
ISSBとはInternational Sustainability Standards Boardの略で、IFRS財団の下で設置された国際的な統一基準を作る組織です。目的は世界各国の企業が同じような視点でサステナビリティ情報を開示できるようにすることで、投資家や金融市場が比較できる情報の土台を整えることにあります。ISSBは「財務と非財務情報の統合」という考え方を重視し、グローバルに比較可能な指標と開示項目の統一性を推進します。また、開示の具体的な要件は複数の地域規制と整合させやすい形で設計されており、企業が海外市場へアクセスする際の負担を軽減する狙いがあります。ISSBのアプローチは長期的な財務計画とリスクマネジメントの一部として、サステナビリティ情報を「財務情報と同じ言語」で語ることを目指します。こうした性質から、ISSBは今後の国際的な開示のスタンダードとして重要性を高めると考えられ、企業の戦略立案にも直接影響を及ぼします。
SASBとは何か?
SASBとはSustainability Accounting Standards Boardの略で、産業別に特化した開示基準を提供する組織です。SASBの特徴は、各産業が直面する財務影響に焦点を絞っており、どの情報が財務上のリスクや機会として投資判断に影響するかを具体的に示している点です。これにより企業は自社の業界特有のリスク・機会を的確に開示でき、投資家は「自分の業界にとって重要な情報は何か」を把握しやすくなります。SASBの基準は地域を超えて使われることもありますが、主な目的は財務影響と企業価値の関係を見える化することであり、投資判断の根拠を強化する助けとなります。SASBは一般に産業別の視点を重視する点がISSBとは異なる重要な特徴です。
違いのポイントと実務への影響
ISSBとSASBの違いを実務に落とすと、以下のポイントが特に重要になります。
1) 目的の違い:ISSBは全球的な統一性を狙い、比較可能性を高めることを重視します。SASBは産業別の財務影響を掘り下げ、実務上の意思決定材料としての価値を高めます。
2) 対象読者の違い:ISSBは世界規模の投資家を想定する一方、SASBは業界内の意思決定者や投資家に対して、業界特有の情報を提供します。
3) 開示の組み立て方:ISSBは「統合レポート的な構造」を促す傾向があり、SASBは「業界別の項目リスト」を中心に組み立てます。
4) 適用範囲と実務負荷:ISSBはグローバルな適用を想定するため、企業の全事業領域を跨ぐ開示が求められる場面が多いです。SASBは業種ごとに絞り込まれているため、業界特有の情報を的確に抽出する力が問われます。
この違いを理解したうえで、企業が取るべきアプローチを整理すると、次の表のように整理できます。項目 ISSB SASB 目的 グローバルな統一性を促進 産業別の財務影響の可視化 対象読者 世界中の投資家・規制当局 産業ごとの投資家・意思決定者 開示の焦点 統合的な情報の土台づくり 財務影響に直結する項目の深掘り 実務負荷 全社的なデータ整備が必要な場合が多い 産業別の詳細データが中心 適用の柔軟性 比較可能性を優先する設計 業界特性に強く寄り添う設計
結論として、ISSBはグローバル市場での比較可能性を高める土台作り、SASBは業界別の財務影響の深掘りと実務への適用性を重視する、という二段構えの理解が実務には最も役立ちます。企業はこの違いを踏まえ、グローバル戦略と産業別戦略をどう組み合わせるかを検討すると良いでしょう。今後、ISSBがより多くの地域で導入されるほど、両者の統合・相互補完の形が現場で現れるケースは増えていくはずです。つまり時代の潮流として「一本化」と「現場の実務性」の両輪を回す視点が重要になるのです。
この記事の情報は2025年時点の動向を基礎にしています。実務での適用を検討する際は、最新の公式ガイドラインや企業の法務・財務部門と連携して判断してください。
今日はISSBとSASBの話を友達と雑談する感じで小ネタをひとつ。ISSBの話をすると、よく『世界中の企業が同じデータを同じ言葉で語れるかどうか』が大切だと感じるんだって。 SASBの話題になると、なんか“業界ごとに隠れている財務上の影の部分”を明るく照らす懐中電灯のようだなあと感じる。つまりISSBは“全体像の地図作り”を、SASBは“特定の道具(財務影響)を業界別に整える”ことを得意としている。こう聞くと、企業は“統一と実務の両方をどう組み合わせるか”を検討する良いヒントになるよ。私たちの学校の進路選択みたいに、大きな枠組みと細かな現実の両方を見渡すことが大事なんだ。フィールドワークのように、資料を赤字で塗りつぶしながら、どの情報が投資家にとって本当に価値があるのかを探る楽しさがある。ISSBとSASBは、そんな“情報の地図と道具”の役割を分担してくれている、そんな感じで理解すると話がスッと入ってくるよ。





















