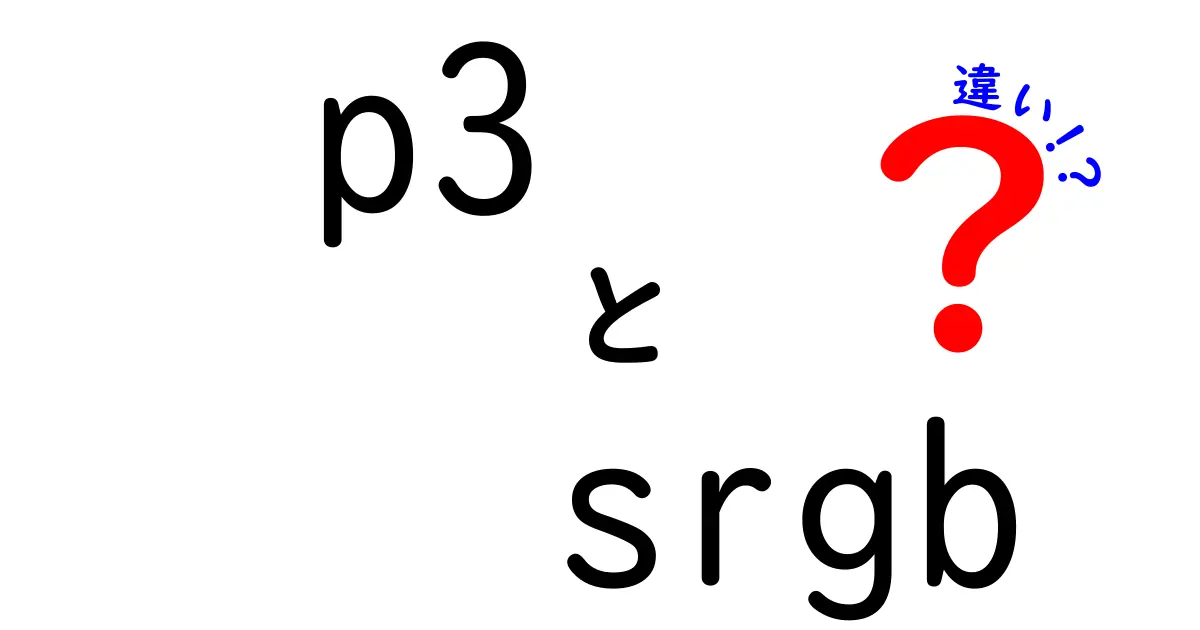

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
P3とsRGBの違いを初心者にもわかりやすく徹底解説する完全ガイド。色空間とは何か、なぜ色が違って見えるのか、どちらを使うべきかを日常の写真・映像制作・デジタルデザインの場面に合わせて具体例とともに解説します。この記事を読めば、ウェブサイトの画像を表示するときの色の崩れを防ぐ方法、写真の現像で色を正しく再現するコツ、そしてディスプレイを選ぶときの判断材料が手に入ります。さらに、互換性の問題やICCプロファイルの役割、色の管理の基本となるガンマと白点の意味も分かるように整理しています。初心者向けですが、専門用語を極力噛み砕き、図解の代わりに実例と比喩を用いて紹介します。
色空間はデジタル画像の“色の約束事”のようなものです。人の目は光の波長を感じ取り、それを脳で色として認識しますが、現実の光源やカメラ・モニターは同じ色を厳密に再現してくれるわけではありません。そこで色空間という“規則”が必要になります。この記事では、まずP3とsRGBという2つの色空間の違いを基本から説明します。sRGBはウェブや多くの写真の標準として広く使われ、互換性が高いのが特徴です。一方Display P3は緑と赤の領域が広く、現代のApple製機器で多く採用されているため、同じ写真を表示する場合でもデバイスによって色の印象が大きく変わることがあります。したがって、適切な色空間を選ぶには“出力先”を意識することが第一歩です。もし出力先がウェブ中心ならsRGBを優先し、モバイル端末やMacの高性能ディスプレイで正確さを追求するならDisplay P3を調整の軸にするのが現実的です。
この章ではP3とsRGBの技術的な違いを分解します。色空間の定義、ガンマカーブの挙動、色域の広さの意味、CIE 1931の座標系との関係、ICCプロファイルの役割、ガンマ補正の実務影響、モニター表示の設定とキャリブレーションの手順、ソフトウェアでの色空間設定の注意点、Webとモバイルの表示差を見極める方法を、具体的な事例と数値の比較表を交えて解説します。さらに、動画制作・写真編集・ウェブデザインの現場で発生しやすい誤解を取り除くために、色域が広いほど常に良いという誤解、カラーマネジメントの順序、色温度の選択肢、モニターの色再現を信じるときの注意点、そして最終的な出力先での変換の要点を、初心者にも理解しやすい対比と例で丁寧に紹介します。
- 色空間は“見え方のルール”
- 出力先を最優先に考える
- ICCプロファイルでデータを正しく伝える
- モニターのキャリブレーションは定期的に行う
放課後、友達と色空間の話をしていて、sRGBはウェブの標準だから安心して使える、けれど現代の多くのモニターがDisplay P3の色域をサポートしているので、写真や動画の現像ではP3を選ぶ場面が増える。結局は“出力先を決めてから色空間を選ぶ”というシンプルな結論に落ち着く。だから部活の作品も、ウェブ公開か印刷か、仕上げの環境を事前に決めておくと、色のギャップに悩む時間が減る。





















