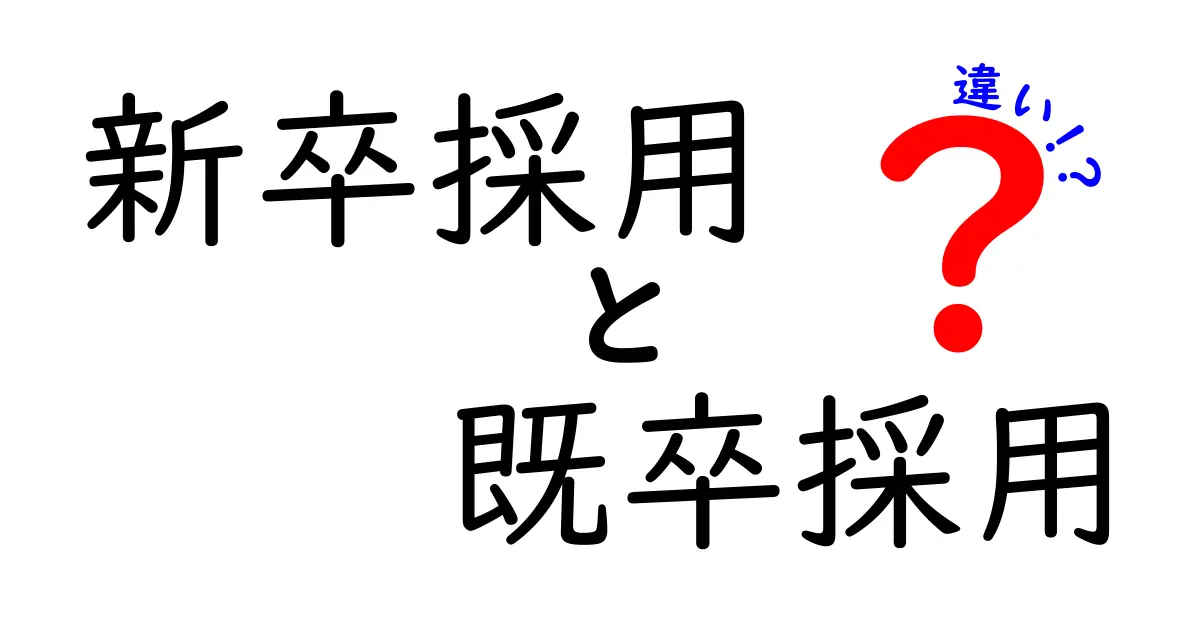

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
新卒採用と既卒採用の基本を理解する
就職活動の世界には「新卒採用」と「既卒採用」という言葉がよく出てきます。新卒採用は卒業予定の学生や現在在学中の人を中心に採用する方法で、企業は学生の「未来の成長ポテンシャル」に期待します。対して既卒採用は卒業後すぐに就職を希望する人や、1年、2年と社会人経験を積んだ人などを対象にします。通常、就職市場の動きは年度ごとに変わります。新卒採用は季節性が強く、春〜夏に募集が集中し、内定を出すタイミングも学年の進行に合わせて計画されます。既卒採用は通年で動く企業も多く、年度をまたいだ募集も見られます。ここで大切なのは、応募者側が自分の現状に合ったルートを選ぶことです。
就活を始めるタイミングは人それぞれです。自分の学年・卒業時期と、企業の募集スケジュールを照らし合わせて動くと良いでしょう。
新卒採用と既卒採用の違いを理解するには、企業側の考え方も知っておくと役に立ちます。新卒は教育コストが低いとみなされ、研修制度が手厚い場合が多い一方、既卒は即戦力の期待が高く、基礎的なビジネスマナーや専門的なスキルの証拠が重視されます。2つの道は、選ぶ人の状況と目標によって適しているかが変わります。
応募条件と選考の流れの違い
応募条件は、新卒採用では「学歴」や「年齢制限」よりも「潜在的な成長性」が重視され、面接やグループディスカッション、適性検査などが中心です。
一方、既卒採用は卒業後の実務経験や資格、成果物など、即戦力を示す材料が評価されやすくなります。企業によっては「ブランク期間の説明」が必要になることもあります。
選考フローの差も覚えておくと良いです。新卒はエントリーから内定までの期間が長く、面接回数が複数回になるケースが多いです。履歴書・エントリーシートの提出→筆記試験→小グループ面接→集団討議→最終面接など、段階的なプロセスが一般的です。対して既卒は、経験を証明する資料があると評価が進みやすく、面接の比重が高めになることがあります。場合によっては書類選考が省かれることや、即日内定が出ることも珍しくありません。
就活生・企業側のメリット・デメリットと実践ポイント
新卒採用のメリットとして、企業は教育コストが比較的低く抑えられ、長期的なキャリア形成を前提に人材を育てやすい点があります。就活生にとっては、企業の教育制度が整っており、社員の成長をサポートしてくれる環境を手に入れやすいという利点があります。
デメリットとしては競争が激しく、内定までの道のりが長いことです。内定の数は限られており、複数の選考を受ける必要があります。既卒採用のメリットは、実務経験を活かして早く現場で貢献できる点や、自己PRで具体的な成果を示しやすい点です。
デメリットとしては、ブランク期間の説明や年齢的な制約が生じる場合があることです。就活では自分の強みを明確に伝える準備と、企業のニーズに合わせた自己PRの設計が重要です。
実践ポイントとしては、インターンシップの活用、課外活動でのリーダーシップ経験、資格取得、ポートフォリオの作成など、具体的な材料を期日内に揃えることが大切です。
企業側の視点を意識して、履歴書には成果を数値で添えると説得力が増します。自分の現状に合ったルートを選び、計画的に準備することが、就活を成功させる鍵です。
最後に覚えておきたいのは、人材市場は常に動いているという事実です。時期や業界によって動向は変わるため、最新情報をチェックし、柔軟に対応することが大切です。
友人とカフェで新卒採用の話をしていたとき、僕は将来の不確実性に不安を感じると言いました。彼は『でもポテンシャルと熱意は数字では測れないけれど、伝える材料は工夫次第で増やせるんだ』と答えてくれました。その言葉が新卒採用の現実を端的に表していました。企業は未来の成長を見たいので、インターンの成果や部活のリーダー経験など、さまざまな材料を活用して自分をアピールすることが大切です。私たちは自分の経験を整理し、企業に伝える準備を進めるべきだと感じました。





















