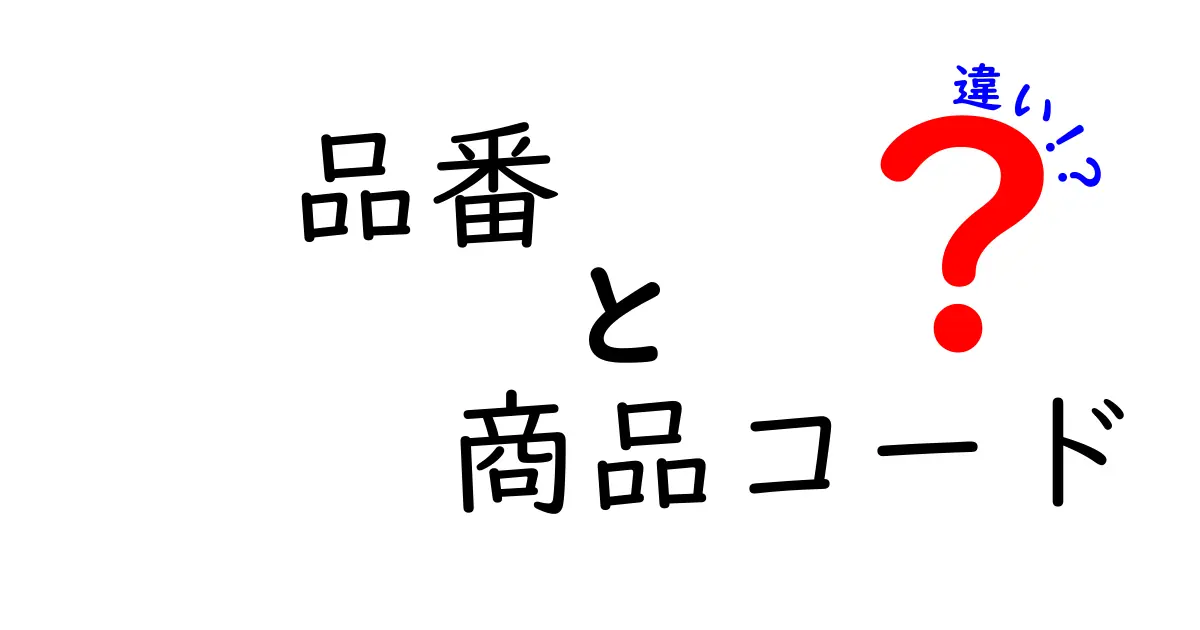

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
品番と商品コードの基本をじっくり学ぼう
品番とは企業が自社の商品を識別するためにつける「品目番号」のことです。一般的には同じブランドの中で特定のサイズ・色・仕様を示す固有の番号として使われ、製造段階の管理や在庫の検索、発注の際に現場で最もよく見られます。
一方で商品コードはショップやデータベースが item を管理するためのコードです。販売チャネルごとに異なるコードを割り当てることもあり、POS端末やECサイトの在庫管理、注文処理、請求処理といった実務の核となります。
重要なのはこの二つが混同されがちですが、役割が異なるという点です。品番は「何を作ったのか」を指し示す固有の識別子であり、商品コードは「どのように自社で扱うか」を決める運用上の識別子です。
この区別を知ることで、在庫検索のときに原因検索が早くなり、顧客に渡す説明も一貫します。
まず覚えておきたいポイントは品番は製品固有の識別子、商品コードはデータ管理の識別子であるという点です。
また、実際の運用では品番と商品コードが一緒になる場面もあります。たとえば特定のカラーバリエーションやサイズが一度作られた後、販売チャネルに合わせて別のコードが付与されることがあり、それが混乱の原因になることも。そんな時は「どのコードが内部処理用で、どのコードが顧客向けの表示用か」を関係者で共有することが大切です。
この章では前提を押さえ、次の章で実務での違いがどう表れるかを具体例で見ていきます。
特に新しい商品を導入する場面や、在庫を整えるためのデータベース設計の際には、品番と商品コードの役割分担を明確にしておくと後で修正が楽になります。
この区別を最初に定義しておくと、社内の混乱を避け、顧客への案内もスムーズになります。
品番と商品コードの違いを具体的な場面で想像する
例えばオンラインショップを運営しているとします。ある靴の「黒・LLサイズ」は品番が同じでも、ECと店舗で扱う商品コードが異なるケースがあります。ECでは商品コードを使用して在庫を引き当て、店舗では別のコードが使われることがあり、販売データを統合するときに工夫が必要です。
ここでのポイントは「顧客に表示されるのは品番や名称が主になる場合が多く、実務上の処理は商品コードが基盤になることが多い」という点です。顧客には品番と名称が伝わるのが自然ですが、店舗の発注やシステムの連携は商品コードが基盤になることが多いです。
この区別を理解しておくと、商品の仕様変更があったときにも、どのコードを更新すれば全体に反映されるかが明確になります。さらに、データベース設計のときには「一商品につき一つの品番・一つの主要コード」というルールを作ると整合性が保たれやすくなります。
実務での使い分けと注意点
実務の現場では、品番と商品コードを混同しないための運用ルールを社内で決めておくことが重要です。
まずは「品番は製品そのものを指す固有の番号」として社内資料に明記します。
次に「商品コードはシステム上の管理コード」であり、チャネルごとに複数存在し得ることを認識します。
ここで出てくる注意点は、商品アップデートやリニューアルのときに品番を変えずに商品コードだけ変えるケースがある点です。顧客向け表示のSKUは変わらなくても、在庫管理システムのコードだけが更新されると、検索性が落ちたり、データの整合性が崩れたりします。
このような事態を防ぐには、変更履歴をきちんと追跡し、定期的に在庫レポートを照合して、二つの識別子の対応表を最新に保つことが大切です。
結論として、品番と商品コードは役割が異なるため、明確な運用ルールと文書化が最適な管理を生み出します。
ねえ、品番と商品コードの違いって知ってる? ぼくは在庫を整理していたころ、同じ商品に二つのコードがあると現場が混乱するのを何度も見てきた。品番は“その製品そのもの”を指す固定の識別子で、商品コードは“データベース上の管理コード”として運用される。つまり表示は品番が顧客向け、処理はコードが中心。ECと実店舗でコードが違うこともあるから、対応表を作っておくと混乱を防げる。こうしたルールを整備するだけで、発注ミスや棚札のズレがぐんと減るんだ。結局、二つのコードは同時に使われるべきで、それぞれの役割をクリアにすることが、現場の作業を楽にしてくれるんだよ。
前の記事: « 供給元と供給源の違いを徹底解説|現場で使える使い分けのコツと実例





















